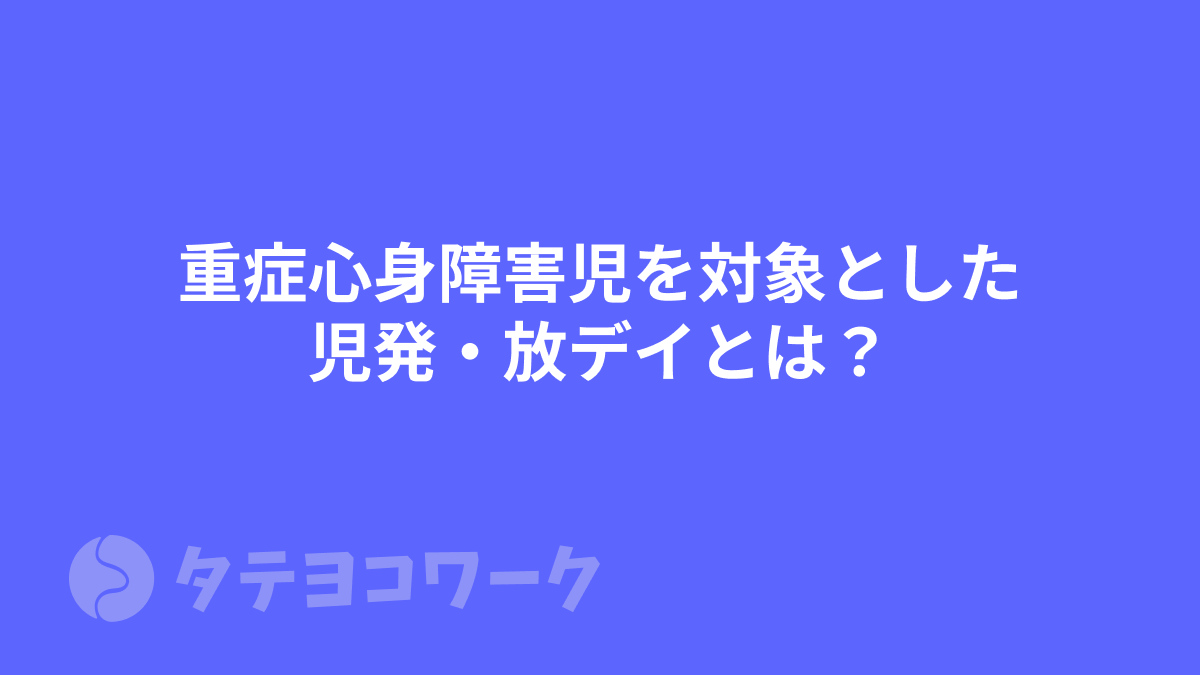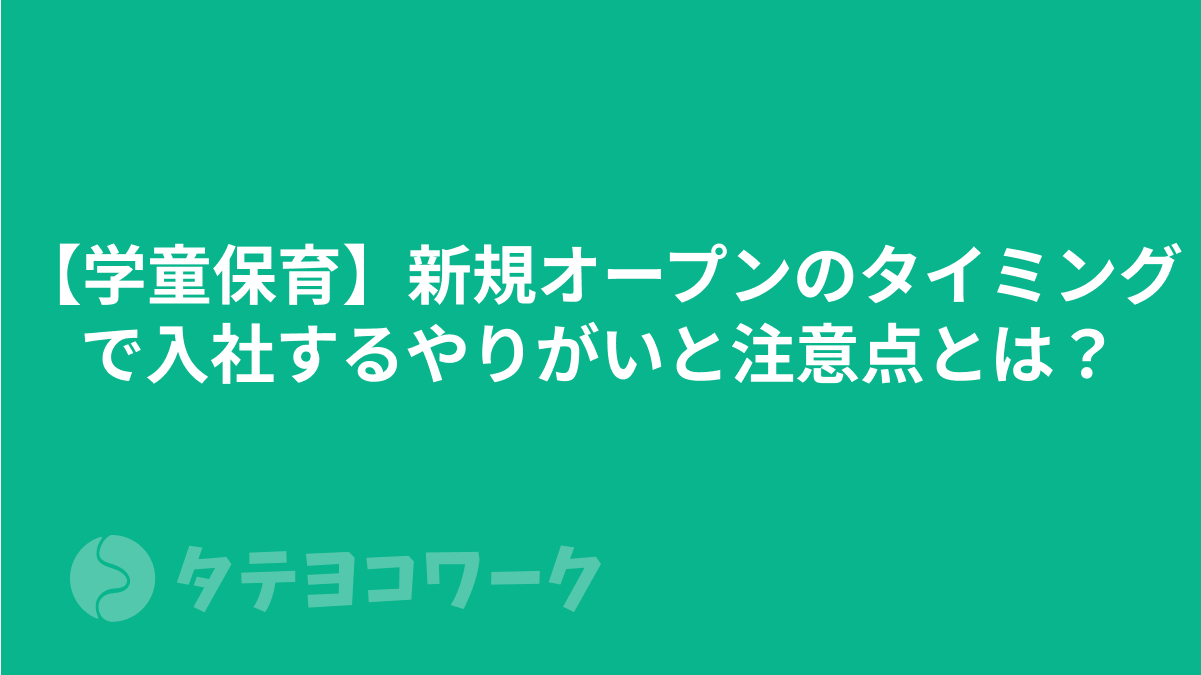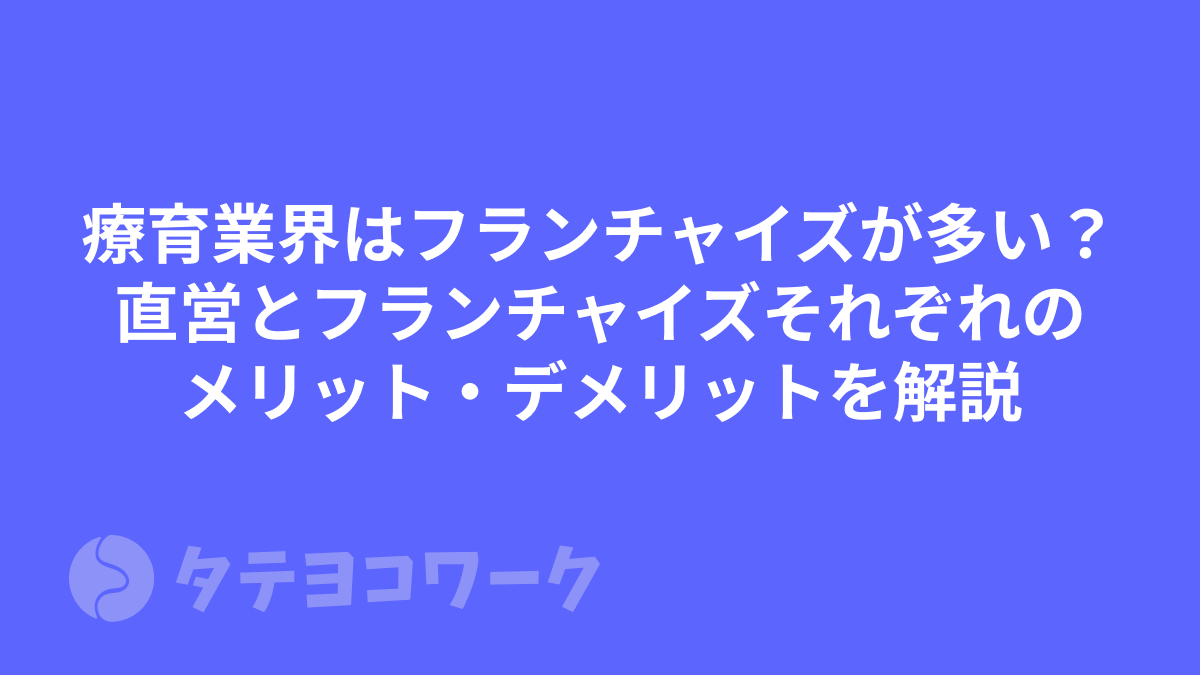タグで絞り込む
キーワードから探す
非認知能力を育むために学童保育が果たす役割とは?
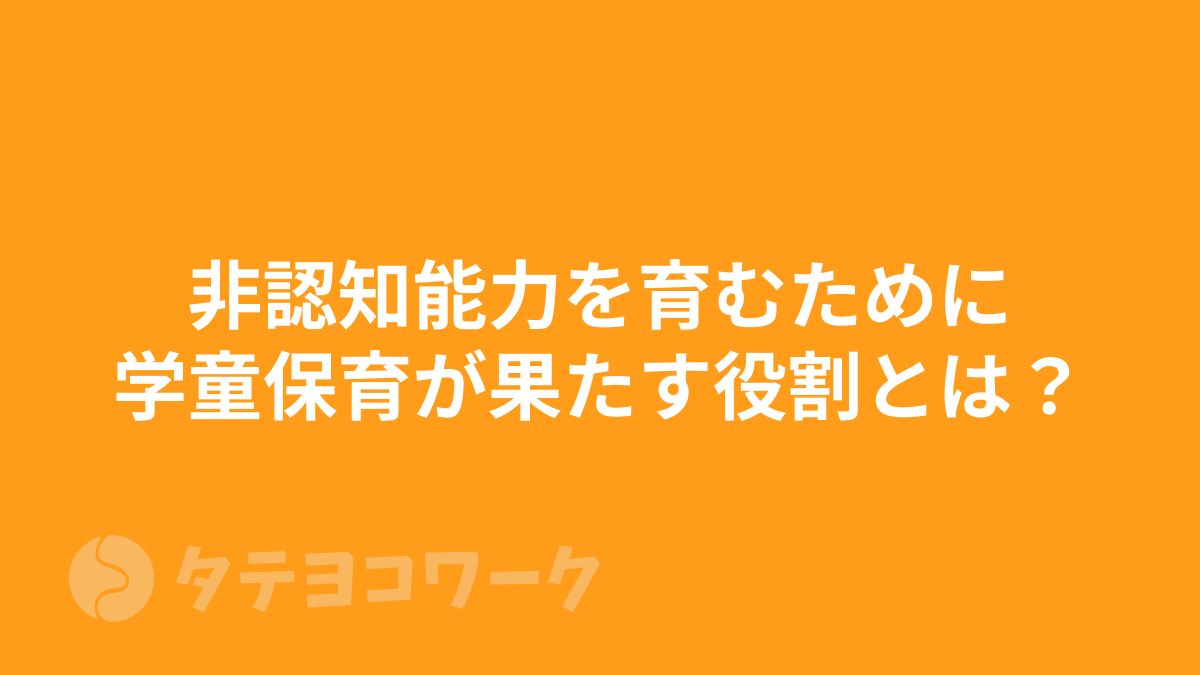
学童
公立学童
民間学童
放課後児童支援員
あそび
非認知能力
共働き世帯の増加に伴い、学童保育の需要は年々高まっています。
かつては「子どもたちを安全に預ける託児施設」としての役割を求められていた学童保育でしたが、最近では「子どもたちが非認知能力を育む場」としても注目を集めています。
では、学童保育はどのようにして子どもたちの非認知能力育成を支えているのでしょうか?
非認知能力とは?
近年、頻繁に耳にするようになった非認知能力という言葉。
非認知能力は、主体性や忍耐力、共感力や自尊心などのことをいいます。
これらの能力は、学校のテストや学力偏差値では測ることができないため「目に見えない・数値化できない力」といわれており、これからの社会を生き抜いていくための基盤となる力でもあります。
なぜ非認知能力は重要なの?
非認知能力が重要だといわれている大きな理由のひとつに、「AIに代替されない能力」であることが挙げられます。
AIは膨大なデータを分析したり高速で正確な計算をしたりするといった認知能力が非常に優れていますが、感情や周囲との対人関係を基にする「判断力」や「柔軟性」といった非認知能力の部分は非常に未熟です。
チームで協力をして仕事をする時、自分の意見を主張したり相手の話を聞いたりして対話やコミュニケーションをする時、子育てや教育をする時、0から何かを創造する時など、非認知能力が求められる場面は社会において数多く存在しています。
そのため非認知能力は、AIとともに生きていく未来の社会で非常に重要な役割を果たすと考えられているのです。
また、グローバル化の進展も非認知能力の重要性を高める要因の一つです。
海外の国々や異文化との交流が日常化していく中で、積極的にコミュニケーションを図りながら多様な価値観を受け入れ、適応する力が求められるためです。
言語の壁はAIやテクノロジーの技術によって取り除かれていくと予想されますが、異なる意見や文化を受け入れる共感力や、問題解決のためのコミュニケーションスキルなどの非認知能力を伸ばしていくことは、これからを生きるこどもたちにとって非常に重要なことです。
学童保育が担う新たな役割
実は学童保育は、こうした非認知能力を育てる絶好の場と言えます。
なぜなら、学童保育は学校のような「子どもたちの基礎学力(認知能力)を身につけてもらう」という役割を持っているわけではなく、「子どもたちの自主性や主体性、社会性などを伸ばすこと」が目的のひとつである場所だからです。
定期テストやコンテストなどで子どもたちの評価をしたり競い合わせたりする必要が無く、一人ひとりの好奇心や興味に応じた個別最適な活動を見守ることができます。
そのため学童保育は、「勤労などで放課後の時間に保護者の適切な保護を受けられない子どもたちを安全に見守る」という役割だけでなく、「放課後の豊かな時間を使って非認知能力を伸ばす場」としても注目されてきているのです。
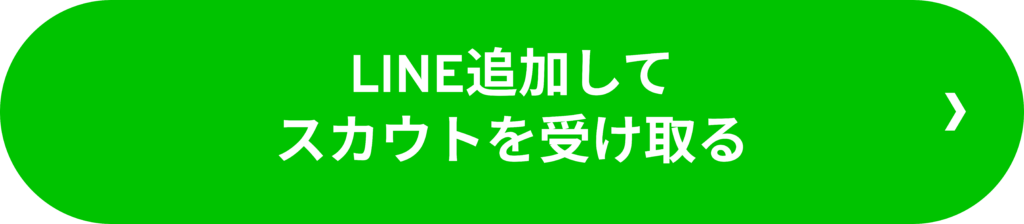
学童保育における非認知能力育成例
学童保育では、日々の自由遊びや異年齢交流を通して、子どもたちは協調性や自己表現力を学んでいくことができます。
①自由遊び
学童保育の場では、自由遊びの時間が多くを占めています。大人や他者によって決められた活動をするのではなく、自分が「やりたい!」と思う遊びに熱中することで子どもたちは自然と好奇心や想像・想像力、集中力を伸ばしていきます。家には無い玩具や大型の遊具、豊かな自然環境などがある場での自由遊びは、より大きな成長に繋がります。
様々なことに対して失敗を恐れずに好奇心のままに挑戦をする経験は、学童保育だからこそ提供できる貴重なものといえます。
また、子どもたちは遊びを通して他者との関わりを学ぶこともできます。鬼ごっこやおままごとなどの集団遊びの場合はもちろんのこと、例えば、積み木を一緒に組み立てたりブロック遊びをしたりするだけでも、コミュニケーションは自然に生まれます。
特定の友達だけでなく、異年齢の子どもたちが一緒に過ごしている環境の中で対話をし、共通のルールを決めたり守ったりすることで社会性が身についていくのです。
②イベントの企画・運営
各施設の運営方針にもよりますが、子どもたちが主体となってイベントを企画したり運営をしたりする学童保育も数多くあります。
学童保育の定番イベントであるお化け屋敷やこどもまつり、ハロウィンパーティーやクリスマスパーティーなど季節の行事を企画する際に子ども会議を開くことで、意見の違いを乗り越えて話し合いをしたり、それぞれの強みを活かした役割分担を考えたりすることができます。
自分の意見を主張すること、それを誰かに認めてもらうこと、他者の意見を受け入れてみんなが納得する形に落とし込んでいくこと、それらはまさにこれからの社会で必要となる非認知能力を育む重要な体験であるといえます。
子ども同士の会議は、職員の支援(=ファシリテーション)が必須といわれています。議論が行き詰まったり本題から逸れてしまったりする時、意見をうまく言葉にできず困っている子がいたりする時などに職員が適切にサポートをすることで、子どもたちは自信を持って楽しみながら話し合いに臨むことができます。
学童保育で非認知能力を伸ばすための課題
このように、学童保育はこどもたちの非認知能力を伸ばす場として非常に適している一方で、以下のような課題も挙げられます。
①学童保育利用人数の増加
日本は現在少子化ではあるものの、共働き家庭の増加により、多くの地域で学童を利用する子どもたちの人数は年々増えています。結果として、待機児童が発生していたり、施設の規定人数を大幅に超えた利用者が登録されていたりする学童保育が全国に存在しています。
学童保育を希望しても利用できない家庭があることは大きな課題である一方、「子どもたちの健やかな成長と安全を確保する」という意味では、規定人数以上の子どもたちが過ごしている学童施設についても問題視する必要があります。
規定人数を大幅に超えた大人数での保育は、事故や怪我の発生が危惧されるだけでなく、上述したような個別最適な支援が難しくなり、職員がこどもたちをまとめるための無理やりな集団行動や一斉指示が増えてしまう可能性も高まるのです。
学校の教室1つ分の大きさに100人以上の子どもたちが過ごしているような学童保育も数多く存在しているため、狭隘環境の緩和などの早急な対応が求められています。
②職員の人手不足・質の担保
学童保育利用の子どもが増えればその分職員を配置していく必要がありますが、学童保育の現場において、全国的に慢性的な人手不足が課題となっています。
そのような余裕のない環境の中で職員研修や勉強会の場が設けられていない学童保育もあり、知識の浅い職員による非認知能力を伸ばすには不充分といえる支援が行われている場合もあります。
学童保育の職員は単に子どもとたち遊ぶだけでなく、一人ひとりをじっくり観察して適切な声かけや見守りをし、保護者とともに子どもたちの成長を支援する重要な役割を持った職業です。
子どもたちの非認知能力を伸ばせるような質の高い学童保育職員がさらに増えていくよう、職員に対する労働環境改善や世間の認識改革が求められます。
学童保育の未来へ向けて
学童保育は単なる「子どもを預ける場所」から「子どもの未来を築く場」へと進化しています。
これからの時代、学童保育は子どもたちが自分の可能性を最大限に引き出し、非認知能力を育むための環境を提供する重要な役割を担っていくと考えられます。
そのためには、職員の人手不足といった課題を解決しながら子どもたちが安心して過ごせる環境を整えていく必要があります。
社会全体が学童保育の価値を認識して支えていくことで、次世代を担う子どもたちの健やかな成長に繋げていきましょう。
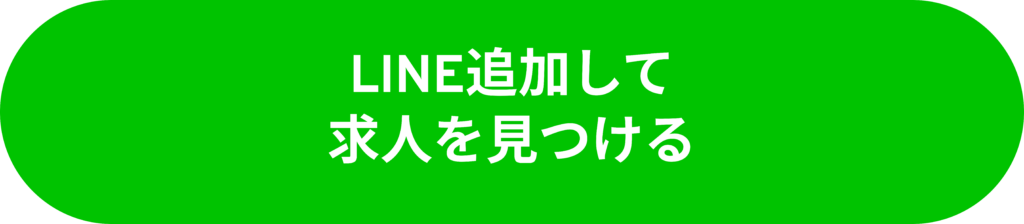
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。