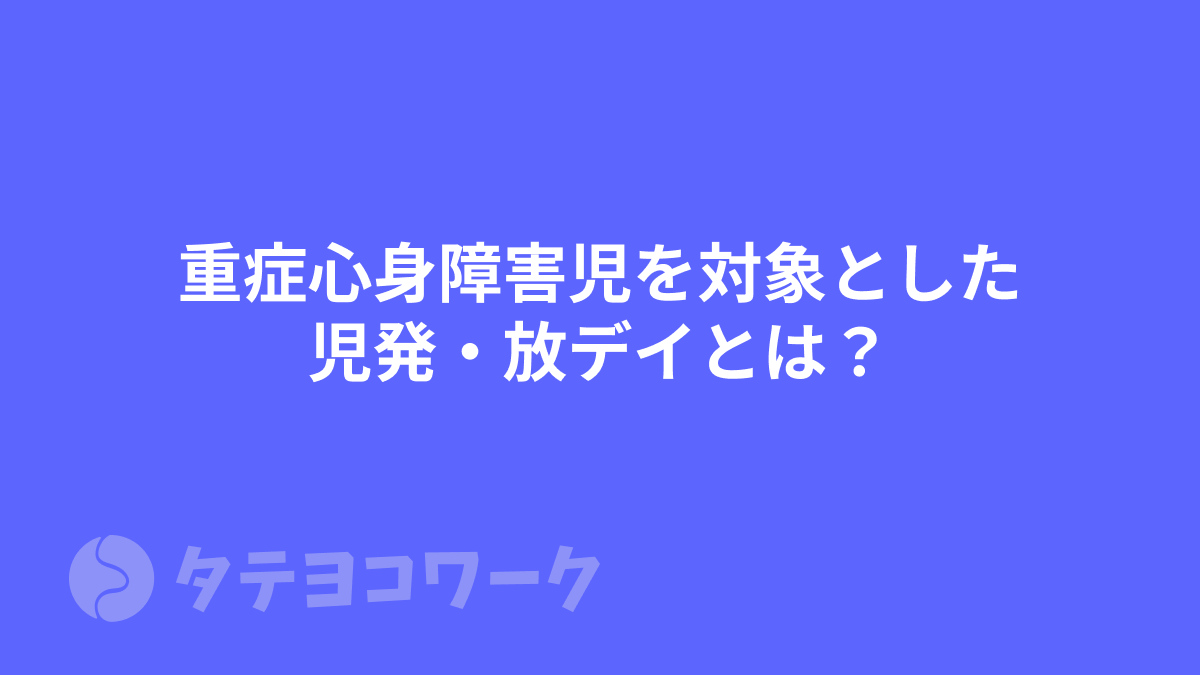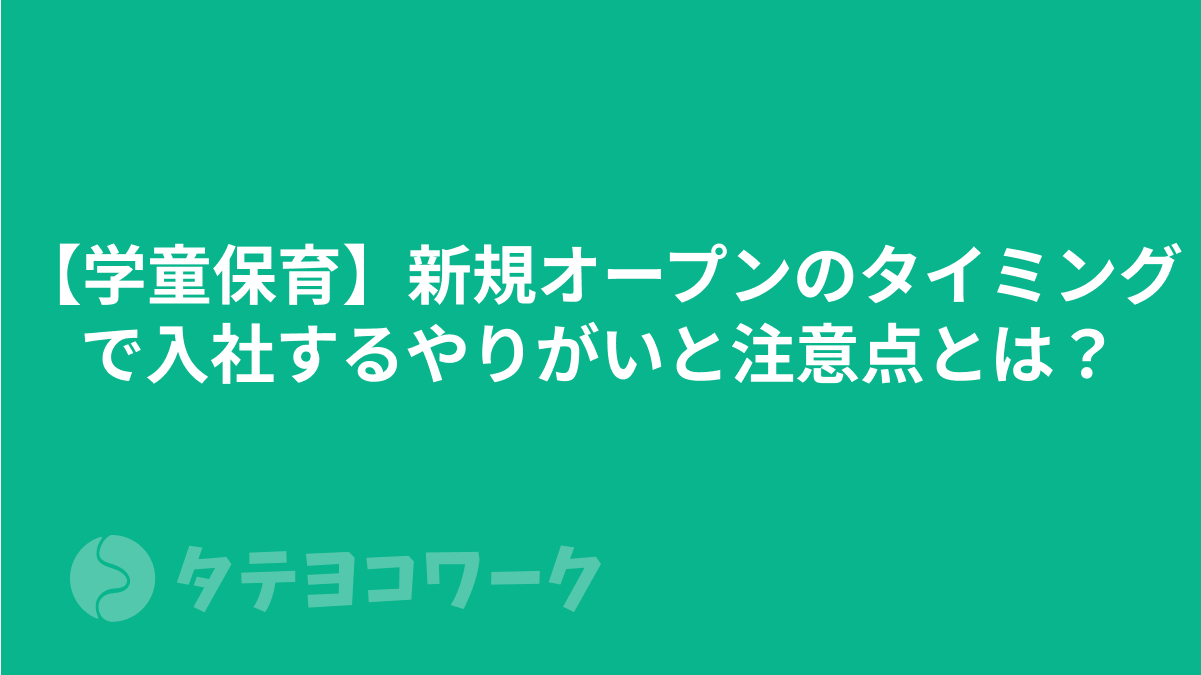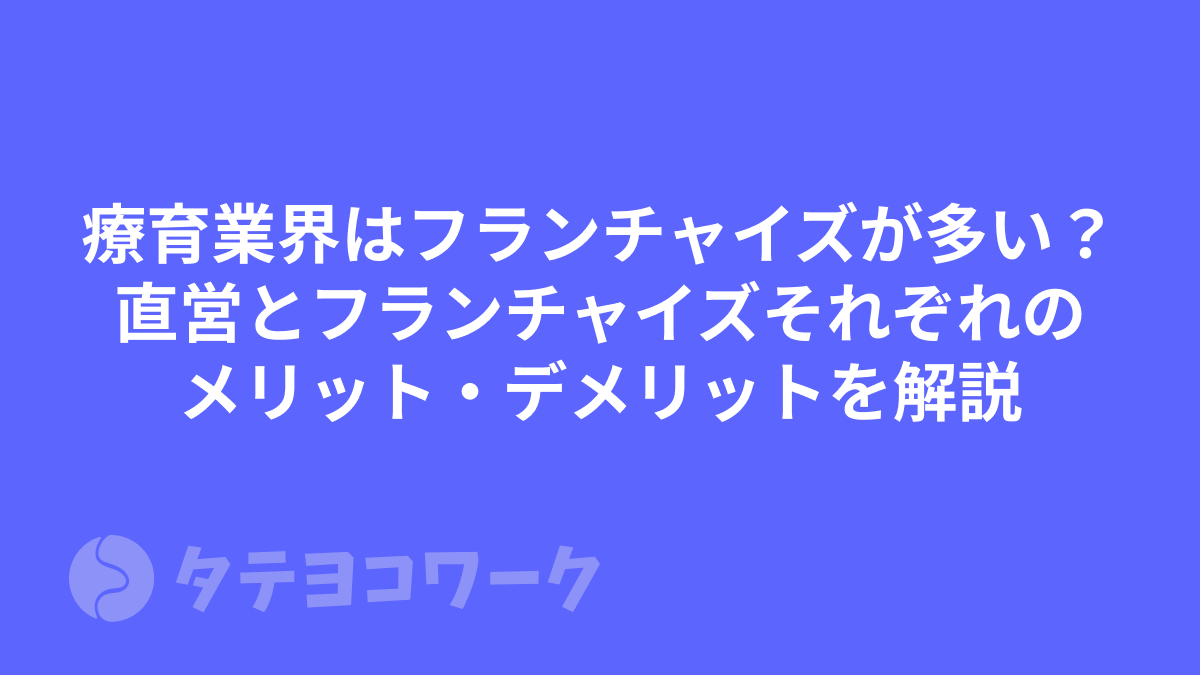タグで絞り込む
キーワードから探す
放課後児童支援員の資格取得方法をわかりやすく解説!
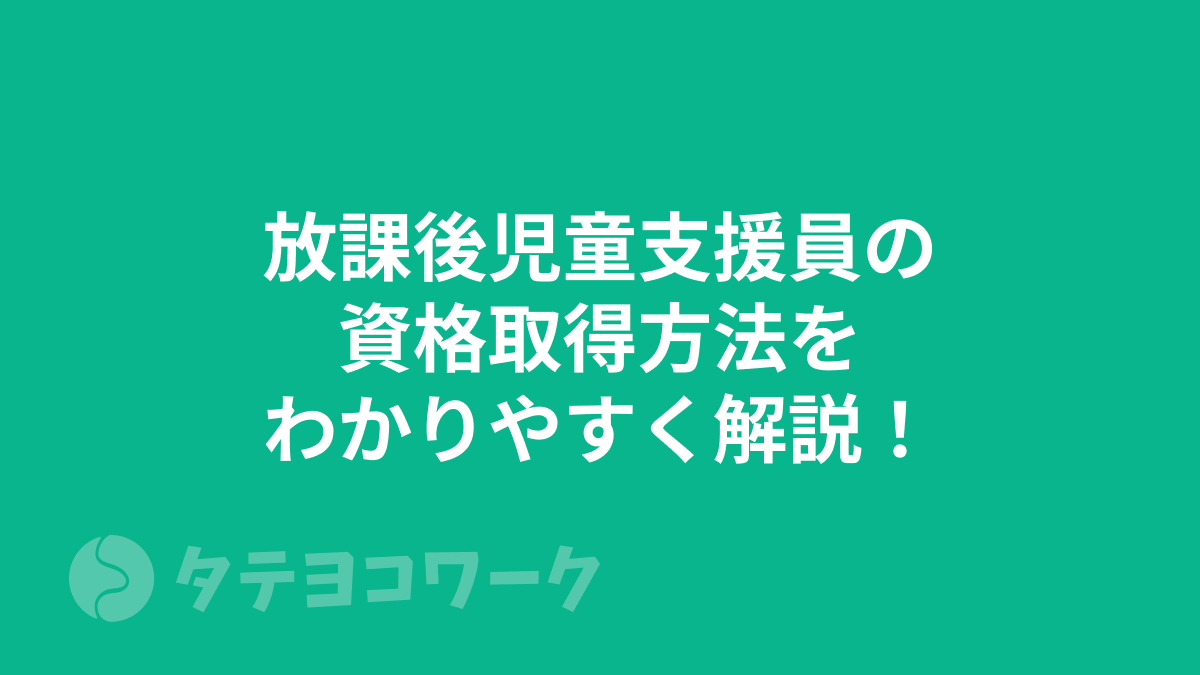
学童
資格
キャリアチェンジ
公立学童
専門性
民間学童
放課後児童支援員
未経験
近年共働き家庭が増加し、放課後児童クラブの重要性が高まる中で、放課後児童クラブで働く放課後児童支援員の仕事や、働く上で必要となる放課後児童支援員資格についても注目されています。
この記事では、放課後児童支援員の資格取得方法をわかりやすく解説していきます♪
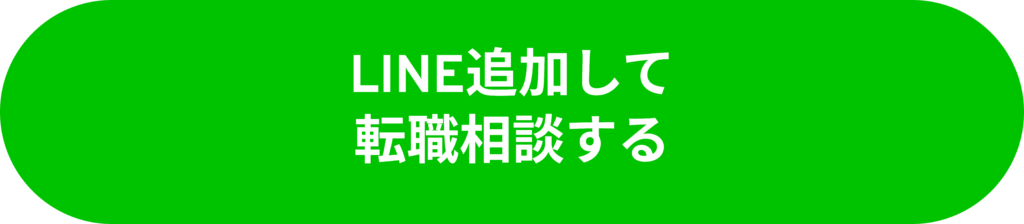
そもそも放課後児童支援員とは?
放課後児童支援員は、小学生が放課後の時間や学校の休業日に安心して過ごせる居場所を提供し、子どもたちの成長を見守る専門職です。具体的には、様々な遊びや異年齢交流・イベントなどを通して、主体性や社会性を育む支援をしています。
また、保護者や学校・地域との連携を図っていくことで、子育て環境の向上にも関わる非常にやりがいのある仕事です。
放課後児童支援員資格って何?
放課後児童支援員資格は、2015年に「子ども・子育て支援新制度」の一環として創設された比較的新しい資格です。
この放課後児童支援員資格は、放課後児童クラブで働くための「専門的な知識」と「技能」を持つことを証明するもので、各都道府県が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」を受講することで取得することができます。
厚生労働省の「放課後児童クラブ運営指針」には放課後児童支援員の配置基準として「概ね40人以下の児童に対して2人以上の支援員を配置すること」と記載されており、そのうち1人は放課後児童支援員の資格を保有している必要があると定められているのです。
放課後児童クラブで働くために必ずしも放課後児童支援員資格を取得する必要はありませんが、上記の理由から「放課後児童支援員の資格を保有していること」または「放課後児童支援員認定資格研修の受講要件を満たしていること」を応募要件とする求人や自治体・企業が非常に増えてきています。
そのため、常勤・社員として放課後児童クラブで勤務する場合は取得が必須になるといっても過言ではないほどに重要な資格なのです。
ちなみに、この資格が創設された背景には、いわゆる「小1の壁」の問題があります。
「小1の壁」とは保育園から小学校に進学する際に、放課後の子どもたちの居場所が不足し、共働き家庭が仕事と子育ての両立に苦労する状況のことを指しています。
この問題を解決するため、放課後児童クラブの拡充とともに、専門的な知識を持つ支援員の配置が義務化されました。
放課後児童支援員資格の導入により、学童保育の質の向上が図られているということですね。

資格取得のメリット
放課後児童支援員資格を取得することで、以下のようなメリットがあります。
①専門性を証明できる!
」放課後児童支援員資格を取得することで、学童保育分野における専門的な知識と技能を持っていることを証明できます。こどもたちと保護者に「安心安全な放課後の時間」を提供しながら、社会性や主体性などの「非認知能力」を伸ばすプロであることを示す資格となります。
②キャリアアップの可能性!
放課後児童支援員を取得することで、正社員雇用もしくは登用される可能性が高まります。アルバイト・パート勤務の場合であっても、放課後児童支援員資格を取得することで時給が上がることもありますので、勤務形態にかかわらず取得を目指すと良いでしょう。
放課後児童支援員認定資格研修を受講するために
放課後児童支援員の資格を取得するには、各都道府県が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」を修了し、証明書を交付してもらう必要があります。
この研修を受講するためには以下の実務経験が必要となりますので確認していきましょう。
◎研修の受講条件となる「実務経験」
・高卒以上で児童福祉事業に2年以上従事した経験
・高卒以上で放課後児童健全育成事業に類似する事業に2年以上従事し、市区町村長が適当と認めた場合
・学歴を問わず、放課後児童クラブで5年以上の実務経験がある場合
ただし、以下の資格や経歴を持っていれば、実務経験が無くても放課後児童支援員認定資格研修を受講することができます。
◎保有していれば実務経験が不要となる「資格・経歴」
・保育士資格
・社会福祉士資格
・教員免許(幼稚園、小学校、中学校、高校)
・大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学のいずれかを専攻して卒業している
放課後児童支援員認定資格研修の申し込み方は各自治体によって異なりますが、東京都では研修事務局へ「受講申込書」、「本人確認書類」、「受講資格確認書類」を提出することで申し込みが可能です。
研修の実施時期や詳細については、各自治体のHPなどをご覧ください。
放課後児童支援員認定資格研修の概要
研修は「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第10条第3項に基づいて実施され、学童保育の場でこどもたちと関わる上での基本的な考え方や心得、必要最低限の知識・技能を習得することを目的として実施されています。
研修受講料は原則として無料ですが、対面・集合形式(※)での受講の場合、交通費、昼食代などの実費は自己負担となります。
(※)2025年現在、東京都ではオンデマンド受講も可能です。
研修は、放課後児童クラブで必要な知識や技能を学ぶためのカリキュラムで構成されており、具体的には以下の6分野16科目が含まれます。
【①放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解(90分✕3科目=4.5時間)】
科目1 …放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容
科目2 …放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護
科目3 …子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ
【②子どもを理解するための基礎知識(90分✕4科目=6時間)】
科目4…子どもの発達理解
科目5…児童期(6歳~12歳)の生活と発達
科目6…障害のある子どもの理解
科目7…特に配慮を必要とする子どもの理解
【③放課後児童クラブにおける子どもの育成支援(90分✕3科目=4.5時間)】
科目8…放課後児童クラブに通う子どもの育成支援
科目9…子どもの遊びの理解と支援
科目10…障害のある子どもの育成支援
【④放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力(90分✕2科目=3時間)】
科目11…保護者との連携・協力と相談支援
科目12…学校・地域との連携
【⑤放課後児童クラブにおける安全・安心への対応(90分✕2科目=3時間)】
科目13…子どもの生活面における対応
科目14…安全対策・緊急時対応
【⑥放課後児童支援員として求められる役割・機能(90分✕2科目=3時間)】
科目15…放課後児童支援員の仕事内容
科目16…放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守
上記のとおり、90分×16科目の合計24時間の研修で、基礎から実践的な内容まで包括的に学んでいきます。なお、既に保育士や教員免許、社会福祉士の資格を有している場合は、研修科目の一部が免除となりますよ(免除される場合でも、積極的な受講が推奨されています)。
まとめ
放課後児童支援員は、子どもたちの成長を間近で見守り、社会に貢献するやりがいを感じられる仕事です。興味のある方は、ぜひ放課後児童支援員資格の取得を検討してみてはいかがでしょうか?
タテヨコワークでは、学童の求人を数多く取り扱っており、未経験から転職を目指す場合でもエージェントが丁寧にサポートします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
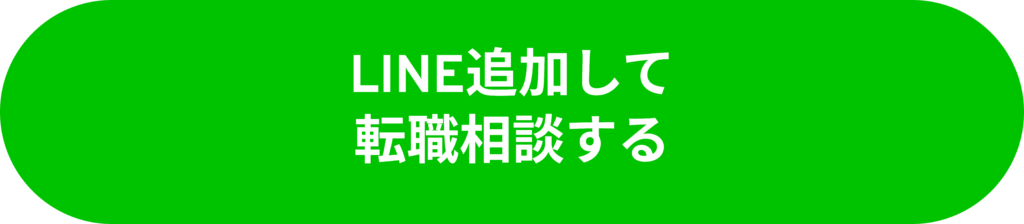
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。