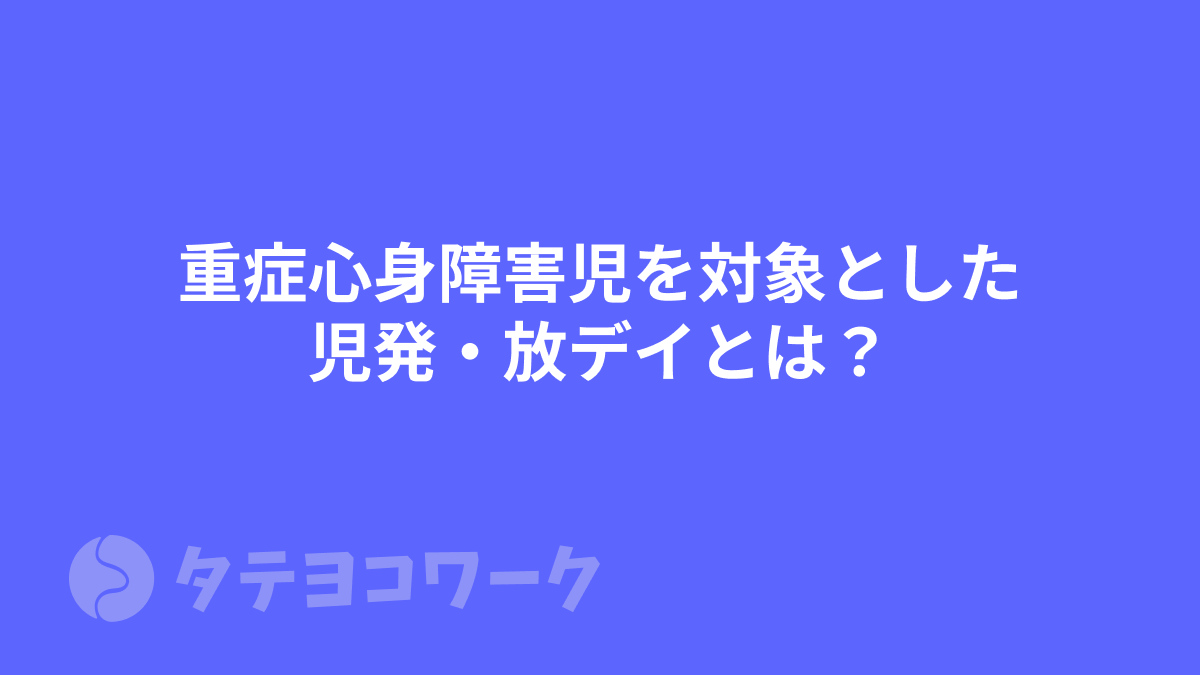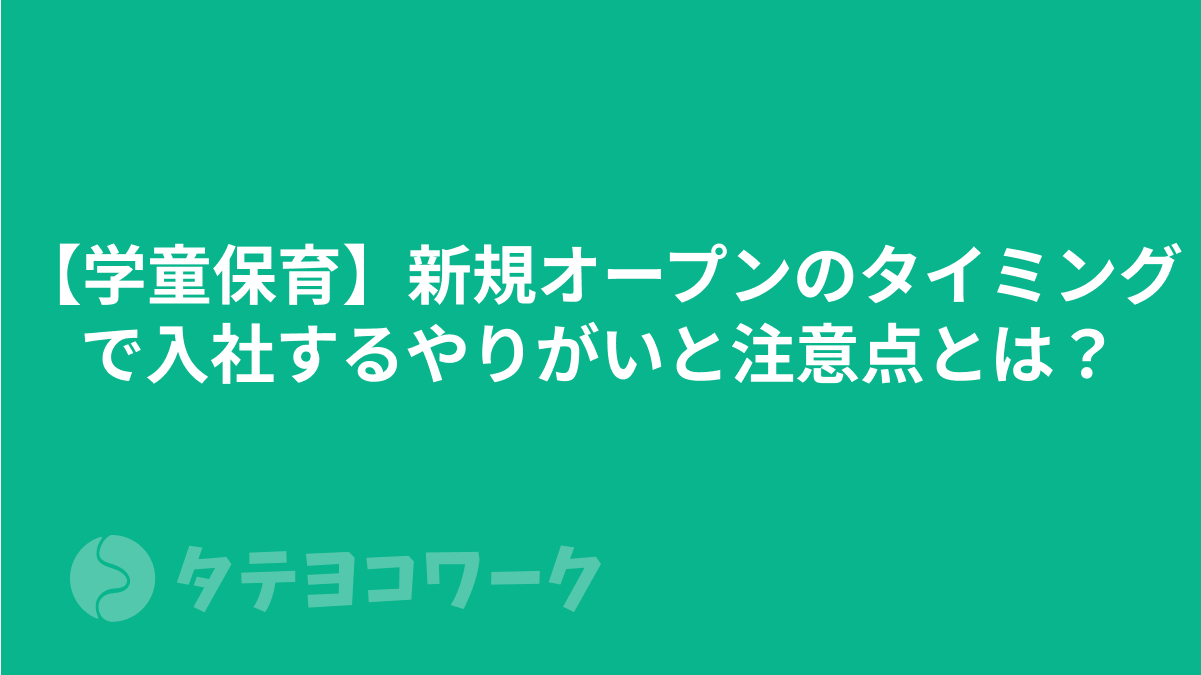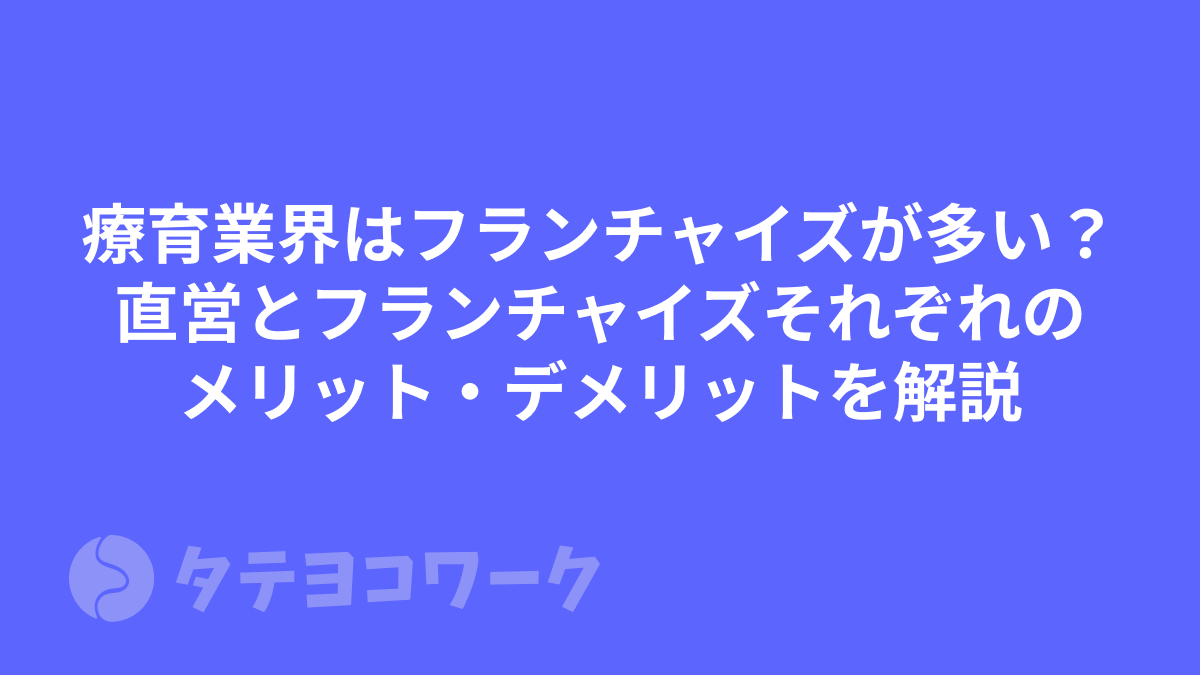タグで絞り込む
キーワードから探す
民間学童と公設学童、働くならどっち?それぞれの特徴も解説!
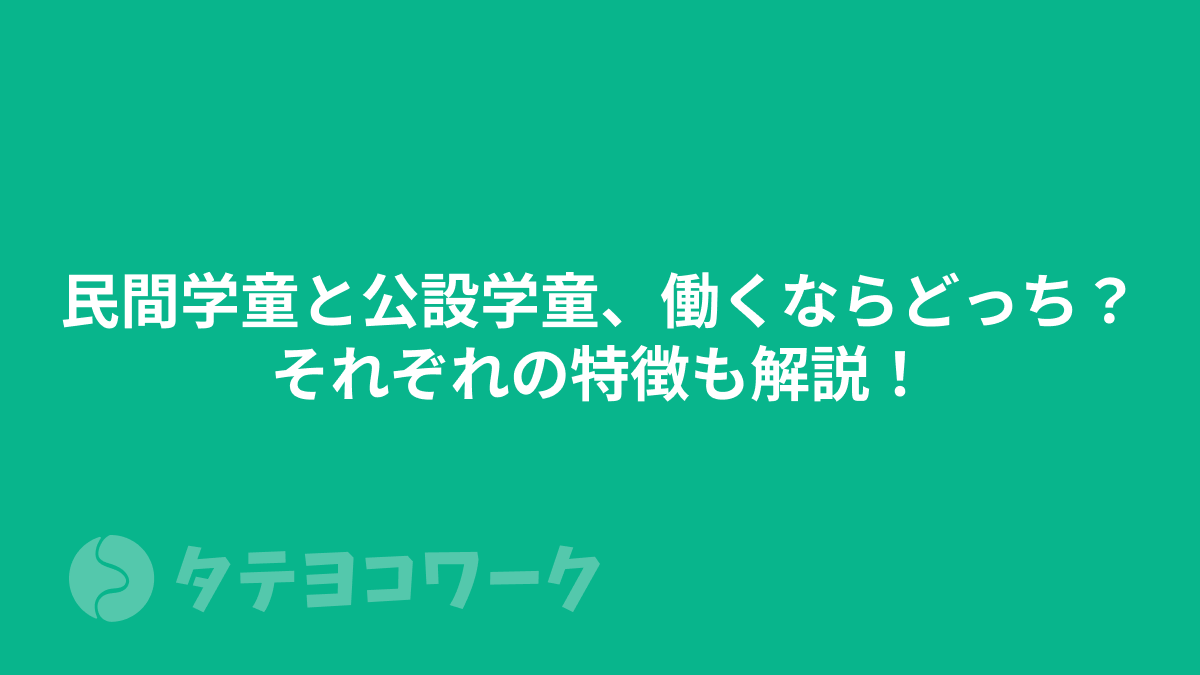
学童
キャリア
キャリアチェンジ
公立学童
民間学童
放課後児童支援員
転職
近年、共働き世帯の増加に比例して学童保育所を利用する子どもたちが増えてきている中で、子どもたちの放課後の時間を安全で充実したものにするために、多種多様な学童保育所が全国的に増えてきています。
今後どのような学童保育所で働きたいかを考える際には、まず「公設公営学童保育所」と「公設民営学童保育所」そして「民間学童保育所」の違いを理解しておくことがとても重要です。
この記事では、それぞれの学童の特徴を掘り下げることでそれぞれの魅力や違いを整理し、自分に合った学童クラブで働くことが出来るようなヒントをお届けいたします!
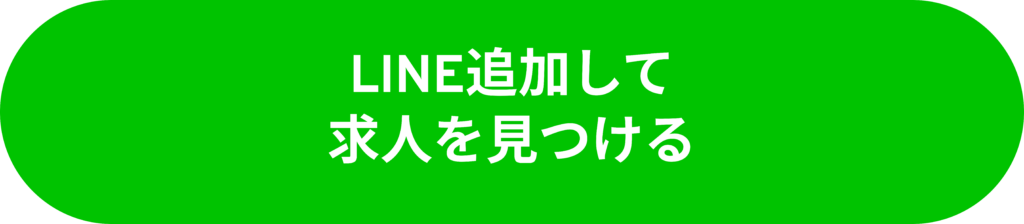
それぞれの学童保育所の特徴
まずは「公設公営学童保育所」と「公設公営学童保育所」、「民間学童保育所」のそれぞれにどのような特徴があるのかを見ていきましょう。
◎公設公営学童保育所の特徴
【運営主体について】
地方自治体が直接運営をしています。そのため公共性が非常に高く、地域住民にとって利用しやすい施設といえます。また比較的低料金で利用できることが多く、家庭の経済的負担を軽減する働きが強いという一面もあります。
【施設環境について】
学校の空き教室や児童館など、地域の公共施設を活用している場合が多いです。
【職員体制について】
公務員や自治体が雇用する職員(会計年度職員など)が運営に携わることが多く、ガイドラインに沿った適切な人数配置を守って運営をするため、比較的安定した管理体制が期待できます。
【活動内容について】
宿題のサポートや自由遊びを中心に、子どもたちが安心して過ごせる環境を提供します。特別なプログラムを提供するというよりも、安心で安全な日常的な居場所としての役割が強い場合が多いです。
同じ学校に通っていたり同じ地域に住んでいたりする子どもたちが集まることがほとんどであるため、友達関係の継続や地域コミュニティの形成に大きく影響し、「第二の家」のようなアットホームな施設であることが多いです。
◎公設民営学童保育所の特徴
【運営主体】
地方自治体が設置した学童保育所の運営を、指定管理者制度(※)などを活用して民間企業や団体に委託しています。そのため、各自治体の基準を満たしつつ、民間のノウハウを活用した効果的な運営が行われています。
(※)指定管理者制度とは?
指定管理者制度は、地方自治体が設置した「公の施設」の管理運営を、民間企業やNPOなどの法人や団体に委託する仕組みです。この制度は、2003年の地方自治法改正によって導入されました。民間企業のノウハウを活用した住民サービスの向上や管理運営の効率化、コスト削減などを実現することができるといわれています。
【利用料金】
多くの場合、公設公営学童所の利用料金と統一されるため、比較的低料金で利用できる場合が多いです。ただし、自治体や運営団体によって異なる場合があります。
【施設環境】
公設公営学童保育所と同様に、学校や児童館などの公共施設が活用されることが多いです。
【職員体制】
地方自治体が雇用する職員ではなく、民間の運営団体が雇用する職員が中心となります。自治体が定める基準に基づいた人員配置が行われるため、一定の質が保証されますが、実際は各運営団体によるところが大きいようです。
【活動内容】
公設公営学童保育所と同様の基本的な宿題サポートや自由遊びに加え、運営団体の特色を活かしたプログラム(スポーツやアート活動など)が提供されることがあります。
公設民営学童保育所は、自治体の安心感・公共性と民間特有のオリジナリティや柔軟性を兼ね備えた施設といえます。

◎民間学童保育所の特徴
【運営主体】
民間学童保育所は、民間企業や団体が独自に設置をして運営する民設民営学童保育所です。最近は塾やスポーツクラブなどが運営する学童保育所も増えてきています。公設の学童保育所とは異なり、自治体の基準ではなく、運営者の理念や目標に基づいた運営が行われます。そのため非常に自由度が高く、より多様なサービスやプログラムを提供することが可能です。
【利用料金】
民間の学童保育所では、利用料金は運営団体が設定します。そのため、公設学童保育所よりも高めの料金設定になる場合がありますが、料金相応の充実したサービスを期待することができます。
【施設環境】
独自の施設や立地条件が選ばれることが多く、専用スペースや設備が充実している場合があります。たとえばサッカーや体操などができる広いスペースや、大きな遊具や芝生が設置された遊び場など、運営者の特色が反映された環境が整えられています。
【職員体制】
民間の運営団体が直接雇用する職員が中心となり、運営者が定める基準や理念に基づいて人員配置が行われます。公設の学童保育所に比べると職員数が少ないこともありますが、スポーツ指導者や学習指導講師など、特定の分野に特化した専門職員が配置される場合もあります。
【活動内容】
宿題サポートや自由遊びはもちろん、民間学童保育所ならではの特色あるプログラムが用意されていることが多いです。外国語学習や自然に触れる体験、アート活動や料理プログラムなど多種多様なサービスが充実していて、個々の子どもの興味や特性に合わせた柔軟な対応が期待できます。
民間学童保育所は、こどもたちや保護者のニーズに合った選択肢を用意しつつ、専門的な教育や体験、快適な環境を提供できる施設として注目されています。
それぞれの学童保育所のメリットとデメリット
各学童保育所の特徴を確認したところで、それぞれの学童保育所で働くメリットやデメリットも見比べていきたいと思います。なお、以下に挙げるメリットやデメリットはあくまで各運営形態の全体的な特徴となりますので、各自治体や運営主体によって詳細は異なります。
⚪︎公設公営学童保育所で働くメリット
①安定した労働環境
公設公営学童保育所で働くことの大きなメリットの一つとして、安定した雇用・労働環境が挙げられます。
地方自治体が運営しているため、労働条件が明確で、福利厚生や労働時間の管理がしっかりしていることが多いです。特に正規職員として雇用される場合は、社会保険や年金制度なども整備され、長期的な視点でのキャリア形成が可能です。また地域社会との結びつきが強く、地元の子どもたちの成長をさまざまな機関と協力しながら支えていけるというやりがいもあります。
②自己研鑽の機会がある
公設公営学童保育所で働くと、自治体の基準に基づいて実施される様々な研修やスキルアップの機会が提供されることが多く、自己成長が期待できる点も大きな魅力です。職場には「子どもたちの健やかな成長を支援する」や「安心できる放課後の居場所をつくる」という同じ目標を持って共に学ぶスタッフがいることも多いため、仲間と一緒にこどもたちのために働くという充実感を得られる点も大きな利点といえるでしょう。
●公設公営学童保育所で働くデメリット
①柔軟さに欠ける
公設公営学童保育所で働くことの課題やデメリットとしては、自治体の予算や方針に影響を受けるため、施設やプログラムに制約が生じることが挙げられます。自治体が定めた基準に従わなければならないため、施設のルール決めやイベントの企画時、利用者対応などの柔軟性が求められる場面で対応が難しく感じる可能性があります。
②利用人数の多さ
学童保育所の大規模化も働くスタッフにとっては大きな課題の一つでしょう。近年は全入制(入所を希望した全家庭の利用を認める制度)をとる自治体もあり、大幅に定員を超えた運営をしている施設も多いです。利用人数が多い施設では、子ども一人ひとりに十分な時間を割くことが難しくなり、結果的にスタッフの負担が増えてしまいます。
③施設の老朽化や狭隘環境
多くの公設公営学童保育所は学校の空き教室や敷地内のスペース、児童館など公共の施設を使用している場合が多く、老朽化が進んでいたり狭隘環境が深刻化していたりする場合があります。古くて狭い施設や、綺麗な遊具や家具が揃っていない保育環境が気になる…という方もいるかもしれません。
⚪︎公設民営学童保育所で働くメリット
①安定性と柔軟性のバランスが良い
公設民営学童保育所は、自治体の方針や基準をもとにした運営をするため、安全で信頼性が高く、スタッフも安心して働ける労働環境が整備されている場合が多いです。加えて、民間運営ならではの多様なプログラムやサービスの提供も実施可能です。各運営団体の専門性やノウハウを活かし、子どもたちの多様なニーズや興味に応える活動を実施できることに面白さを感じるスタッフも多いのではないでしょうか。
②自己研鑽の機会がある
公設民営学童保育所で働くと、公設公営学童保育所と同様の自治体主催研修やスキルアップの機会が提供される上に、運営主体である民間団体独自の研修プログラムを受けることも可能です。そのため、自己研鑽しやすく得られる学びの機会が多い働き方であるといえます。
●公設民営学童保育所で働くデメリット
①自治体の方針に縛られることがある
公設民営学童保育所は公設公営学童保育所と同様に、基本的には自治体が定めた基準に従って運営する必要があるため、やりたいことが迅速かつ柔軟に出来ない可能性があります。
民間ならではのノウハウやプログラムを提供することが出来るのが大きなメリットではありますが、あくまで公設の学童保育所であるためイベント企画報告書や事業計画は自治体に提出する必要があり、場合によっては修正が入ったりストップがかかってしまったりする場合があります。
特に同じ自治体の中に公設公営学童保育所が存在する場合は、同様のプログラムを実施することや同じペースでの変革を求められることもあるため、思うように民間らしい運営が出来ずもどかしい…という現場スタッフの声もあるようです。
②利用人数の多さ
③施設の老朽化や狭隘環境
といった、上述した公設公営学童と同様の課題もあります。
⚪︎民間学童保育所で働くメリット
①独自性や専門性が活かせる
民間学童保育所は運営やプログラムの自由度が高いため、スタッフが自分の得意分野や個性を活かした指導ができる点が魅力です。例えば、アートが得意なスタッフは絵画教室を担当したり、スポーツが好きなスタッフは運動プログラムを企画したりできます。このように、自身のスキルや興味を活かせる環境で働けるため、日々の仕事にやりがいを感じられます。また、子どもたちとの直接的な交流を通じて、成長を間近で見守る喜びも大きなモチベーションとなります。
②充実した保育環境で人数のこどもたちと密に関わることが出来る
民間学童保育所は基本的に定員を設けており少人数制であることが多いため、一人ひとりの子どもと深く関わる機会が豊富です。また新しくて綺麗な施設であったり、様々な遊具や設備に囲まれた充実した環境であったりすることも多いです。そのため心に余裕を持ちながら子どもたちの個性や成長過程を細かく観察し、それに合わせたサポートができるという喜びがあります。特に子どもが何か新しいことに挑戦をしたり、成功した瞬間を共有したりできるのは大きなやりがいといえるでしょう。
●民間学童保育所で働くデメリット
①不安定な雇用条件
民間学童保育所は運営主体が企業や個人であるため、経済状況や運営方針によって雇用条件が不安定になる場合があります。たとえば、経営がうまくいかない場合に人員削減が行われたり、給与や福利厚生が公設学童に比べて少なかったりする場合があります。
②業務内容や人手不足による負担
民間学童保育所では、スタッフが保育業務に加え、車やバスを使用したこどもたちの送迎、イベントの企画運営、保護者対応、施設管理、利用者募集の営業活動、など幅広い業務を行う必要がある場合があります。
また公設の学童保育所と異なり、職員配置基準が適切に定められていなかったりスタッフの採用がうまくいかなかったりといった要因で人手不足に陥る可能性もあります。
そういった環境で働くスタッフは負担が大きくなる場合もありますので、注意が必要です。
まとめ
このように公設公営学童保育所、公設民営学童保育所、民間学童保育所にはそれぞれの特徴やメリット・デメリットがあることが分かりました。
結論として、「どちらで働くべきか?」の答えはその人の価値観や目指す方向性によります。
民間学童は創造性や柔軟性を重視する職場で、多様なプログラムを提供できる魅力があります。
一方、公設学童は安定性や地域貢献を重視する職場としての特長があります。
どちらを選ぶにしても、まずは自分の理想像や強みを明確にして、それぞれの特色を考慮しながら決断することが重要です。
タテヨコワークでは、学童の求人を数多く取り扱っており、未経験から転職を目指す場合でもエージェントが丁寧にサポートします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
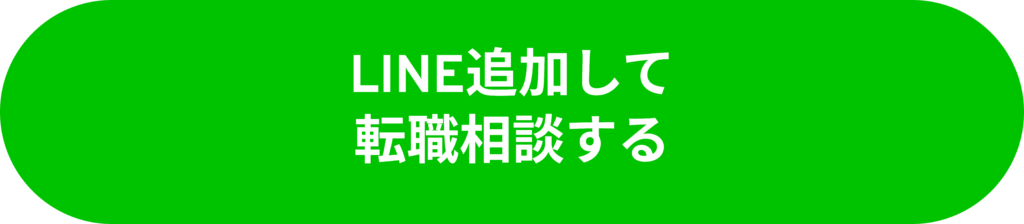
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。