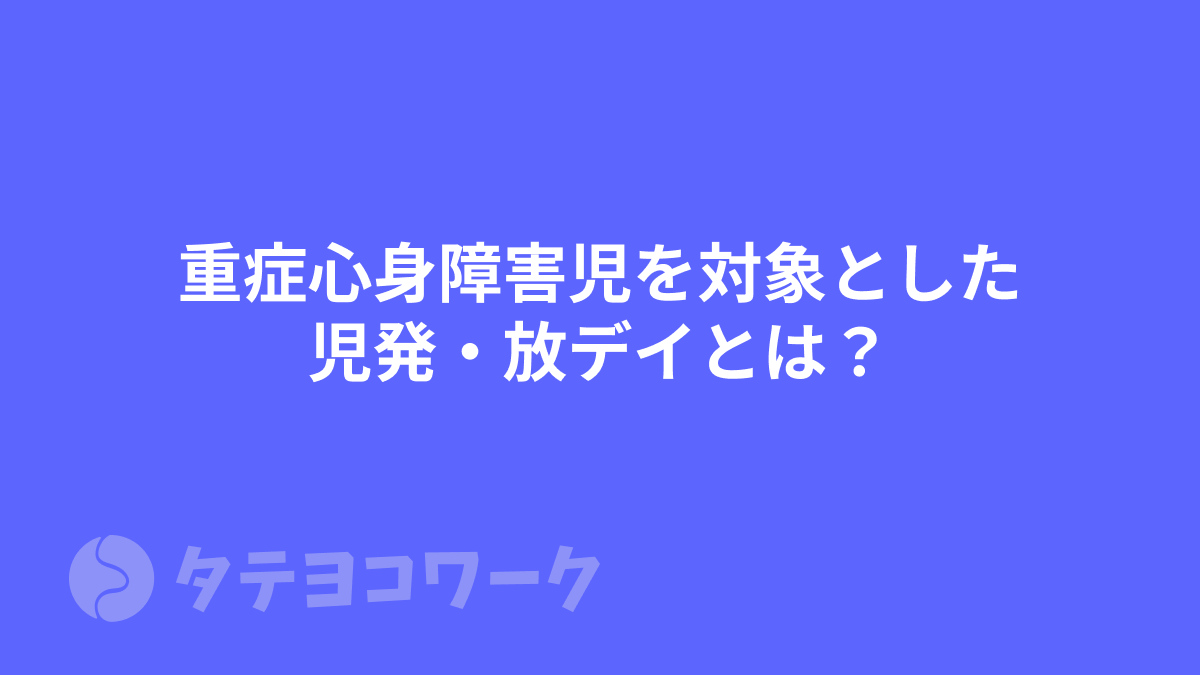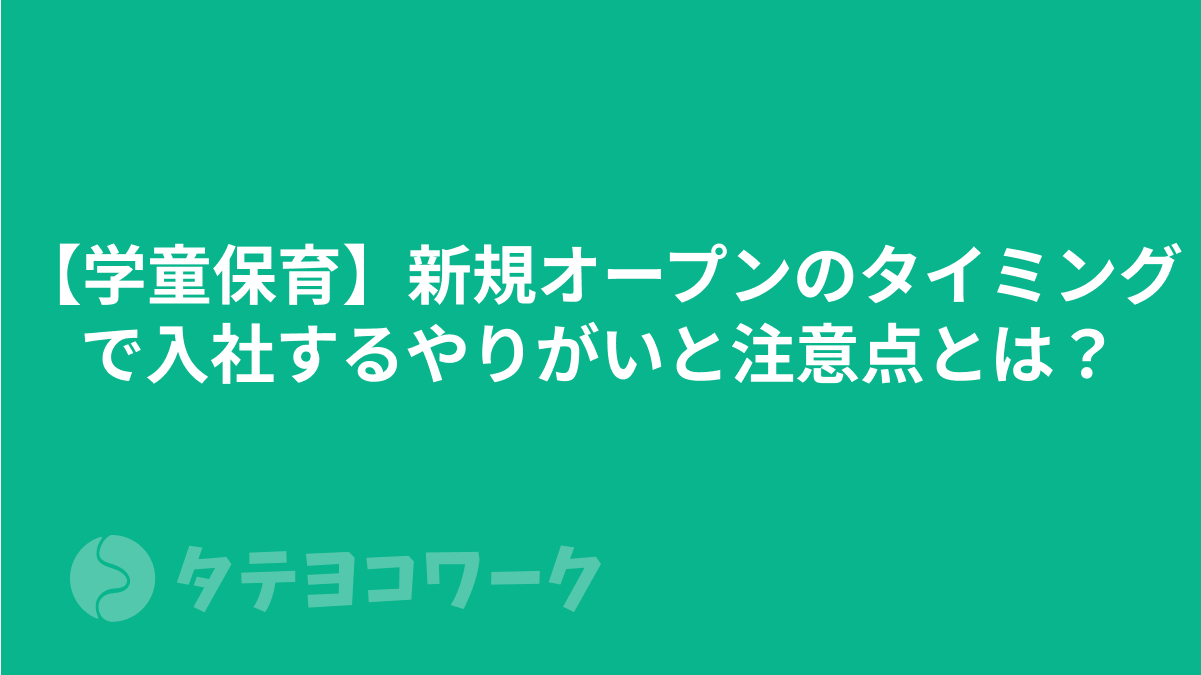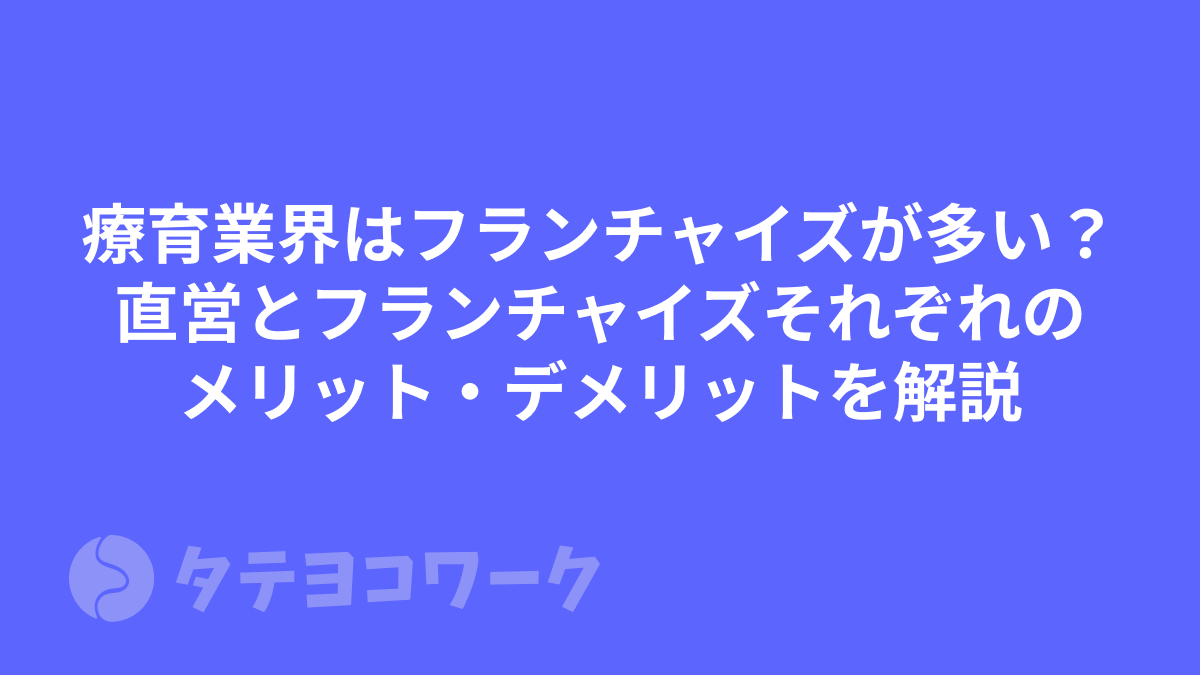タグで絞り込む
キーワードから探す
学童保育で使える!100均グッズでできる工作ネタ5選
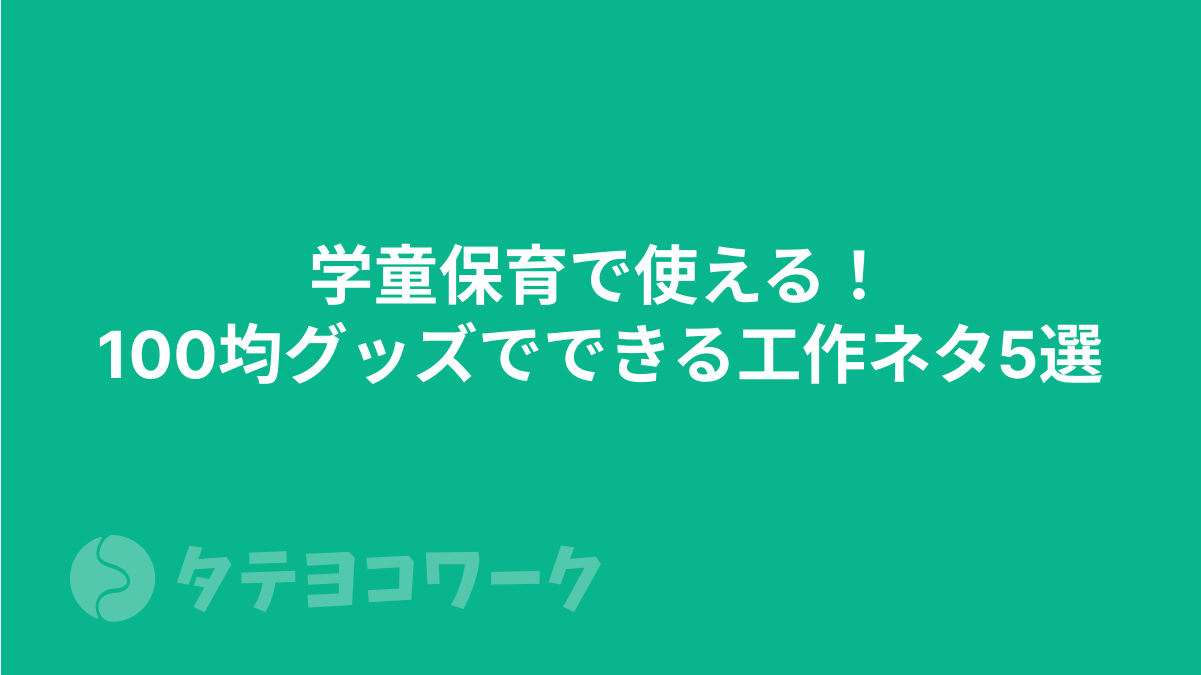
学童
ノウハウ
公立学童
民間学童
あそび
実践事例
学童保育の現場では、こどもたちが放課後の時間を安全かつ充実して過ごせるように、さまざまな活動が行われています。その中でもこどもたちに人気が高く、季節や行事に合わせて取り入れやすい活動が「工作」です。工作は単に楽しい遊びというわけではなく、こどもたちの手先の器用さや創造力、集中力など様々なスキルを養うことが期待できる素晴らしい活動です。
とはいえ学童保育の現場では、工作活動に充てられる予算や時間が限られているのが現実…。何十人ものこどもたち全員に必要な材料を行き渡らせようとすると、材料費だけでも相当な額になってしまうことも珍しくありません。
そんなとき、学童スタッフの強い味方となるのが、100円ショップ(以後、100均と表記)!
今回は、学童保育で実践しやすく、こどもたちが楽しみながら作れる「100均グッズでできる工作ネタ」を5つご紹介します。すべて低コストかつ簡単に揃えられる材料で、低学年から高学年まで幅広く楽しめる内容になっていますので、是非最後までご覧ください。
◎100均グッズの魅力とは?
「100円で買えるものだけで、面白い工作活動の準備ができるのかな?」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、100均を決して侮る無かれ! 100均で揃う工作材料には、こんな魅力があるのです。
●お手頃価格であること!
…一部例外商品はあるものの、ほとんどの商品が100円(税込110円)で工作グッズを購入できるため、多くの材料を用意しても金銭的な負担が少ないことがやはり大きな魅力です。
●入手がしやすいこと!
…全国どこにでも多くの店舗があり、品揃えが安定しているため、必要な時に必要な量を入手することが容易であるというメリットもあります。定期的に新作商品が入荷されますし、ハロウィンやクリスマスなどの季節限定商品や多彩な素材が揃うことも魅力です。
上記のとおり、安くて入手しやすい100均の工作材料は「失敗してもやり直しやすい」という点も長所です。「失敗したらもったいない」という気持ちは大人にとってもこどもにとっても大きな負担…。でも、100均素材ならコスト的な負担が少なく、思い切って作り直すことができます。これは、学童保育の工作活動で非常に大切なポイントです。
【工作ネタ①】 紙を使った工作「回る!カラフル風車」
★材料
• カラフルな画用紙または両面折り紙
• 太めのストロー(紙製でも可)
• 画びょうまたは安全ピン
• ビーズ(小さめ)
• セロハンテープ
• ハサミ
• 定規
• 鉛筆
⭐︎作り方
1. 画用紙を正方形にカットします。15cm×15cm程度が回しやすいためオススメです!
2. 正方形に切った紙に、定規で対角線をひいて中心点を決め、鉛筆で印をつけます。
3. 対角線に沿ってハサミで切れ込みを入れますが、中心点までは切らず、2cm手前で止めます。
4. 四隅のうち、同じ向きの角(例:すべて右側の角)を中央に集めます。
5. 集めた角と中央を画びょうで留めます。画びょうを通す前に、紙と紙の間にビーズを1粒挟むと、風車がよりスムーズに回ります。
6. 画びょうの針をストローの先端に刺し、裏面からセロハンテープで補強します。
7. 完成後は、外に出て風に当てたり口で息を吹きかけたりして回して遊びます。
《安全面の配慮事項》
• 金属製の画びょうは危険なので、先が短いプラスチック製の安全画びょうを使用するのがおすすめです。また、画鋲を取り付ける作業は大人がやるなど、十分扱いには注意をしてください。
• ハサミ使用時は低学年の子には必ずサポートをつけましょう。
《アレンジ例》
• 透明セロファンを使うと光を通す風車になり、窓辺の飾りにもなります。
• 季節に合わせて柄を変える(春は花柄、夏は海の生き物や貝柄、秋は紅葉柄、冬は雪の結晶柄など)と可愛いです。
《学童保育での導入ポイント》
• 事前に紙を正方形にカットしておくと作業がスムーズになります。
• 高学年の子や工作が得意な子には、上級編として風車の羽を4枚から6枚に増やすなどの応用を提案できます。
• 制作後は屋外や扇風機の前などで風を感じながら遊ぶ時間を設けると満足度が高まります。
【 工作ネタ② 粘土を使った工作「オリジナルマグネット」】
★材料
• 粘土
• マグネットシート(裏面シールタイプ)
• アクリル絵の具
• 絵具筆
• 水入れ
• 作業マット(下敷きや牛乳パックを開いたものでも可)
• ニス(つや出し用、なくても可)
⭐︎作り方
1. 粘土を袋から出し、よくこねて柔らかくします。
2. 好きな食べ物や動物などの形に粘土を形成します。パーツは粘土同士を軽く押しつけて、水を少量つけるとくっつきやすくなります。
4. 裏面にマグネットシートを貼ります。
5. 半日〜1日程度乾燥させ、完全に固まったらアクリル絵の具で色を塗ります。
6. 絵の具が乾いたら、ニスを塗ってツヤを出します。
《安全面の配慮》
• 小さなパーツは誤飲の危険があるため、必要に応じて大きめの作品を推奨しましょう。
• アクリル絵の具は服につくと落ちにくいので、エプロンや汚れても良い服を着用してもらえるよう保護者にも事前連絡をしておきましょう。
• ニス使用時は換気を行ってください。
《アレンジ例》
• 名前や好きな言葉を入れてオリジナルネームマグネットにしたり、母の日や父の日のプレゼントなどにしても良いでしょう。
• カラフルなマーブル模様を粘土の段階で作ると、塗装不要でも可愛いです。
《学童保育での導入ポイント》
• 乾燥が必要なため、2日間に分けて実施するとスムーズです。夏休みや冬休みの長期休暇期間に実施するのも良いでしょう。
• 学年などのグループに分けて色塗りなどを時間差で行うと、作業場所の混雑・タイムロスを防げます。
【工作ネタ③ 風船を使った工作「ぷかぷか水ヨーヨー」】
★材料
• 水風船
• ヨーヨー用の糸と輪ゴム
• 水を入れる桶やタライ
• ラメやビーズ(お好み)
⭐︎作り方
1. 水風船に水を3分の1程度入れ、残りは空気を入れて膨らませます。
2. 口をしっかり結び、輪ゴムを取り付けます。
3. 糸やゴム紐を輪ゴムに通し、持ち手を作ります。
4. タライや幼児用プールなどに水を張り、浮かべて遊びます。
《安全面の配慮》
• 水を使うため、屋外や水はけの良い場所で行うのがオススメです。
• 割れた風船の破片は誤飲や転倒などの事故を防ぐため、すぐに回収しましょう。
• 水風船を人に投げないよう声をかけましょう(水遊びとして相手に向かって投げる場合は、全体の合意を取る)。
《アレンジ例》
• 水風船にマジックペンで絵付けをするとオリジナリティが溢れる作品になり可愛いです。
• ヨーヨー釣りにしたり、夏祭りイベントと組み合わせたりすると楽しさが倍増します。
【工作ネタ④ ストローを使った工作「ストロー迷路」】
★材料
• 太めのストロー
• 厚紙(A4程度)
• ビー玉
• 両面テープまたは接着剤
• 定規・鉛筆
⭐︎作り方
1. 厚紙を土台にし、迷路の設計図を鉛筆で描きます。
2. ストローを迷路の長さに合わせて切ります。
3. 切ったストローを両面テープで固定します(両面テープの使用が難しければ片面セロハンテープでも可)。
4. ビー玉を転がしてゴールを目指します。
《安全面の配慮》
• ビー玉の誤飲防止のため、低学年には大きめの玉を使用したり注意喚起をしたりしましょう。
• 接着剤使用時は換気を心がけましょう。
《学童保育での導入ポイント》
• 自分が作った迷路で遊ぶだけでなく、他の人に遊んでもらったり他の人が作った迷路で遊んだりできる時間を設けると盛り上がります。
【工作ネタ⑤ ペットボトルを使った工作「ペットボトルけん玉」】
★材料
• 500mlペットボトル
• 紐(50cm程度)
• ピンポン玉
• ビニールテープ
• 千枚通し(穴あけ用)
⭐︎作り方
1. ペットボトルを半分に切ります。飲み口部がついている上半分を使用します。
2. ピンポン玉に千枚通しで穴を開け、紐を通して結びます。
3. 紐の反対側をペットボトルの口に結びつけます。
4. ビニールテープで補強したら、完成!
《安全面の配慮》
• 1と2の工程(カッターや千枚通しを使用する部分)はこどもの状況に応じてスタッフが担当しても良いでしょう。
• 紐の長さは子どもの腕の長さに合わせて調整してください。
《アレンジ例》
• ペットボトルに装飾をしたり、ピンポン玉に絵付けをしたりしても楽しいです。
• ペットボトルけん玉の成功回数を競うトーナメント戦などを企画すると盛り上がります。
◎学童保育での工作活動を成功させるポイントは?
学童保育での工作活動は、ただ「作る」だけでなく、安全面・時間配分・達成感をバランスよく組み込むことが大切です。準備から片付けまでを円滑に進めるため、以下のポイントを押さえておくと失敗が減り、こどもたちの満足度も高まります。
① 事前準備は入念すぎるほど入念に!
100均への買い出しは1週間前までに済ませ、必ずスタッフで試作をするようにしましょう。実際に作ってみて、こどもが手間取りそうな工程などを確認して置けるとスムーズです。
また、紙や紐のカット、パーツの仕分けなどは可能な限り事前に行うと当日の混乱を防げます。特に人数が多い学童では、材料の配布だけで5分以上かかってしまうことがあるため、個別キット化(ジッパー袋や紙袋にまとめる)が効果的です。
ハサミやカッターを使う工程は、あらかじめスタッフが切って用意をしておくと安全かつ時短になります。
② 作業時間は「集中できる時間+少しの余裕」を考慮!
こどもたちは、年齢や発達度によって集中できる時間が異なります。目安は低学年で15〜20分、高学年で30分程度でしょうか。長引くと飽きてしまい、短すぎると満足のいかない仕上がりになってしまいますので、試作をしながらゴールまでの工程を逆算して時間配分を決めましょう。早く完成した子ども向けに「おまけ作業」(色塗りや追加デコレーション)を用意しておくと、待ち時間の暇つぶしになります。
③説明は「短く・見せながら」!
工作活動のはじめに、必ず全員で道具の使い方やルールを確認しましょう。「ハサミは歩きながら使わない」、「接着剤は少量ずつ」など丁寧に説明をすることが大切です。ただし、言葉で長時間説明しても「早く工作したいな…」とウズウズしているこどもたちの耳をすり抜けてしまいますので、イラストや写真付きの説明書を事前につくっておけると効果的です。
工作の手順も口頭説明だけでなく必ず手元で作りながら説明しましょう。ホワイトボードや模造紙に全体の手順を書き出しておくと、作業中に迷った子どもが自分で確認できますのでオススメです。また、1回で全工程を説明せず、「まずはここまで作ってみよう」と工程を区切って伝えると混乱を防げます。
④ こどもの自主性を尊重!
指示・見本通りに作るだけでなく、「色は自由に」や「形は好きなようにアレンジOK」と選択の余地を残すことで、創造力や作品への愛着がアップします。決して工作に正解はなく、完成形が見本と異なっていても問題ないという空気をつくることが大切です。どのような結果であれ「それも素敵だね」と肯定的に受け止めることで、次への挑戦意欲や工作への興味関心が高まります。
⑤片付けまでを工作活動の一部に!
「作って終わり」ではなく、片付けまでを活動時間に含めてみましょう。「面倒くさい」と思われがちな片付けタイムを「面白い」と感じられるゲーム感覚にする(タイマーで時間を計る、片付け名人を決める)と乗り気になるかもしれません。画鋲やハサミなどの危険な道具を使った後は、必ず机や床、育成室の安全もチェックして、その後の事故怪我を防ぎましょう。
⑥振り返りと展示で達成感アップ!
完成後は全員で作品を並べて「作品発表タイム」を設けてみても良いでしょう。作品を学童内に飾ると、保護者や他の子から見られ、認めてもらえる機会が増えるため、こどもたちの満足度や自己肯定感が上がる可能性があります。作品展示を見ながら「次はもっとこういうのを作りたい!」や「次はこんな材料で作りたい!」というこどもの声・リクエストを聞いておくと、次回の活動にも活かせます。
◎まとめ
学童で100均工作を行う魅力は「安く・簡単に・工夫次第で無限の可能性があること」です!高価な材料を用意しなくとも、ちょっとした発想力や工夫・準備で、こどもたちの目が輝き想像力が光る活動につなげることができます。こどもたちが全力で楽しみ取り組むことができる100均工作を、是非日々の学童保育に取り入れてみてくださいね。
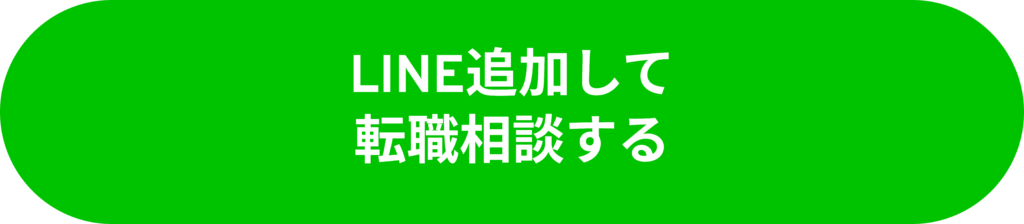
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。