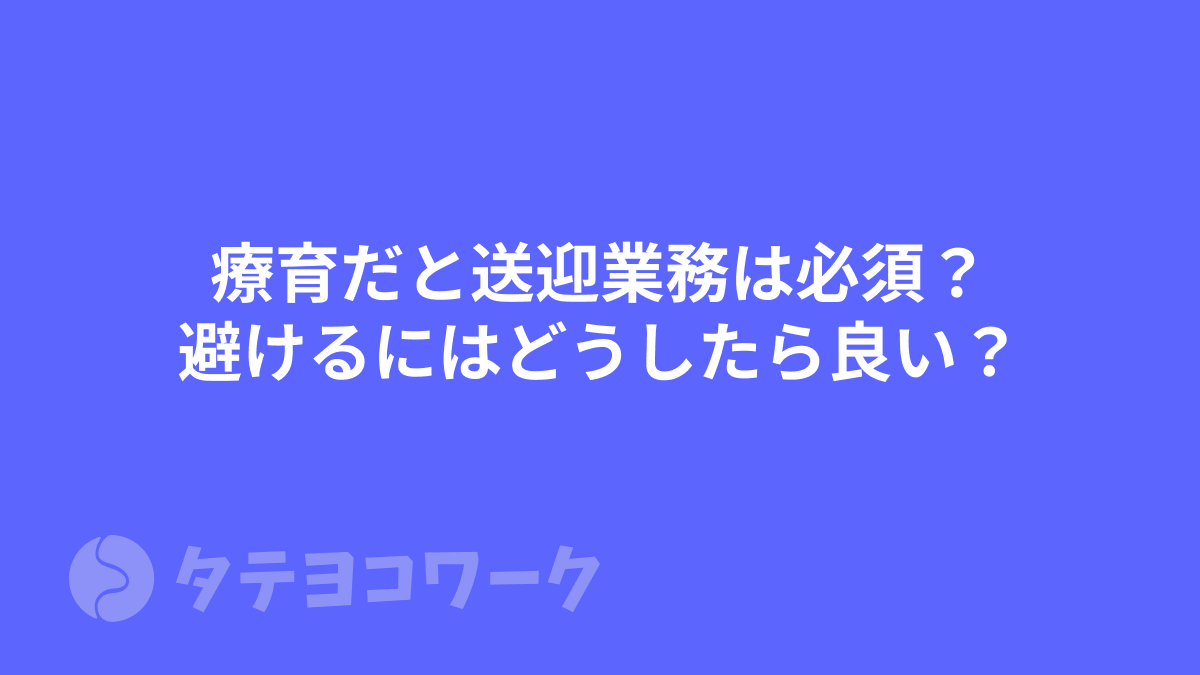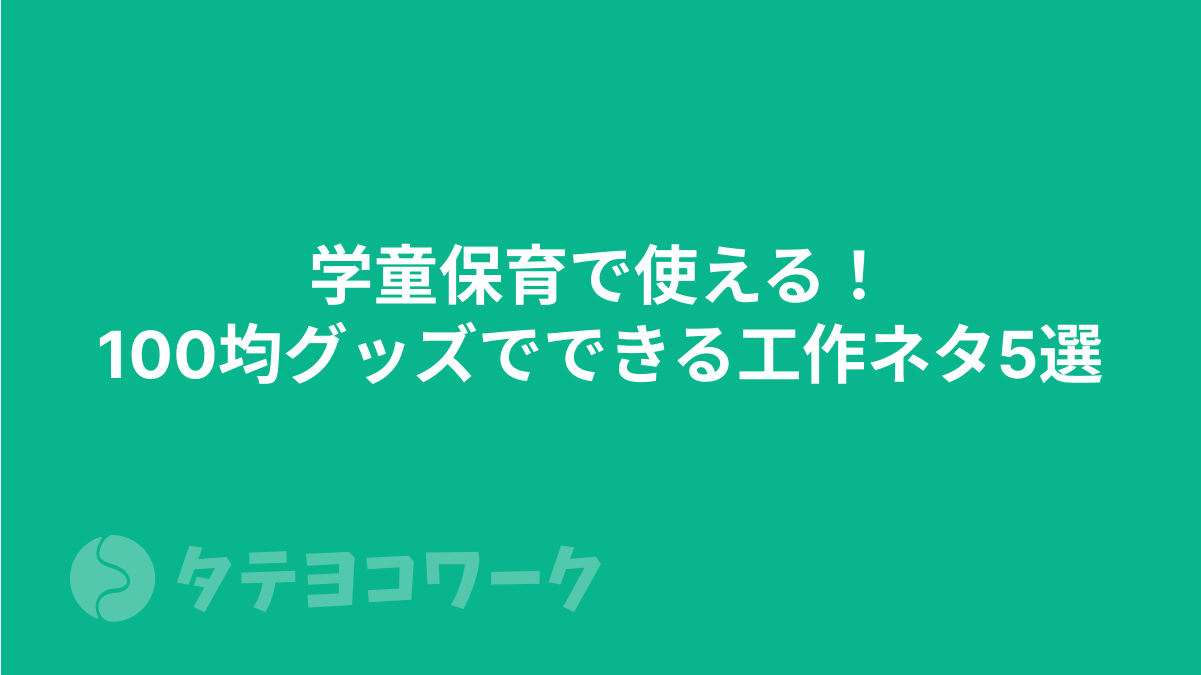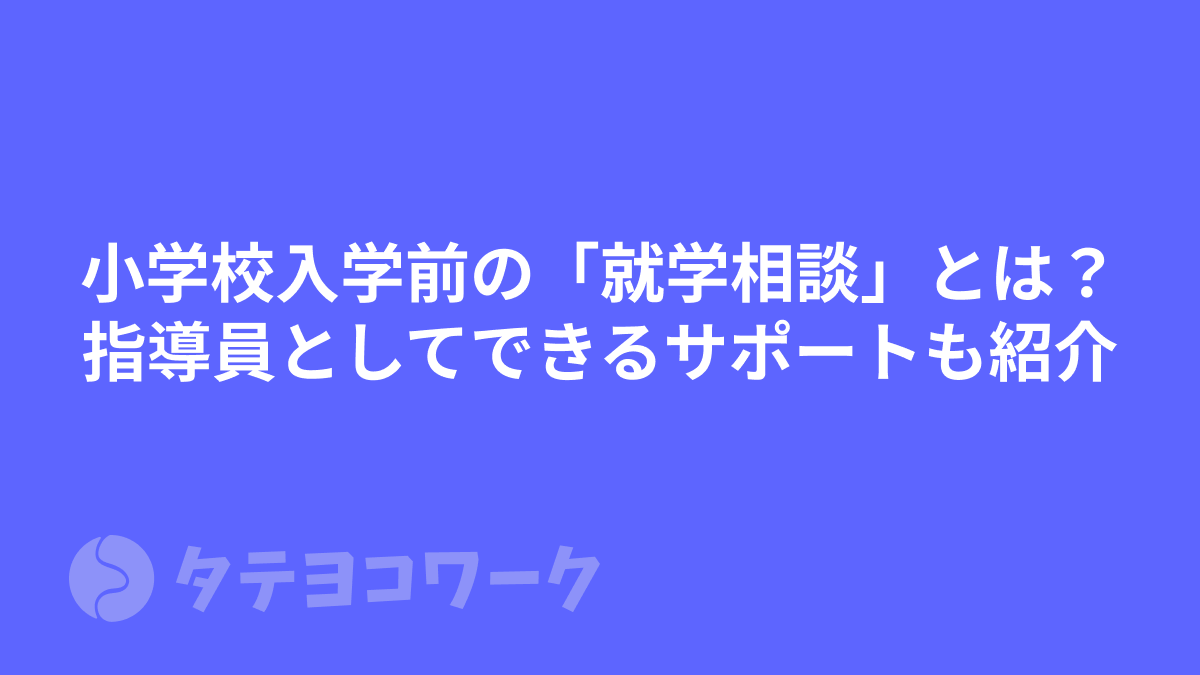タグで絞り込む
キーワードから探す
民間学童におけるおやつ事情!手作り?既製品?実例を紹介
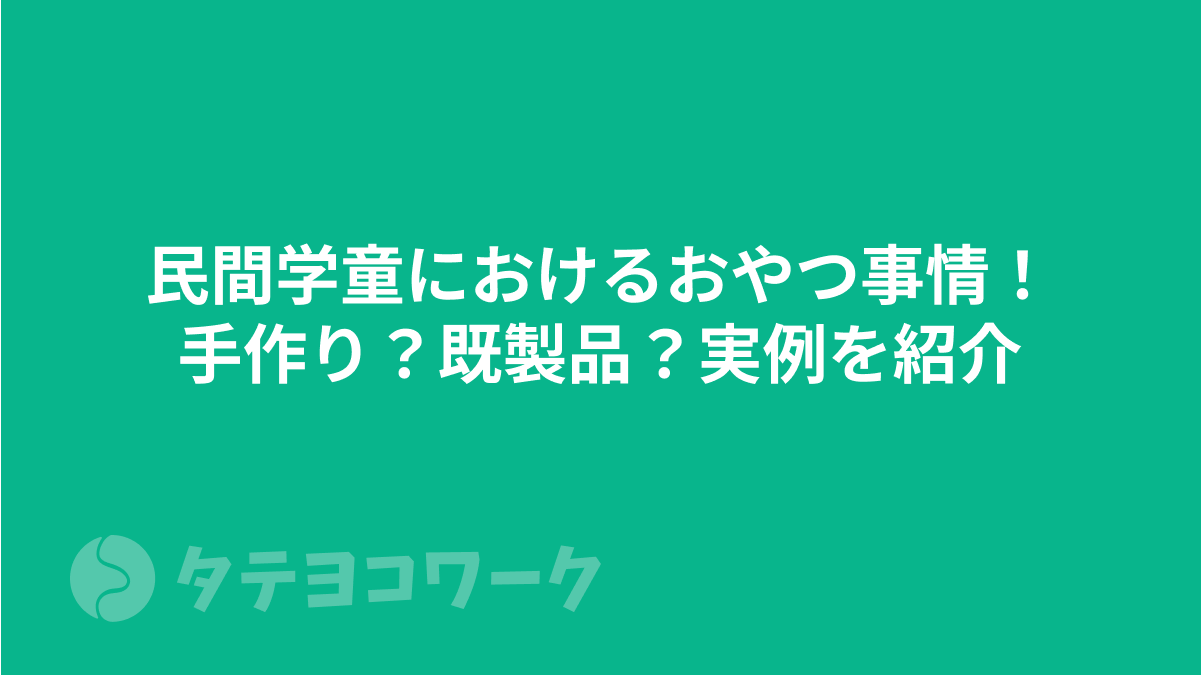
学童
ノウハウ
公立学童
民間学童
放課後児童支援員
あそび
実践事例
こどもたちが家の代わりに放課後の時間を過ごす学童保育所において、「おやつの時間」を1番の楽しみにしている子が多く存在します。そんなおやつが果たしている役割は、実は“単なる空腹しのぎ・腹ごしらえ” にとどまらないのです!
特に民間の学童保育所では、提供されるおやつの内容にも多様性があります。手作りのあたたかみのあるおやつ、市販品を工夫したもの、こども自身が調理に関わる体験型のおやつなど、バリエーションは実にさまざまです。
この記事では民間学童におけるおやつ事情について、「手作りおやつ」・「既製品のおやつ」・「子どもがつくる・体験するおやつ」の3つに分けながら、実例をまじえてご紹介していきます!
◎「手作りおやつ」について
「手作りおやつ」は学童保育所ならではの特別感やあたたかみがあり、学童保育の現場では長年大切にされてきました。出来立てのおやつや温かい食べ物の匂いが漂う空間は、学童を「家庭のように感じられる場所」にしてくれる効果があり、こどもたちにとって安心できる環境にする大きな要素といえるでしょう。
そして何より、「大好きな先生が作ってくれたおやつ」という事実が、よりおやつの味を美味しく感じさせ、先生とこどもたちの信頼関係を育むことにも繋がるのです。
民間学童の中には、「手作りおやつ」を大きな特色として掲げるところも多く存在します。焼きたてのホットケーキやクレープ、季節の果物を使ったゼリーやスイーツ、スープやおにぎりなど、バリエーションも豊富です。
食材を選ぶところからこだわる施設もあり、「旬」や「栄養バランス」、「色合い」を大切にしたメニューがたくさん用意されているので、見た目にも楽しく、こどもたちの五感を刺激するおやつの時間が生まれています。
しかし、「今日はどんなおやつかな?」とワクワクしながら学童に帰ってくるこどもたちの姿がある一方で、提供するスタッフにとっては、おやつの献立考案に実際の調理、徹底した衛生管理…と様々な手間が伴うのも事実です。
アレルギー対応はもちろんのこと、特に夏場などは、食中毒への配慮が欠かせません。また、最近では「添加物を出来るだけ含めないおやつがいい」や「甘いものを摂りすぎるのは心配」という幅広い保護者ニーズを汲んだメニュー調整も求められるとか…。
コロナ禍で「手作りおやつ」の文化が途絶えてしまった施設も多くあるようですが、スタッフの負担と利用者ニーズのバランスを考えながら様々な工夫をして手作りおやつに取り組んでる施設もあります。
ある民間学童では、「毎週⚫︎曜日は手作りおやつデー」と定め、それ以外の日は既製品のおやつを提供するというルールをつくることで、無理のない運営をしているそうです。毎日食べられるわけではないからこそ、「手作りおやつ」に対する特別感が生まれるのもいいところですね。
⭐︎手作りおやつ実践例〜白玉フルーツポンチづくり〜
学童の定番手作りおやつといえばフルーツポンチ!簡単に調理できる、こどもたちにも大人気のひんやり甘いおやつです。今回は白玉入りのフルーツポンチレシピをご紹介します。是非参考にしてください。
《白玉フルーツポンチ》
〜材料(15人分)〜
・白玉粉 450g
・水 450ml前後(様子を見ながら加えてください)
・缶詰みかん 3缶
・缶詰パイン 3缶
・サイダー 1.5L
〜作り方〜
1. 白玉粉に水を少しずつ加え、耳たぶくらいのやわらかさになるまでこねる。
2. 白玉を一口大に丸め、沸騰したお湯でゆでる。
3. 浮き上がったらすくい、冷水にとる。
4. 大きめのボウルやタライに白玉、缶詰フルーツ(シロップごと)、サイダーを入れて完成!
〜学童で作るときのポイント〜
・フルーツのミックス缶詰を使う際はアレルギーに注意してください。
・白玉を手で丸める際は手袋などをして衛生面にも注意をしてください。
・缶詰は汁ごと入れると甘みがちょうど良く、サイダーでさっぱりします。
・夏場は氷を入れるとより冷たく美味しくなります。
◎「既製品のおやつ」について
「既製品(市販)のおやつ」=手抜きである、というイメージを持たれることもありますが、実際には多くの民間学童で既製品のおやつは積極的に取り入れられています。
その理由は明確で、
①コスト管理がしやすいこと。
②アレルゲンが表示されており、アレルギー対応が容易なこと。
③食中毒などのリスクが低く、衛生的で安心なこと。
④準備が簡単なこと。
などが挙げられるでしょう。
つまり、圧倒的な「安全性」と「スタッフの負担が軽いこと」が魅力なのです。
こういった「既製品のおやつ」ですが、ただ配るだけでは味気ないと思われがち…ですが、ここでも現場の工夫が光ります!たとえば以下のようなアイデアが、多くの民間学童で実践されています。
☆既製品おやつを楽しむ工夫例
①おやつバイキング形式
数種類の個包装のおやつをトレイに盛り付けて並べておき、そこかはこどもたちは自分の好きなものを選んで食べることができるシステムです。こどもは自分で選ぶ行為自体が楽しいですし、自己選択をすることで主体性も育まれます。
②くじ引き形式
あらかじめおやつの名前を紙に書いて箱などに入れておき、こどもが箱から紙をくじのようにひくことで、自分が食べるおやつを決められる…というゲーム性が高く盛り上がるシステムです。
”くじでひいたおやつが嫌な時は、他児と交渉をして交換することもできる” という特別ルールを設けることで、「自分の思いを言葉にして相手に伝える力(=コミュニケーション能力、言語化能力)」や「嫌な時はNO!と断る力」を鍛える練習としている施設もあるそうです。
③お買い物ごっこ形式
複数のおやつに値付けをしてトレイに並べておき、手作りのお金を使ってこどもたちが好きなお菓子を選んで買うというシステムです。お金の使い方を学ぶ機会になったり、お金のデザインを考えるコンテストなどのイベントを付随させることができたりというメリットもあり、スタッフからもこどもたちからも人気が高いイベントです。
上記のような工夫を凝らさずとも、単に「配る」&「食べる」で終わらせず、「誰が何を選んだか」&「どのようなお菓子なのか」ということに目を向けてこどもたちに伝えることができれば、十分に豊かな時間になります。市販おやつでも「心の通った提供」は可能なのです!
◎「こどもがつくる・体験するおやつ」について
近年、民間学童において増えてきているのが、「こども自身がつくるおやつ」の取り組みです。パンケーキや白玉団子、フルーツ串、クレープ、サンドイッチなど、火や刃物を使わず安全に調理できるメニューを選ぶことで、楽しく安全な体験が可能になります。
ただ食べるだけではなく、「どうやって作るのか」や「どんな順番でやると効率が良いのか」、「少しの分量や材料の違いで味が変わること」など、多くの発見や学びがあるのがこども自身が作るおやつの魅力です。調理体験を取り入れることで、おやつの時間が「食育の時間」へと広がるのです。
ある民間学童では、調理の手順をこどもたち自身がタブレットで検索して調べて作る方式を採用しているそう。調理は苦手でもタブレットの検索で活躍する子、積極的におやつ作りに携わる子、こだわって盛り付けを楽しむ子など、こどもたち一人ひとりの個性が輝く貴重な時間になっているそうです。みんなで協力して作ることは、コミュニケーション能力や協働性を育むうえでも重要な機会となりますね。
また、おやつ作りを季節の行事と組み合わせることで、より記憶に残る楽しい体験になります。たとえば、サイダーゼリーに星形のフルーツを飾りつける七夕ゼリー作りや、平たく潰した食パンにクリームや好きな具材を巻いて作る節分の恵方巻風ロールサンドなどがあります。より具体的な実践例(レシピ)を以下にご紹介します。
⭐︎こどもつくる体験おやつの実践例〜オリジナルパフェづくり〜
こども自身が具材を選び、盛り付けられるオリジナルパフェ作りは、多くの民間学童で実践されている大人気おやつです。
〜材料〜
・ヨーグルト 1.5kg
・コーンフレーク 750g(1人50g)
・フルーツ缶詰 6缶程度
[トッピング用]
・カラースプレー 150g
・チョコチップ 150g
・ミニマシュマロ 150g
・チョコソース 200ml
・ホイップクリーム 1000ml
〜作り方〜
【スタッフの下準備】
・缶詰フルーツは汁を切り、食べやすい大きさにカットしておきましょう。
・ 「コーンフレーク」「ヨーグルト」「フルーツ」「トッピング」を別々のお皿・ボウルに用意して盛りつけ専用エリアを確保しておきましょう。
1. こどもたちが透明カップに、コーンフレーク → ヨーグルト → フルーツ → トッピングの順で自由に好きなものを入れる。
2. 仕上げにホイップクリームやチョコソースをかければ完成!
〜学童で作る時のポイント〜
・配分が心配な食材(最初の方で多く盛りつけをしすぎて終盤足りなくなる、盛りつけ量が少なすぎて余るなど)に関してはスプーンの大きさで調整するのがオススメです。「スプーン一杯までなら自由に量の調整ができる」というルールにするだけで、分配ミスが防げますよ。
・同じタイミングで一気にこどもたちに盛り付けをしてもらうと混雑して混乱が起きます。テーブルごとに分けたり時間を分けたりしてスムーズなおやつ作りにしましょう。
◎民間学童における”おやつ提供の課題”とは?
これまで大きく3つに分けて、民間学童のおやつ事情についてまとめてきました。民間学童は基本的に公立の学童に比べて人数が少ないため、おやつの時間を工夫しやすいところが魅力といえますね。
しかし、民間学童においてもおやつの提供あたってはいくつかの課題があります。
まずはアレルギーのこと。卵や乳、小麦にナッツにフルーツ…食べられない食材はこどもによってさまざまです。材料の確認や器具の使い分けなど、細やかな配慮が欠かせません。
次に衛生管理。特に暑い季節は、食材のいたみ・食中毒が心配です。冷蔵庫の使い方や手洗い、調理器具の消毒などを徹底する必要があります。
最後はコスト管理と人手のバランスです。手作りおやつは気持ちがこもっていて大変魅力的ですが、材料費や作る時間がかかります。逆に市販品は手軽で安定して用意できますが、どうしてもマンネリ化しやすいというデメリットも…。
こうした様々な課題と向き合いながら、毎日のおやつ時間がもっと楽しく、安心できるものになるよう工夫しているのが民間学童の現場なのです。
◎まとめ
民間学童は非常に自由度が高いからこそ、手作りおやつに市販の既製品おやつ、こどもたちが一緒に作るスタイルのおやつと、様々な形のおやつ提供が可能です。もちろん、アレルギーや衛生面、コストや保護者の希望など、乗り越えるべき課題はありますが、そのぶん工夫のしがいがあるのも事実です。
おいしくて、楽しくて、こどもへの想いが伝わるちょっと特別なひととき。それが民間学童における大切なおやつの時間なのです。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。