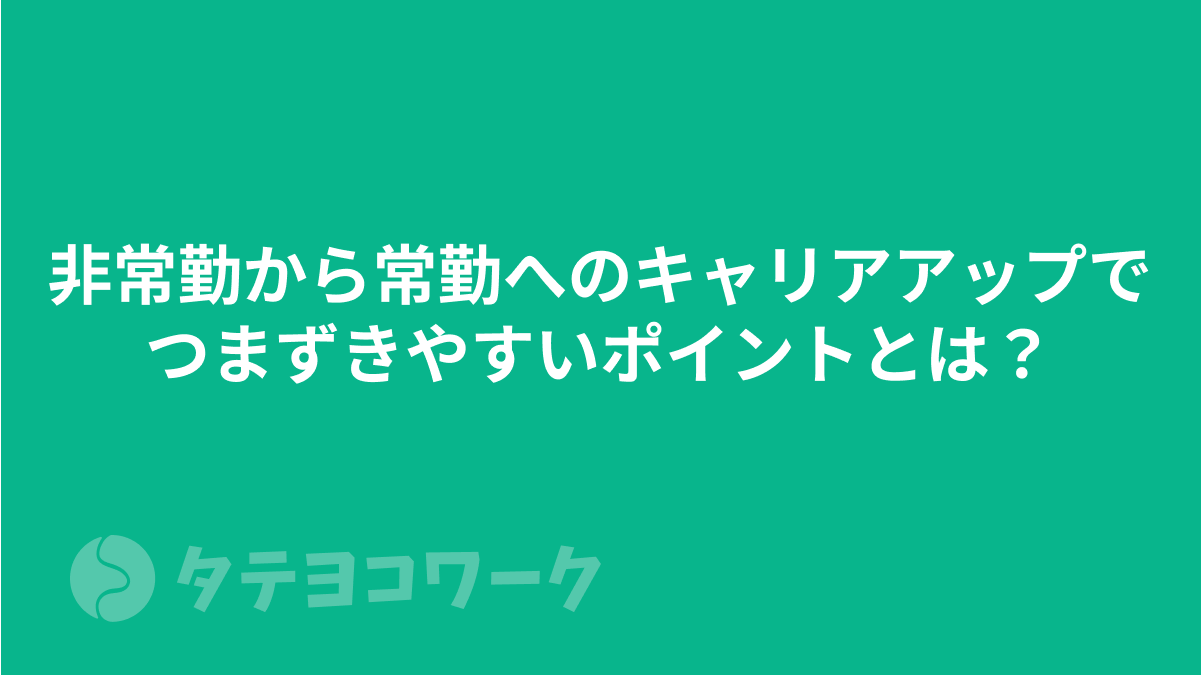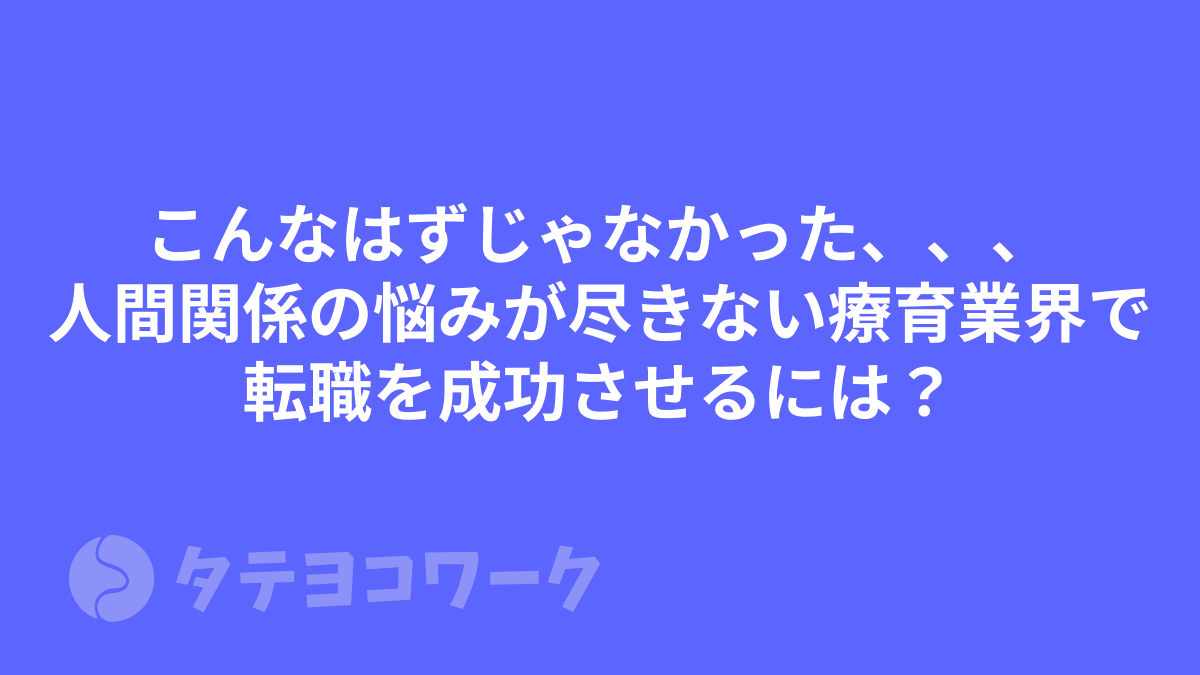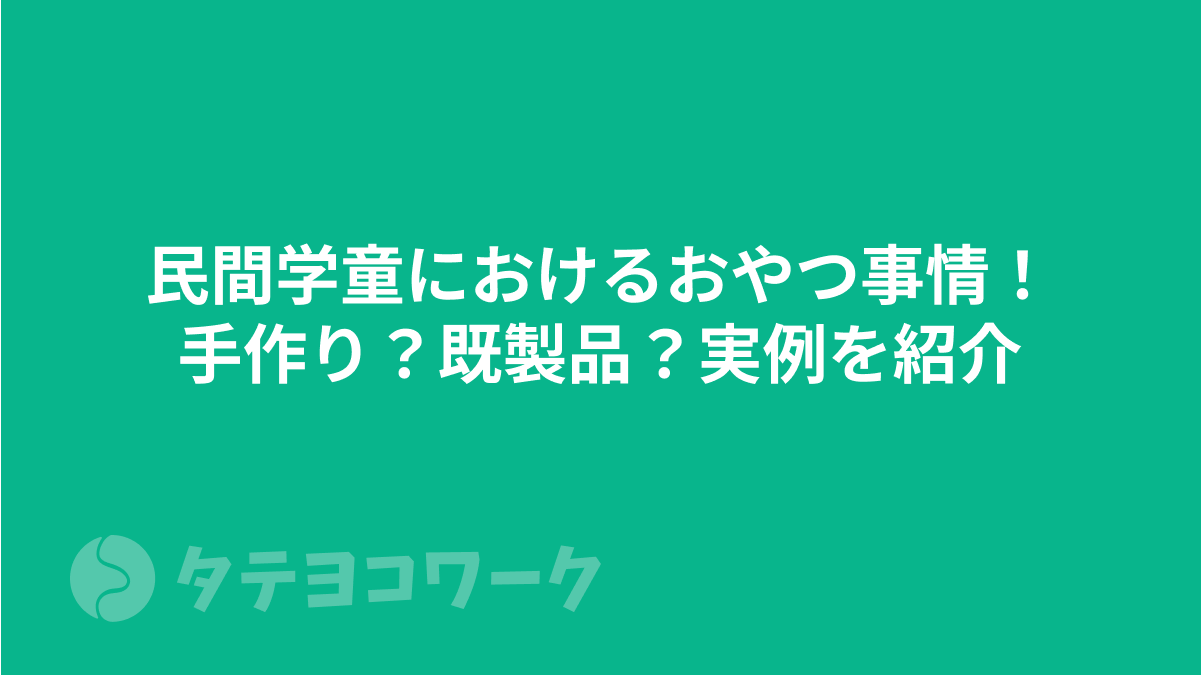タグで絞り込む
キーワードから探す
学童にICT導入って必要?デジタル化で変わる現場の姿
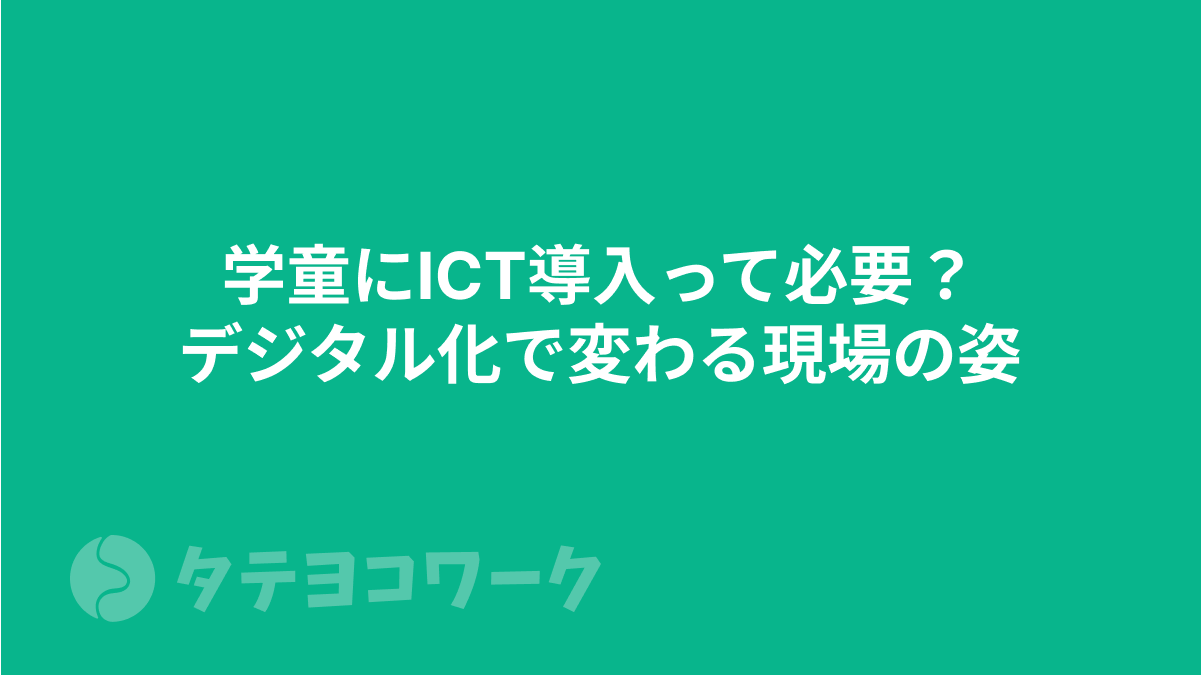
学童
公立学童
民間学童
学童経営
共働きの家庭にとって無くてはならない学童保育所は、戦後の時代に地域住民が「放課後のこどもたちに安心できる居場所を」と立ち上げた活動がルーツであると言われています。空き家や寺の一角を利用して始まった小さな場が、1970年代には制度化され、いまや全国で100万人以上のこどもたちが利用する重要な社会インフラへと成長しました。
ただ、この文化は長らく “スタッフの経験と紙の記録” に支えられてきており、電話連絡に手書きのお便り・プリント配布などが伝統的に続けられていたため、最新技術とは縁遠い世界でもありました。こどもたちの遊びもコマやけん玉、おままごとにボードゲームなどのアナログな遊びが中心。これらは学童保育所では“当たり前”のことであり、人との繋がりが感じられるような温かみのある空間を作り出している大切な要素でもあります。
そんなアナログといわれる学童業界においても、共働き世帯の増加や利用者の多様なニーズ、そしてコロナ禍などの状況の変化によって、近年急速にICT導入への関心が高まってきています。
果たして、学童保育所にICTを導入する必要はあるのでしょうか? 本コラムでは、学童におけるICT導入の現状やメリット、課題、今後の展望について詳しくまとめていきます。
1. 学童現場におけるICT導入の現状
◎学校・保育園との比較
学校ではGIGAスクール構想により、児童生徒一人一台端末の整備が進み、ICT環境が急速に整備されています。授業でのICT活用や、校務の情報化も進んでいます。保育園でも、保護者連絡アプリやクラウド型の児童台帳などが少しずつ浸透しつつあるようです。
しかし学童保育所の現場は、地域性や運営主体によって差が大きく、ICT導入が進んでいるところと、ほとんどアナログの制度のまま運営をしているところが混在しているのが現状です。
◎学童保育所で使われているICTの例
学校や保育園と比べるとやや遅れがあるとはいえ、近年は少しずつ学童現場でもICTの導入が進みつつあります。すでに活用され始めているICTには次のようなものがあります。
①入退室管理システム
ICカードやQRコードでこどもの入退室を管理し、保護者に自動通知するシステムです。保護者が安心するだけで無く、こどもたちを目視確認して名簿にチェックをしていくような従来の登所管理と比較すると、大幅に現場スタッフの負担が軽減されます。
②出欠予定管理システム
登所予定や欠席連絡、延長保育の希望などをアプリから申請できるシステムです。保護者が利用予定を記載した紙をこどもに持たせ、スタッフが受け取るという登所予定管理の流れが必要なくなります。また、突然の予定変更も従来は連絡帳に書いたり電話をしたりする必要がありましたが、アプリからすぐに連絡できるのも保護者にとっては嬉しいポイントです。
③連絡帳アプリ
スタッフから保護者に学童でのこどもの様子やイベントの持ち物などを伝えたり、保護者からスタッフに家庭での状況や困りごと・体調の変化などを伝えるための連絡手段として、これまでは紙の連絡帳や電話が活用されてきましたが、アプリで全て代用できるようになるシステムです。
④業務支援ツール
シフト管理、支援計画や日誌の作成支援などの効率化を図るシステムで、うまく活用すれば日々の事務作業が圧倒的に楽になります。
◎導入率のばらつき
大手の民間学童では早期から導入が進んでいる一方、公設学童や地域の小規模クラブでは導入が遅れがちです。その背景には予算の制約、導入に伴う職員の学習コスト、自治体の方針の違いなどがあります (詳細は本コラム「3. ICT導入における課題って?」をご覧ください)。
また現場でもICT導入に対して積極的な意見と消極的な意見が混在しており、特に御年配のスタッフが多く働いている施設では導入が進みづらい…という状況もあるようです。
2. ICT導入によるメリットって?
ICTを導入することで、現場で働くスタッフにとっても、利用者である保護者とこどもたちにとっても、多くのメリットがあると考えられます。
①職員の負担軽減
学童保育所では、出席簿や日誌、お便りに保護者への配布物など、紙による事務作業が膨大です。ICTを活用すればそれらの事務作業の負担が軽減されるだけでなく、入退室の自動管理や児童記録の効率化、連絡業務の簡略化が可能になります。その分、スタッフはこどもたちと直接関わる時間にエネルギーを注ぐことができるのです。
②保護者の利便性向上
共働き家庭にとって、学童保育所との連絡は迅速かつ手軽であることは大きなポイント。アプリを使えば欠席連絡や急な予定変更の連絡をスマホひとつで完結でき、こどもの入退室状況をリアルタイムで確認することもできます。また、行事予定や配布資料もオンラインで共有できるため、プリントの紛失防止や情報の見逃しを減らせます。ランドセルの奥底から大切なお知らせの紙が出てきた…という絶望からおさらばできるのです!(笑)
③こどもたちの学びの充実化
ICT導入は、スタッフと保護者のためだけでなく、こどもたちの学びや体験の幅を広げるという大きなメリットも併せて持っています。
具体的には、調べ学習や創作活動にタブレットを活用したり、プログラミング学習やデジタルアート制作の活動を取り入れてみたり、他施設や自宅にいる子とオンライン交流を図ってみたりといったことができるかもしれません。これらの活動は「放課後ならではの探究活動」を実現し、こどもの好奇心や主体性を伸ばすきっかけになると考えられます。
3. ICT導入における課題って?
こんなにもメリットがたくさんあるのなら、どんどん学童保育所にもICTを導入したらいいのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ICT導入にはいくつかの大きな課題があるのです。
①導入コスト・予算
システム導入には初期費用や維持費用がかかります。場合によっては数十万円単位の費用がかかる場合もあるため、予算が限られている学童保育所にとっては大きな負担となってしまいます。
なお、導入コストの課題を解決するために、国や自治体では補助金制度を設けています。文部科学省や内閣府による「放課後子供総合プラン」関連経費として、入退室管理や業務効率化システム導入に補助が出る場合があります。また、東京都や大阪府などの一部自治体では学童クラブのICT導入を支援する補助制度を設けています。教育・子育て支援を目的とした財団がICT機器購入を助成するケースもありますので、こまめに最新情報をチェックすることで導入の負担をグッと下げることができるかもしれません。
②ICTに関する知識不足
ICTを導入できたとしても、スタッフがICTに不慣れだと、逆に業務が煩雑になってしまうリスクを孕んでいます。そのため、ICTを使いこなせる人材を配置したり、職員へICTの研修を実施したりする必要がありますが、なかなかその余裕がない…という現場も多くあります。
③個人情報とセキュリティのリスク
こどもたちの個人情報をアプリで管理することになると、情報漏洩や不正アクセスのリスクは少なからず発生してしまいます。システム選定時のセキュリティ対策や、職員による適切な運用ルールの徹底が不可欠となります。
④学童の良さが損なわれるのでは?という懸念
学童は「人との関わり・遊び」が中心のあたたかな居場所です。ICTが便利だからといってデジタル活動に偏りすぎて、こどもの育ちに必要な「体験的な学び」が損なわれるのではないかという懸念を抱く現場スタッフが一定数います。ICTが学童における「活動の中心」になるのでは無く、あくまで「支える道具」として位置づける必要があるのかもしれません。
4. これからの学童はどうなるの?
学童保育所のこれからを考えると、「ICTを導入するかしないか」ではなく「ICTをどう活用するか」が重要になってくるといえるでしょう。業務効率化に活かせるものは積極的に取り入れ、こどもたちへの活動には選択肢の一つとして提供し、生活面や感情面のケアは人が担っていく…そんなバランスが理想形のひとつかもしれません。
また、ICTの活用は学童保育所同士や他自治体との繋がりを広げる可能性も持っています。リアルではなかなか会えない距離にいる学童施設の子たちと繋がって一緒に遊ぶことができたり、オンラインで外部講師をゲストに呼んだ企画をしたり、複数施設が合同でイベントを行ったりと、これまでの学童保育所の枠を超えた学びの機会を作り出せます。
人の繋がりや体験から得られる学びを重要視してきた学童保育所だからこそ、最新技術をうまく活用すれば、こどもたちのさらなる飛躍的な成長の場になる可能性があると考えられます。

おわりに
学童保育所におけるICT導入は「便利だから導入する」だけではなく、「こどもたちにより良い放課後を提供するための手段」として捉えて考えていく必要があります。
職員の負担を減らし、保護者に安心を与え、こどもたちの学びや体験を広げる。こうした効果を最大化するには、アナログとデジタルを掛け合わせた“ハイブリッドな学童”を目指すことが大切です。
ICTは学童保育所の現場をより豊かに変えていく力を持っています。これからの学童保育所は、変化を過剰に恐れることなく、従来通りのあたたかい人の関わりをベースにしながらデジタルの力を加えていくことで、さらに進化していくのではないでしょうか。
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。