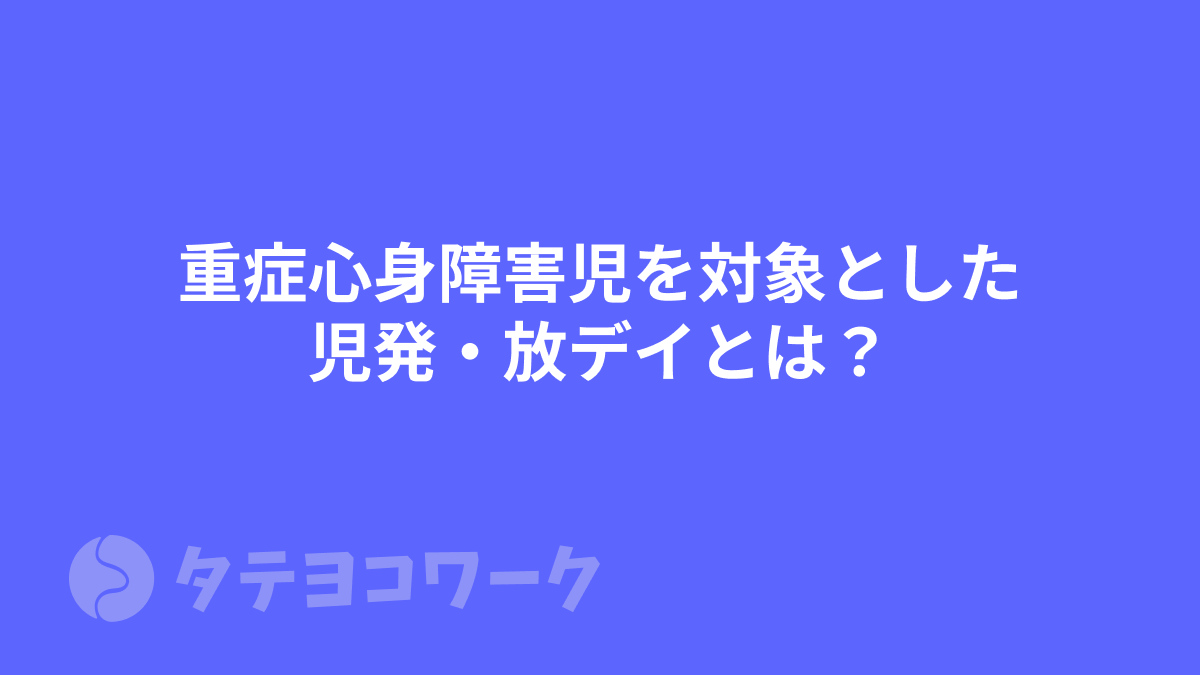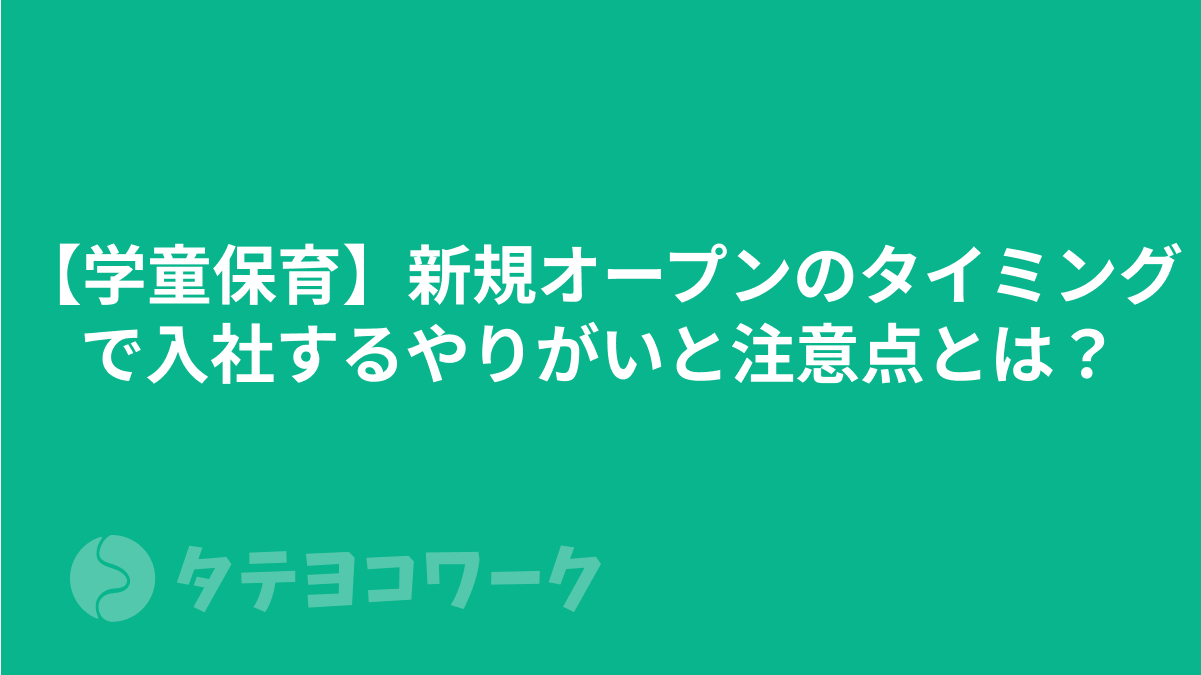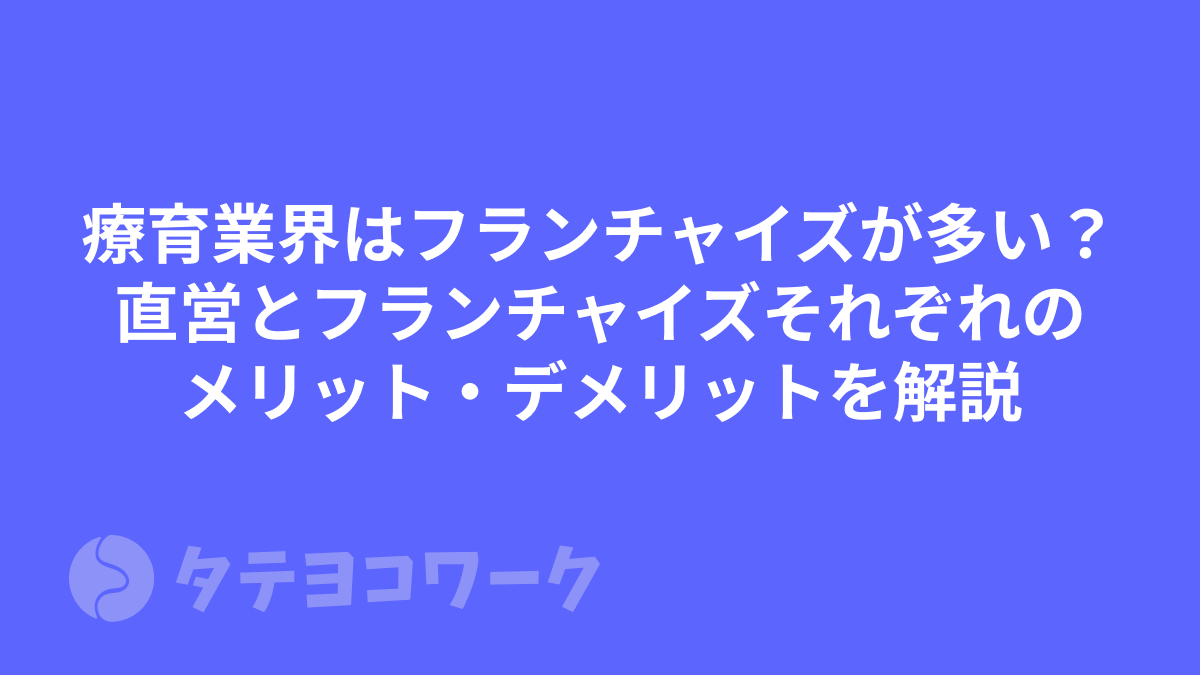タグで絞り込む
キーワードから探す
非認知能力とは?子育てや保育に活かせる実践的な伸ばし方もご紹介!
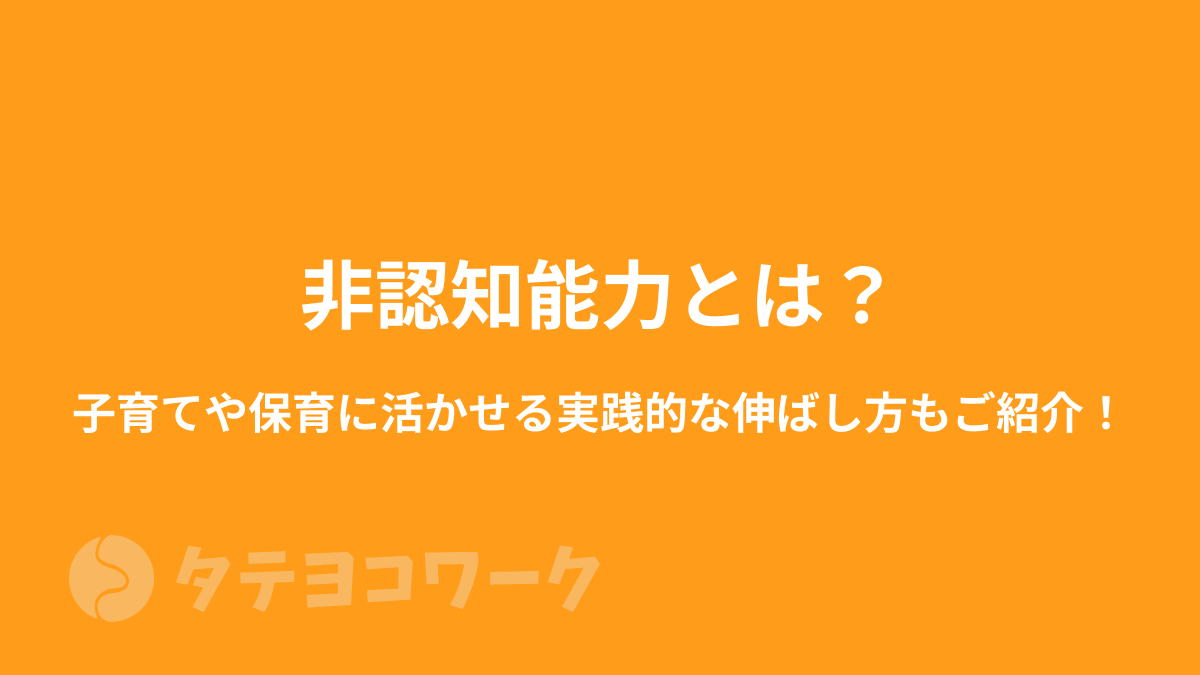
学童
療育
子育て
あそび
児発
放デイ
非認知能力
社会が急速に変化し、これからを生きていく子どもたちに必要とされる力も少しずつ変わってきています。
その中でも最近よく耳にしたり目にしたりするのが「非認知能力」です。
非認知能力とは、一体どのような能力のことを指していて、なぜ重要視されているのでしょうか?
そして、私たちは日常生活や保育の中でどのようにしてこどもたちの非認知能力を育むことができるのでしょうか?
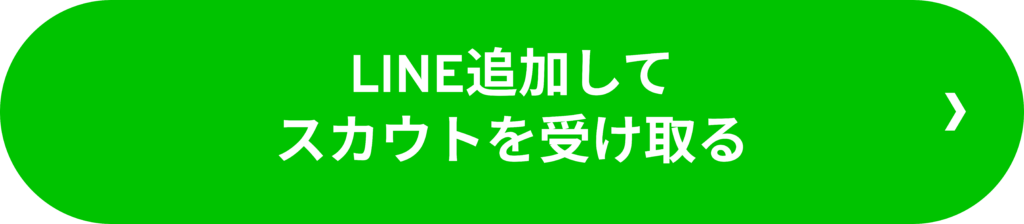
今回は、非認知能力の基本から実践的なアプローチまでをわかりやすくご紹介します。
1. 非認知能力とは?
非認知能力とは、「これからの時代に必要となる、目に見えない力」のことです。
テストなどで測定可能な認知能力に対し、非認知能力は基本的に数値化することができないため、目に見えないという表現が使われます。
以下に、具体的な非認知能力の例を挙げてみましょう。
・社会性
・協調性
・コミュニケーション能力
・自制心
・忍耐力
・自尊心
・好奇心
・柔軟性
ノーベル経済学賞受賞者であるジェームズ・J・ヘックマンが、「非認知能力は、認知能力(IQや学力)以上に、長期的な社会的・経済的成功に寄与する場合がある」という研究結果を発表したこともあり、非認知能力は現在、世界的に大きな注目を集めています。
2. 今、非認知能力が重要視されている理由
上述のとおり、ジェームズ・J・ヘックマンが提唱したことで非認知能力の注目度が上がったことは事実なのですが、実は以前から「生きる力」や「自ら考える力」などという言葉で、非認知能力は教育や子育てにおいて重要視されてきました。
それが今、これまで以上に必要とされている理由は「社会の大きな変化」にあります。
最も大きな社会の変化の一つとして挙げられるのが、AIの発達です。
人間が担ってきた仕事の多くを、これからはAIに任せられるようになっていきます。AIは認知能力、特にデータ処理や分析、高速で高精度な計算などを得意分野としています。そのため、AIと共に生きて豊かな社会をつくっていくには、人間は人間にしかできないこと=非認知能力を活かした仕事を担うことが求められるのです。
創造力を活かして完全に新しいアイデアや作品を作りだすことや、共感力や感受性が求められること、道徳的価値観に基づいた判断が必要なことなど、人間にしか出来ないことの多くは非認知能力が生み出してくれるため、これからの時代に必要とされる能力であると考えられています。

3. 子どもの非認知能力を育む実践的な方法
非認知能力は、「自分自身と向き合い、自分の意思で伸ばしていくもの」とされているため、周囲が一生懸命に働きかけても、子ども自身に伸ばしたいという意思がなければ変化は生まれません。
しかし、子どもの非認知能力を育むことができないというわけではありませんのでご安心ください。
適切なアプローチをすることで、子ども自身が非認知能力を伸ばすための意識改革や行動の変容を起こしやすくすることができます。今回は子育てや保育の現場で活かせる実践的な方法をご紹介してきます。
⑴ たくさん対話をする!
…子どもと大人もしくは子ども同士で対話する時間を確保することで、子どもたちの自己表現力や共感力を育む土台が築かれます。子どもが安心して感情を共有できる環境は、心の健康を守るだけでなく、自分自身と向き合う力を養います。例えば「今日は何が楽しかった?」といった簡単な質問から、子どもの思いや感情を引き出し、適切に受け止める習慣を始めてみてはいかがでしょうか?
⑵ 発達段階に応じた挑戦の機会をつくる!
…子どもに適切な難易度の課題や活動を提供することで、小さな成功体験を積み重ねられ、自信を築くきっかけを作ることができます。自己効力感を高める効果もありますので、将来の挑戦に対する意欲や粘り強さにつながります。この時、重要なポイントとしては「挑戦の結果ではなく、過程を認める」といことです。成功したとしても失敗してしまったとしても、前向きに挑戦に取り組んだ姿勢を認めてあげることで、「失敗しても大丈夫」、「私なら大丈夫」というような安心感と自己肯定感を育むことができるのです。
⑶ 仲間で協力する遊びや活動を取り入れる!
…チーム活動を通じて、社会性や協調性を育むことができます。複数人で協力する遊びは、コミュニケーション能力や問題解決力を鍛える機会にもなります。みんなでボードゲームやスポーツ活動をする機会をつくるだけでも、お互いに助け合ったり意見を共有したりする経験ができるので非常にオススメです。
⑷ 子どものことをよく観察して、実況中継と評価をする!
…子どもの行動をじっくりと観察し、実況中継をするように行動の背景を伝えて評価をすることで、自己理解を促すことができます。「今、昨日よりも高く積み木を積み上げているね。集中して取り組んでいるね」のように、具体的なフィードバックをすることで、達成感を感じてもらい、成長を実感してもらうことができるのです。最も効果的なのは、本人が無意識に行なっている行動の実況中継や評価です。自分では気がついていない良いところや成長しているところなどを周囲から教えてもらえると、ぐっと自己肯定感が高まります。
4. まとめ
このように、非認知能力は子どもたちの未来を形作る重要な土台といえますね。
日々の生活や保育の場での、ちょっとした工夫や意識が非認知能力の育成に繋がることを知っていただけたでしょうか?
また、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出すためには、私たち大人が自分の非認知能力を伸ばしていくことも非常に大切です。非認知能力が高い人と関わることが、子どもたちの非認知能力を伸ばすコツでもあります。自分自身にしっかりと向き合って新たな刺激や変化を受け入れていくことで、大人であっても少しずつ非認知能力が向上していきますよ。
大人も子どもも非認知能力を身につけて、豊かで充実したこれからの時代を生きていきましょう。
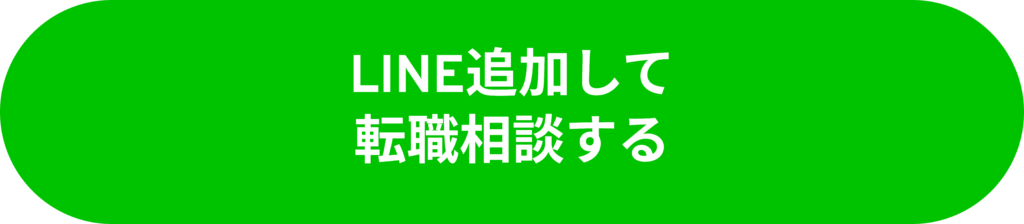
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。