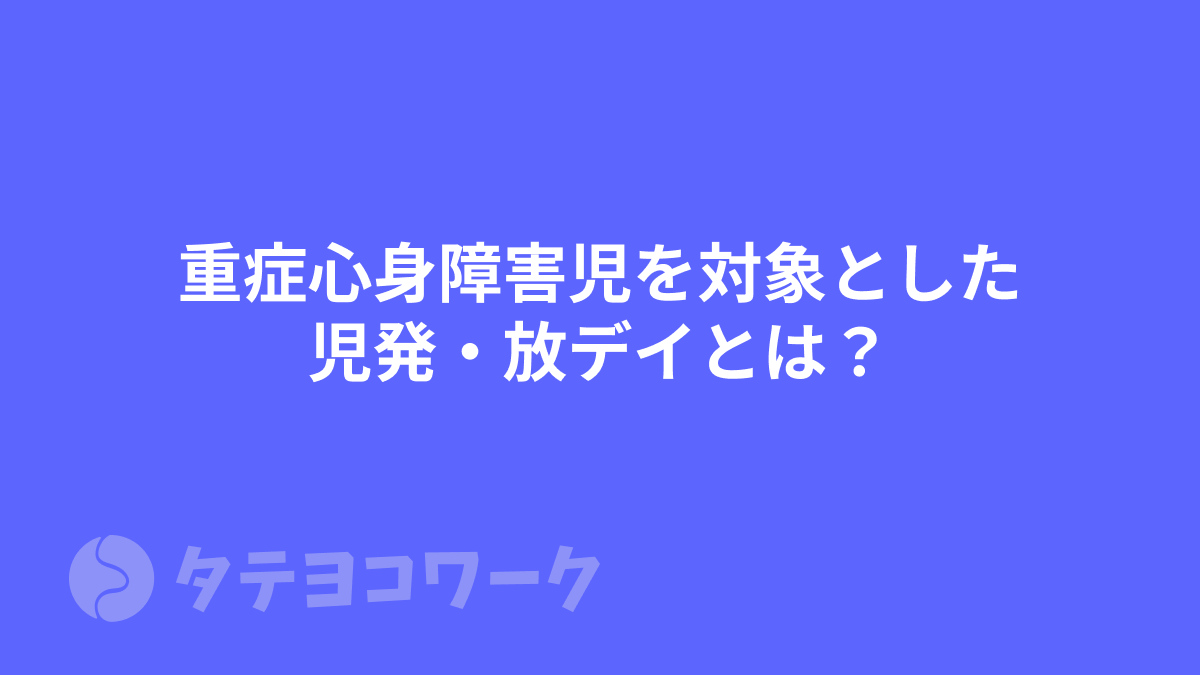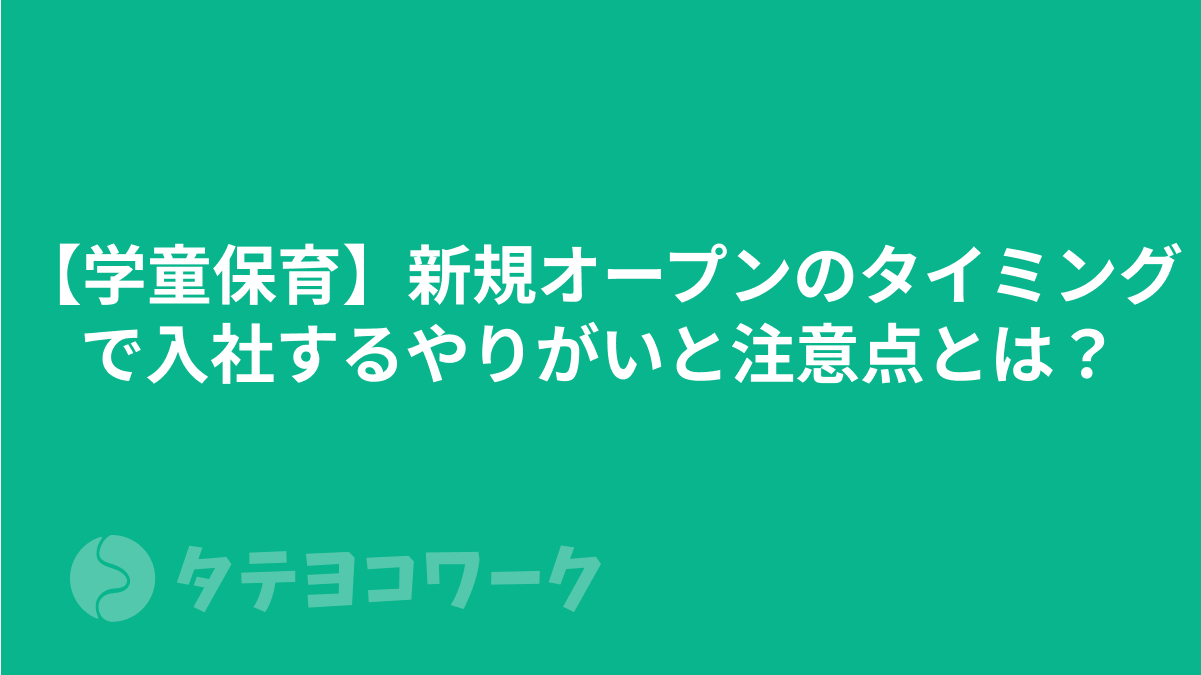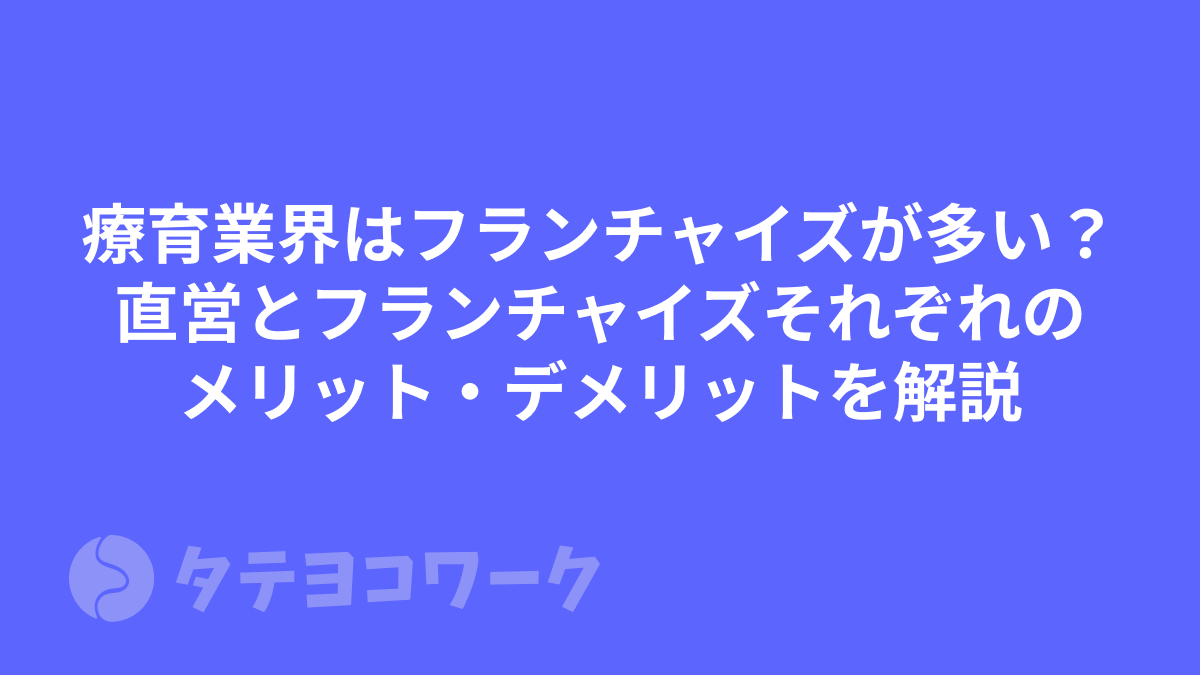タグで絞り込む
キーワードから探す
療育における学習⽀援とは?求められるスキルや存在意義をご紹介!
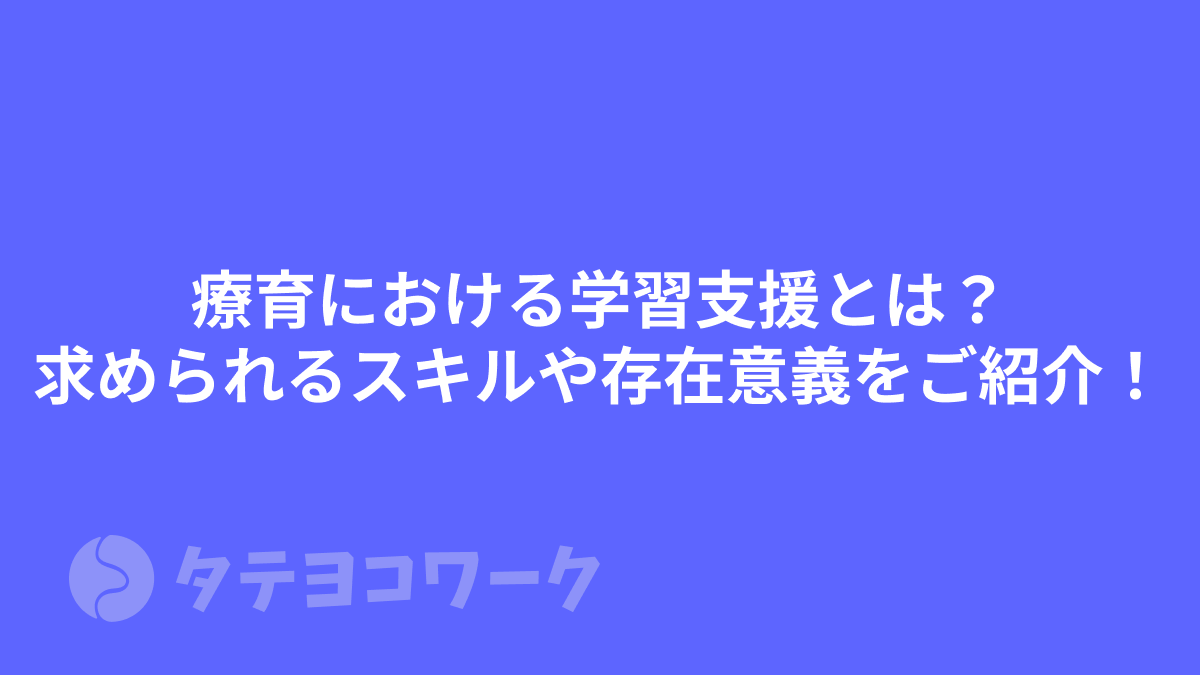
療育
専門性
発達支援
児発
放デイ
学習支援
はじめに
療育とは、発達に課題を抱える⼦どもたちが社会的に⾃⽴し、豊かな⽣活を送るために⾏わ
れる⽀援の総称です。その中でも「学習⽀援」は、単なる勉強を教えるという枠を超え
多⾓的かつ本質的な役割を担っています。個々の特性に応じた⽀援は、⼦どもたちの可能性
を広げ、将来的な⾃⼰実現につながります。
本コラムでは、療育における学習⽀援の⽬的や実践⽅法、⽀援者に求められるスキル1⼈1
⼈の特性に合わせた⽀援⽅法について詳しく解説します。

1. 療育における学習⽀援とは
療育における学習⽀援は、⼦どもたちの「わかる」「できる」「たのしい」という経験を積み
重ねていくことが重要視されます。学校での⼀律的な学びとは異なり、療育の場では「その
⼦にとっての最適な学び⽅」を探ることが最優先されます。
いわば個別アレンジが⾮常に重要なものになるのです。
例えば、ひらがなの読み書きに困難さがある⼦どもには、⾳と⽂字を結びつけるアプローチ
を⾏い、数字の理解が曖昧な⼦どもには、実際の買い物ごっこなど体験型の活動を通して数
の概念を⾝につけてもらいます。これらは単に知識を詰め込むのではなく、「経験としての
理解」を⽬的としています。
加えて、学習⽀援には「成功体験を積む」という⽬的もあります。学校でつまずきやすい⼦
どもにとって、少しでも「できた」という感覚を持つことは、⾃⼰肯定感を育む第⼀歩です。
2. ⽀援者に求められるスキル
療育に参加する⼦ども達に誰1⼈として全く同じ発達特性を持つ⼦はいません。
だからこそ、療育現場で学習⽀援に携わるには、以下のようなスキルや姿勢が求められます。
2-1. アセスメント⼒
⼦どもたちの現状を把握し、どこに困難があるのか、どのような⽀援が必要かを⾒極める⼒
です。発達検査の結果や観察記録、保護者からのヒアリングなど、様々な情報を総合して評
価することが⼤切です。
2-2. 個別最適化の視点
同じ課題でも、⼦どもによって提⽰⽅法や難易度を変える必要があります。たとえば、同じ
「数字の書き取り」でも、視覚⽀援をつけたり、体の動きを加えたりと、⼯夫が求められま
す。いわゆる「個別⽀援計画(IEP)」の⽴案が⼤事ですね。
2-3. 継続的な関わりと信頼関係の構築
⼦どもとの信頼関係がなければ、学びは成⽴しません。⽬を⾒て挨拶を交わす、失敗しても
受け⽌める姿勢で接するなど、⽇々のコミュニケーションが⼤切です。
2-4. チーム連携⼒
療育は⼀⼈では成り⽴ちません。保護者、学校、医療機関、⽀援機関などと情報を共有し、
連携を取る⼒が⽋かせません。
3. 視覚優位・聴覚優位とは?その⾒分け⽅と⽀援⽅法
⼦どもによって、「どの感覚から情報を取り⼊れやすいか」には違いがあります。⼤きく分
けると「視覚優位」と「聴覚優位」のタイプが存在し、それぞれに合わせた⽀援を⾏うこと
が、効果的な学習⽀援の鍵となります。
3-1. 視覚優位とは
視覚優位の⼦どもは、「⾒て覚える」ことが得意です。⽂字や絵、写真、図などを通じて情
報を理解しやすい傾向があります。
特徴の⼀例:
•話を聞くより、図やイラストで⾒た⽅が理解が早い
•黙読よりも絵本や写真の多い教材を好む
•順序やルールを図解にすると⾏動しやすい
⽀援⽅法:
•スケジュールを「絵カード」で提⽰する
•作業⼿順を「写真付き」で⽰す
•数学の問題を「視覚的なブロック」や「図解」を⽤いて説明する
視覚優位の⼦どもにとっては、⼝頭だけの説明では情報が抜け落ちてしまうことがあります。
なるべく「⾒てわかる」⼯夫をしましょう。

3-2. 聴覚優位とは
聴覚優位の⼦どもは、「聞いて覚える」ことが得意です。⽿での情報処理に⻑けており、⾳
声での説明や⼝頭のやり取りに強みがあります。
特徴の⼀例:
•⼀度説明を聞くと内容を覚えている
•⾳読やリズムでの学習が得意
•メロディーやリズムを活⽤した記憶が得意
⽀援⽅法:
•学習内容を「歌」や「リズム」に乗せる
•説明や指⽰は「はっきりとした声」で、短く簡潔に伝える
•⽿で覚える教材(オーディオ教材など)を活⽤する
聴覚優位の⼦どもは、視覚情報が多すぎると混乱することがあります。静かな環境で「⽿に
集中できる」⼯夫を⼼がけると良いでしょう。
3-3. どうやって⾒分けるか?
実際には、すぐに「視覚優位」「聴覚優位」と明確に分かるわけではありません。⽇常の⾏
動観察や反応を通じて、どちらの感覚をよく使っているかを⾒極めていくことが⼤切です。
観察のポイント:
•説明を聞いたあと、どのように理解・⾏動するか?
•絵カードと⼝頭説明、どちらに反応がよいか?
•⾳読と黙読、どちらが得意そうか?
必要であれば、発達⽀援専⾨家や⼼理⼠と連携し、正確なアセスメントを⾏うことも重要で
す。
4. 学習⽀援が⼦どもにもたらす意義
学習⽀援を通して、⼦どもたちは次のような⼒を育んでいきます。
・⾃⼰肯定感
「できた」「わかった」と感じられる経験は、⾃⼰肯定感の⼟台になります。療育の現場で
は、⼦どもたちの⼩さな成功を積み重ね、ポジティブな⾃⼰イメージを育てます。
・主体性
⾃分から取り組みたい、⾃分のやり⽅でやってみたいという気持ちは、社会で⽣きる⼒の根
本です。⽀援者が⼿を出しすぎず、⼦どもが⾃ら考える時間を与えることが⼤切です。
・社会性
学習⽀援の中には、他者とのやりとりや協働活動も含まれます。こうした経験を通して、社
会の中での関わり⽅を⾃然に学んでいきます。
おわりに
療育における学習⽀援は、「勉強を教える」ことを超えた意味を持ちます。それは、⼦ども
の内側にある「学びたい」「できるようになりたい」という気持ちを育てるための⽀援です。
そして、そのためには個々の認知特性を理解し、視覚優位・聴覚優位といった感覚の違いに
寄り添うことが不可⽋です。
⽬の前の⼦ども⼀⼈ひとりが、⾃分らしく学び、⾃分らしく⽣きるために、私たち⽀援者が
できることはたくさんあります。学習⽀援を通して、その可能性を共に育てていきましょう。
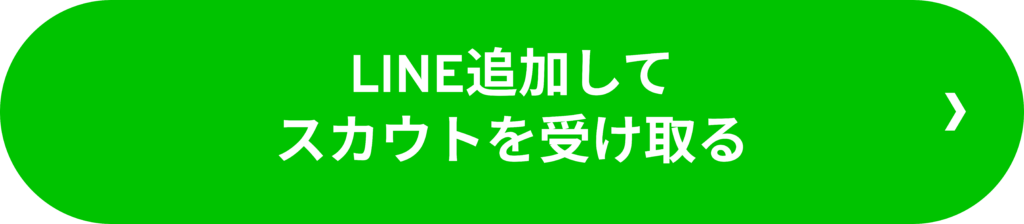
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。