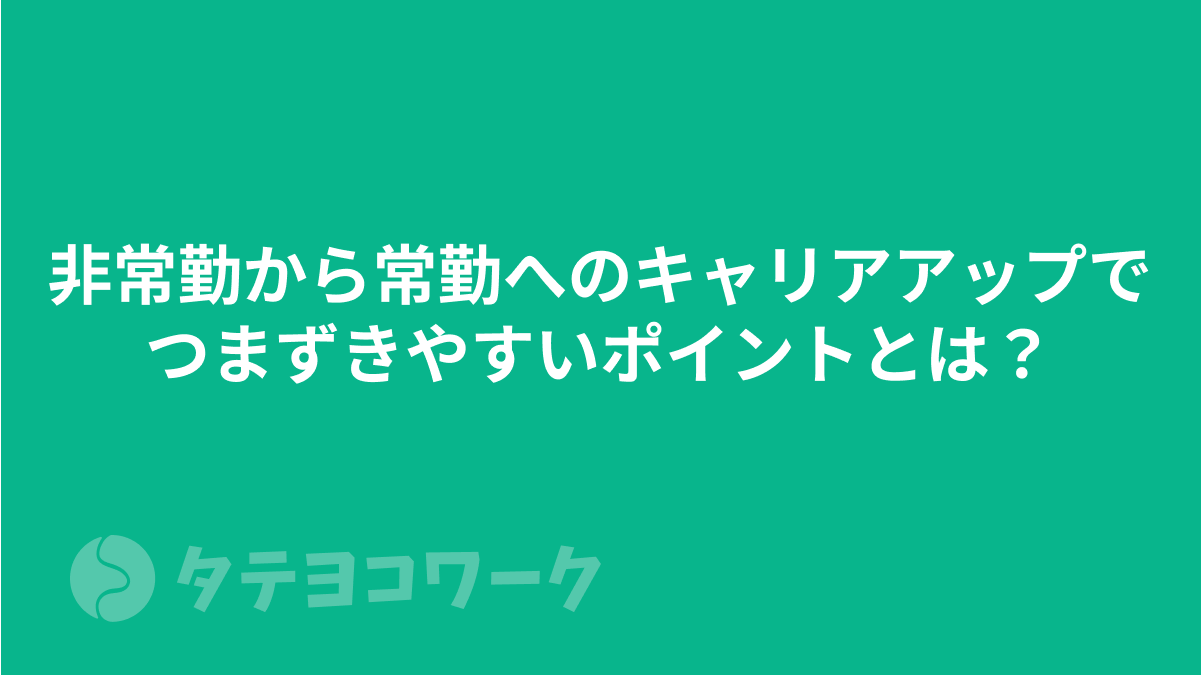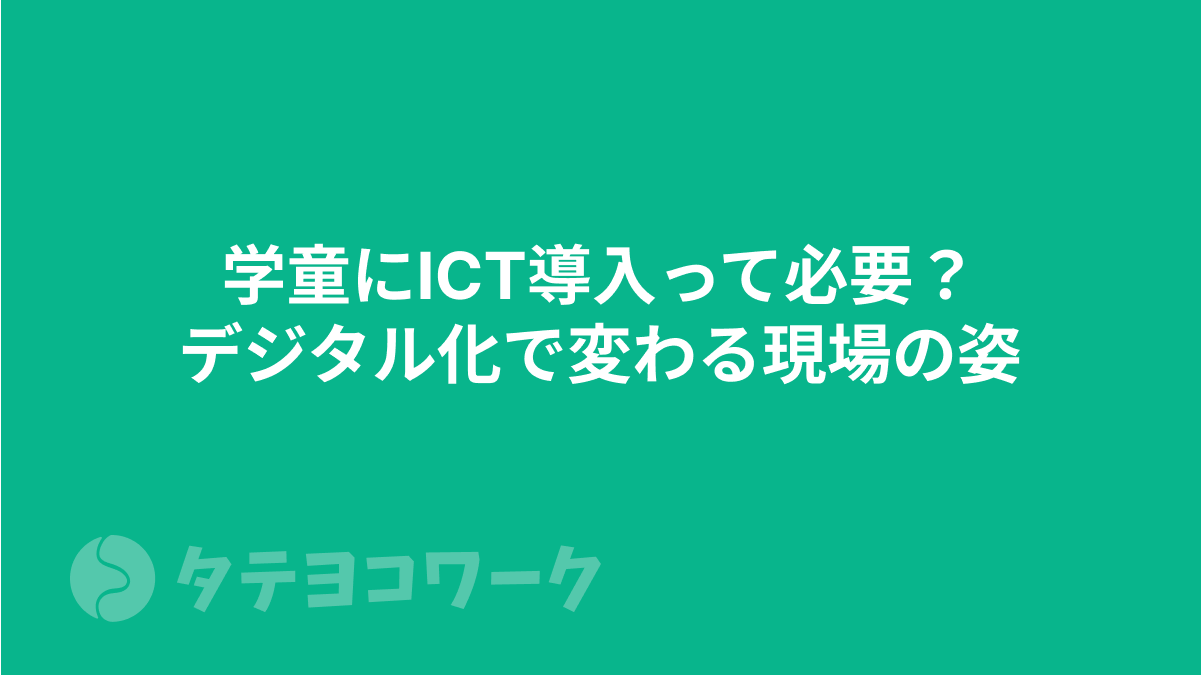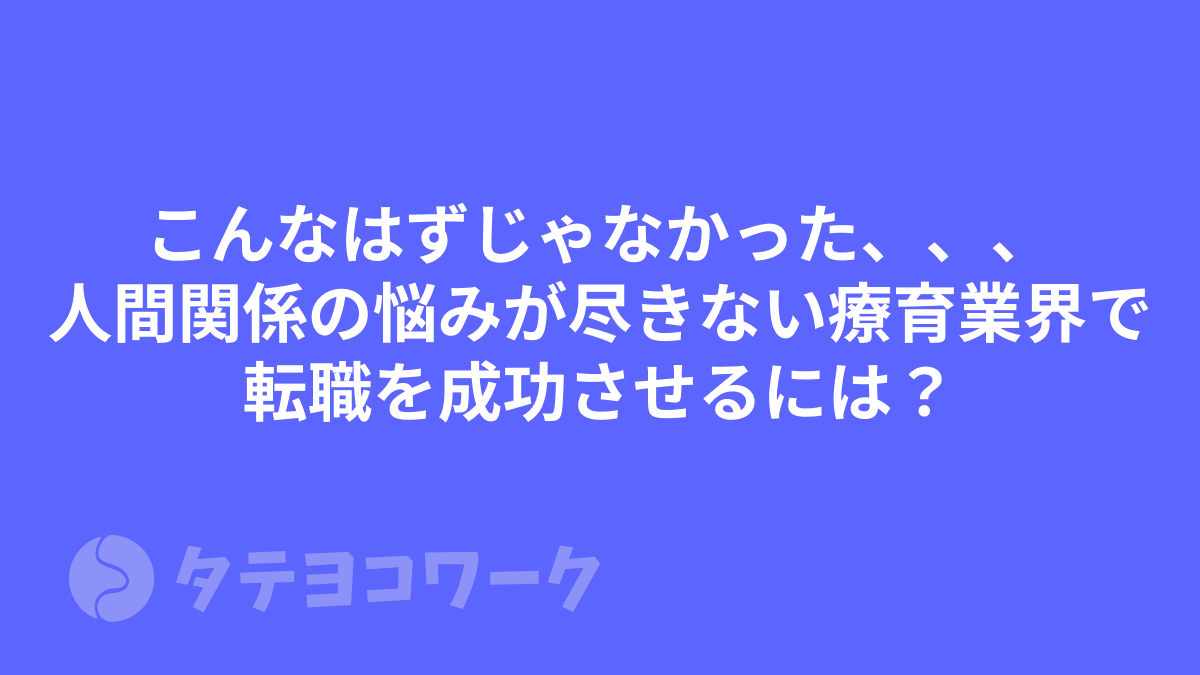タグで絞り込む
キーワードから探す
【児発・放デイ】療育における5領域とは?保育との違いも解説!
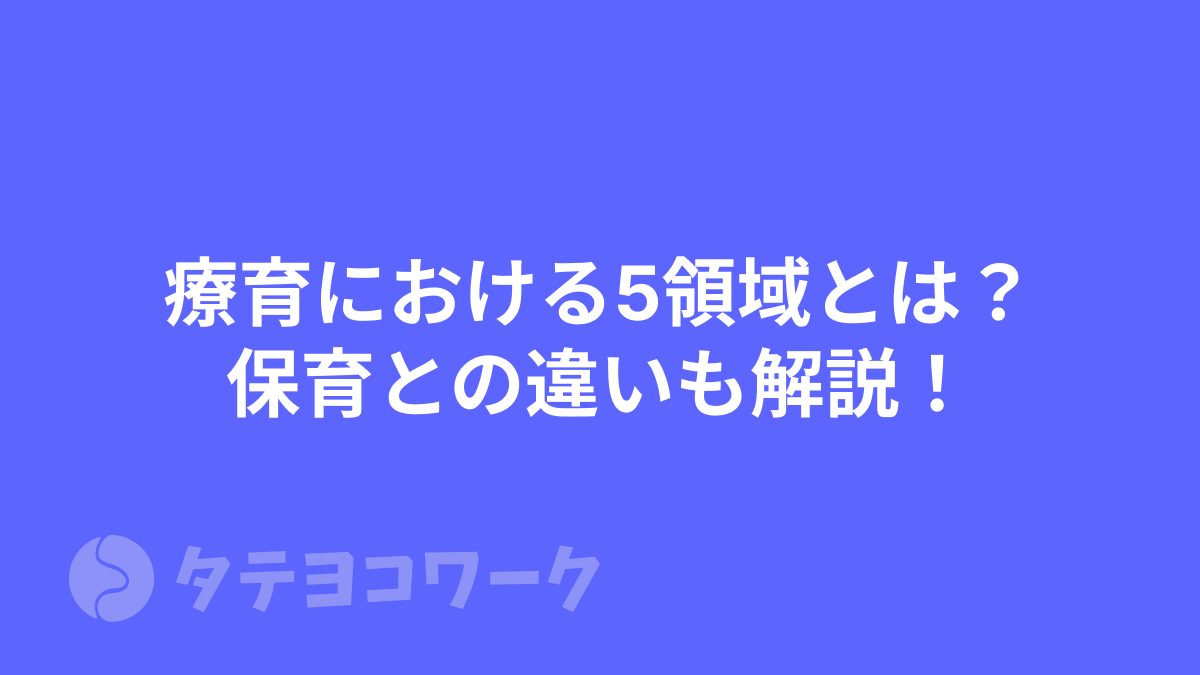
療育
ノウハウ
専門性
発達支援
児発
放デイ
1. はじめに
令和6年度(2024年度)の報酬改定により、児童発達支援施設および放課後等デイサービスにおいて、療育の5領域を網羅した支援を行うことが必要とされました。
療育の「5領域」とは、子どもの発達支援を行う上で重要な5つの側面を示したもので、児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)の現場で広く活用されています。
具体的には「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つです。
この5領域は、子どもが社会の中で安心して生きていくために必要な力を育む基盤とされており、それぞれが独立しているわけではなく、互いに影響し合いながら発達していくのが特徴です。
※療育は保育とは支援の目的やアプローチが異なりますので注意しましょう。保育との違いについては詳しく後述していますので、ぜひ最後までご一読ください!
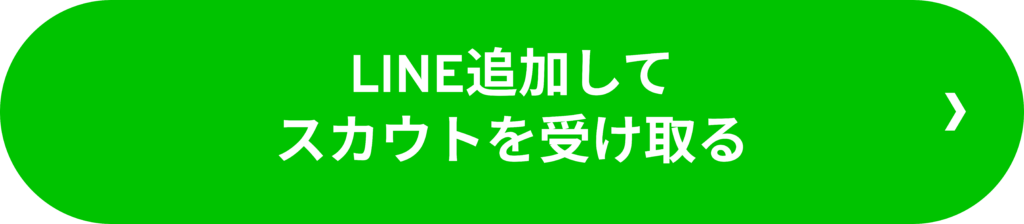
2. 療育における「5領域」を詳しく解説
2-1. 【領域1】健康・生活
この領域は、療育の最初のステップともいえるもので、子どもが「安心して自分らしく生活できる」ことを目指します。基本的な生活習慣が整うことで、他の領域での学びや集団参加もスムーズになり、子どもの自立や自己肯定感の向上にもつながっていきます。
<ねらい>
- 健康状態の維持・改善
- 生活のリズムや生活習慣の形成
- 基本的生活スキルの獲得
<支援内容>
①健康状態の把握
健康な心と身体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出すことを支援します。また、検温などによる健康状態の常なるチェックと必要な対応を行います。その際、意思表示が困難である子どもの特性等にも配慮し、小さなサインから心身の異変に気づけるよう、きめ細かな観察を行います。
②健康の増進
睡眠、食事、排泄等の基本的な生活のリズムを身に付けられるよう支援します。また、健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めるとともに、食育なども取り入れながら楽しく食事ができるよう、口腔内機能・感覚等に配慮しながら、咀嚼・嚥下、姿勢保持、自助具等に関する支援を行います。さらに、病気の予防や安全への配慮も重要です。
③リハビリテーションの実施
日常生活や社会生活を営めるよう、それぞれの子どもに適した身体的、精神的、社会的訓練を行います。
④基本的生活スキルの獲得
身の回りを清潔にし、食事、衣類の着脱、排泄等の生活に必要な基本的技能を獲得できるよう支援します。
例えば、着替えに苦手意識がある場合には視覚的な手順カードを使ってスモールステップで練習したりといった支援方法が考えられます。
⑤構造化により生活環境を整える
生活の中で、さまざまな遊びを通して学習できるよう環境を整えます。また、障害の特性に配慮し、時間や空間を本人に分かりやすく構造化します。
また、生活リズムの乱れがある場合は、家庭と連携しながら起床・就寝時間の調整も含めて支援を行うことがあります。
<支援例>
食育(一緒に料理をする、おやつ作りの過程を見せるなど)
トイレトレーニング
視覚化を意識した指示方法
2-2. 【領域2】運動・感覚
「運動・感覚」の領域では、身体の基本的な動きや感覚の調整を通じて、子どもがより自由に・安全に身体を使えるようになることを目指します。
<ねらい>
- 姿勢と運動・動作の向上
- 姿勢と運動・動作の補助的手段の活用
- 保有する感覚の総合的な活用
<支援内容>
①姿勢と運動・動作の基本的技能の向上
日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化を図ります。
②姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用
姿勢の保持や各種の運動・動作が困難な場合、姿勢保持装置など、様々な補助用具等の補助的手段を活用してこれらができるよう支援します。
③身体の移動能力の向上
自力での身体移動や歩行、歩行器や車いすによる移動など、日常生活に必要な移動能力の向上のための支援を行います。
④保有する感覚の活用
保有する視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分に活用できるよう、遊び等を通して支援します。
⑤感覚の補助及び代行手段の活用
保有する感覚器官を用いて状況を把握しやすくするよう眼鏡や補聴器等の各種の補助機器を活用できるよう支援します。
⑥感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)への対応
感覚や認知の特性(感覚の過敏や鈍麻)を踏まえ、感覚の偏りに対する環境調整等の支援を行します。例えば、子どもによっては感覚の過敏さ(音や光に極端に反応する)や鈍感さ(痛みに気づきにくい)が見られることがあります。このような感覚の偏りに対して、「感覚統合あそび」などを通して、脳と身体がうまく連携できるような働きかけを行います。
<支援例>
トランポリン、体操、ダンス、スポーツ
視覚や聴覚、触覚を刺激するようなゲームやクイズ
感覚過敏な子に配慮した環境整備
2-3. 【領域3】認知・行動
「認知・行動」の領域では、注意の持続、記憶力、順序理解、課題の遂行など認知機能や行動調整の力を段階的に育て、自律させます。子どもの特性に応じて段階的・個別的に行い、小さな「できた!」を積み重ねながら、自己肯定感や成功体験を得られるよう工夫していきましょう。
<ねらい>
- 認知の発達と行動の習得
- 空間・時間、数等の概念形成の習得
- 対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得
<支援内容>
①感覚や認知の活用
視覚、聴覚、触覚等の感覚を十分活用して、必要な情報を収集して認知機能の発達を促す支援を行います。
②知覚から行動への認知過程の発達
環境から情報を取得し、そこから必要なメッセージを選択し、行動につなげるという一連の認知過程の発達を支援します。
たとえば、文字や絵でこちらの意図を伝えることで理解しやすくする支援が挙げられます。
③認知や行動の手掛かりとなる概念の形成
物の機能や属性、形、色、音が変化する様子、空間・時間等の概念の形成を図ることによって、それを認知や行動の手掛かりとして活用できるよう支援します。
④数量、大小、色等の習得
数量、形の大きさ、重さ、色の違い等の習得のための支援を行います。
⑤認知の偏りへの対応
認知の特性を踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるよう支援し、認知の偏り等の個々の特性に配慮する。また、こだわりや偏食等に対する支援を行います。
認知行動療法なども参考にしてみましょう。
⑥行動障害への予防及び対応
感覚や認知の偏り、コミュニケーションの困難性から生ずる行動障害の予防、及び適切行動への対応の支援を行います。
他害行為や自傷行為、強いこだわり等に対する支援がこれに当てはまるでしょう。
<支援例>
立体物を使った創作活動(ブロックなど)
五感を刺激する活動(音楽、ダンスなど)
ビジョントレーニング(ナンバータッチゲームなど)
2-4. 【領域4】言語・コミュニケーション
療育においては、単に話す力だけでなく、「聞く」「理解する」「表現する」「やり取りする」といった、コミュニケーションの土台全体をサポートしていきます。
たとえば、ことばがゆっくりな子どもに対しては語彙の習得や発音の練習を通じて言語発達を促したり、自分の気持ちを整理して伝えることが難しいお子さんに対しては、カードや絵本、ロールプレイを使って、楽しくやり取りの練習を重ねていきます。
<ねらい>
- 言語の形成と活用
- 言語の受容及び表出
- コミュニケーションの基礎的能力の向上
- コミュニケーション手段の選択と活用空間・時間、数等の概念形成の習得
<支援内容>
①言語の形成と活用
具体的な事物や体験と言葉の意味を結びつける等により、体系的な言語の習得、自発的な発声を促す支援を行います。
②受容言語と表出言語の支援
話し言葉や各種の文字・記号等を用いて、相手の意図を理解したり、自分の考えを伝えたりするなど、言語を受容し表出する支援を行います。
③人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得
個々に配慮された場面における人との相互作用を通して、共同注意の獲得等を含めたコミュニケーション能力の向上のための支援を行います。
④指差し、身振り、サイン等の活用
指差し、身振り、サイン等を用いて、環境の理解と意思の伝達ができるよう支援します。
⑤読み書き能力の向上のための支援
発達障害の子どもなど、障害の特性に応じた読み書き能力の向上のための支援を行います。
学校の進度と合わせるなどの連携が重要となります。
⑥コミュニケーション機器の活用
各種の文字・記号、絵カード、機器等のコミュニケーション手段を適切に選択、活用し、環境の理解と意思の伝達が円滑にできるよう支援します。
⑦手話、点字、音声、文字等のコミュニケーション手段の活用
手話、点字、音声、文字、触覚、平易な表現等による多様なコミュニケーション手段を活用し、環境の理解と意思の伝達ができるよう支援します。
<支援例>
言葉ゲーム(伝言ゲームや早口言葉など)
ロールプレイング(日常生活に基づくもの)
発表会(自分の考えや好きなことをプレゼンテーションする)
2-5. 【領域5】人間関係・社会性
発達特性のある子どもは、相手の気持ちを読み取ったり、自分の感情を適切に表現したりすることに難しさを抱えている場合があります。そのため、療育では「どう感じているか」「どうしたらいいか」といった場面を、ロールプレイや絵カード、絵本、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などを活用して、視覚的・体験的に学んでいきます。
<ねらい>
- 他者との関わり(人間関係)の形成
- 自己の理解と行動の調整
- 仲間づくりと集団への参加
<支援内容>
①アタッチメント(愛着行動)の形成
人との関係を意識し、身近な人と親密な関係を築き、その信頼関係を基盤として、周囲の人と安定した関係を形成するための支援を行います。
②模倣行動の支援
遊び等を通じて人の動きを模倣することにより、社会性や対人関係の芽生えを支援します。
③感覚運動遊びから象徴遊びへの支援
感覚機能を使った遊びや運動機能を働かせる遊びから、見立て遊びやつもり遊び、ごっこ遊び等の象徴遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援します。
④一人遊びから協同遊びへの支援
周囲に子どもがいても無関心である一人遊びの状態から並行遊びを行い、大人が介入して行う連合的な遊び、役割分担したりルールを守って遊ぶ協同遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援します。
⑤自己の理解とコントロールのための支援
大人を介在して自分のできること、できないことなど、自分の行動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整ができるように支援します。
⑥集団への参加への支援
集団に参加するための手順やルールを理解し、遊びや集団活動に参加できるよう支援します。
<支援例>
ロールプレイや職業体験(店員になりきる等)などを通してなり切ってみる
イベントやゲームなどを実施し、集団活動への参加・経験を促していく
4. 療育と保育の共通点や違いは?混同されがちなポイントを整理
4-1. 「子どもの育ちを支える」という共通点
まず大前提として、療育も保育も「子どもの成長・発達を支えること」が目的です。どちらも子どもたちの「できること」を伸ばし、将来社会の中で自立して生活できるようにサポートするという点では共通しています。
しかし、療育と保育では「支援の内容」と「アプローチ方法」に違いがあります。
4-2. 支援内容のアプローチの違い
療育は、発達に遅れや偏り、特性がある子どもたちを対象に、その子一人ひとりに合わせた支援を行います。たとえば、言葉の発達がゆっくりな子には言語の訓練、集団行動が苦手な子には社会性を育む練習など、発達段階や課題に応じた個別支援が中心です。
一方で、保育園は主に保護者の就労支援を目的とした福祉サービスで、障害の有無に関係なく、すべての子どもが対象です。基本的には健康な子どもが日常的に通い、食事・遊び・昼寝・着替えなどの生活全般を通じて、集団の中で社会性や基本的生活習慣を育んでいきます。
保育では、一人ひとりの特性に応じた個別支援は行われますが、専門職による発達支援のような体系的な支援は、療育と比較すると限定的です。
4-3. 両者を併用するケースも増えている
最近では、保育園に通いながら、週に1~2回は児童発達支援(療育)を利用するお子さんも多く見られます。このように、保育と療育を併用することで、日常の集団生活と、個別の発達支援の両方をバランスよく取り入れることが可能になります。
4-4. 親としてどう選ぶべきか?
子どもの特性や支援の必要度によって、どちらを選ぶべきかは変わってきます。迷ったときは、専門機関(市区町村の子育て支援課や療育センター)に相談してみましょう。また、療育施設では見学や体験利用を行っているところも多くありますので、実際に足を運んで、雰囲気や支援の内容を確認するのもおすすめです。
6. 【まとめ】療育5領域を知って、子どもの可能性を広げよう
療育の5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)は、発達に課題を抱える子どもたちの成長を多角的に支えるための重要な視点です。それぞれの領域を意識することで、子ども一人ひとりに合った支援が可能になります。ご家庭や支援者がこの枠組みを理解して関わることで、子どもの持つ可能性が大きく広がっていきます。まずは、5領域を知ることから始めてみましょう。
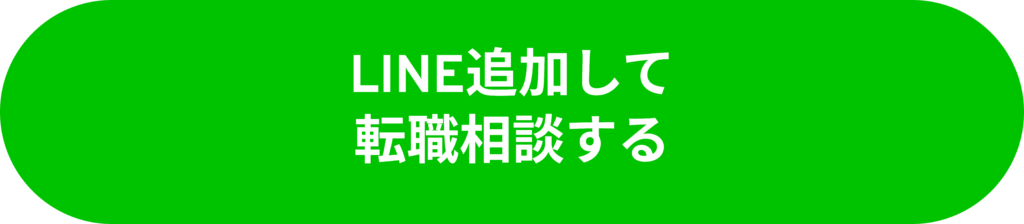
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。