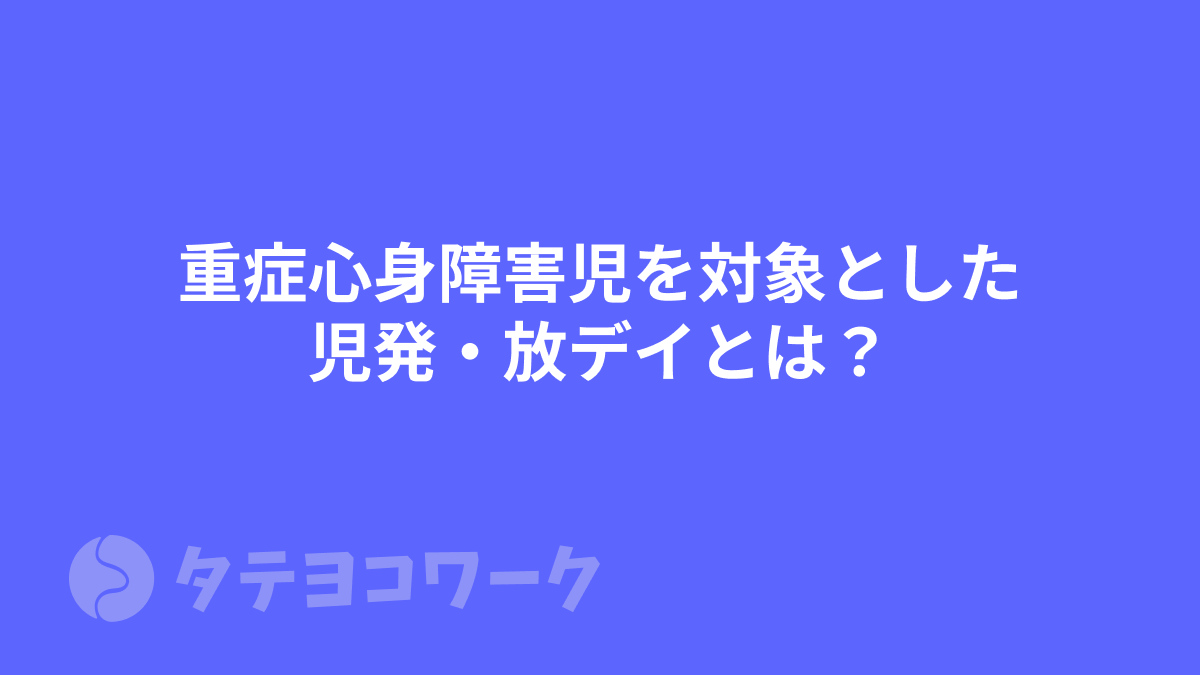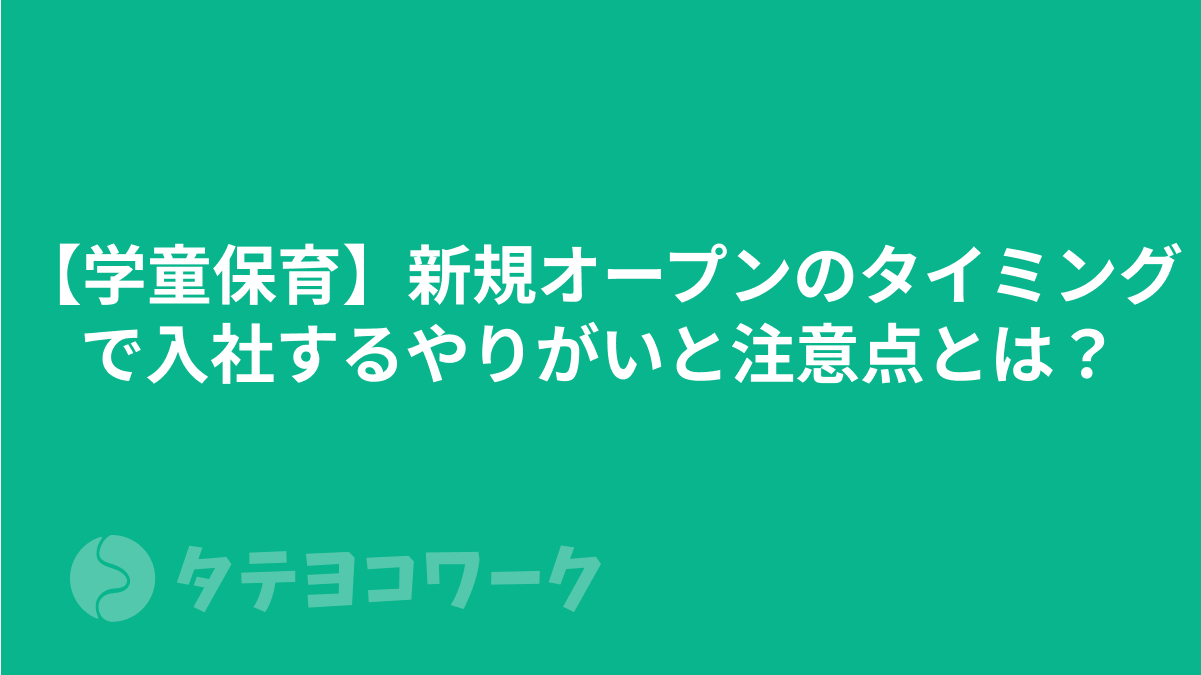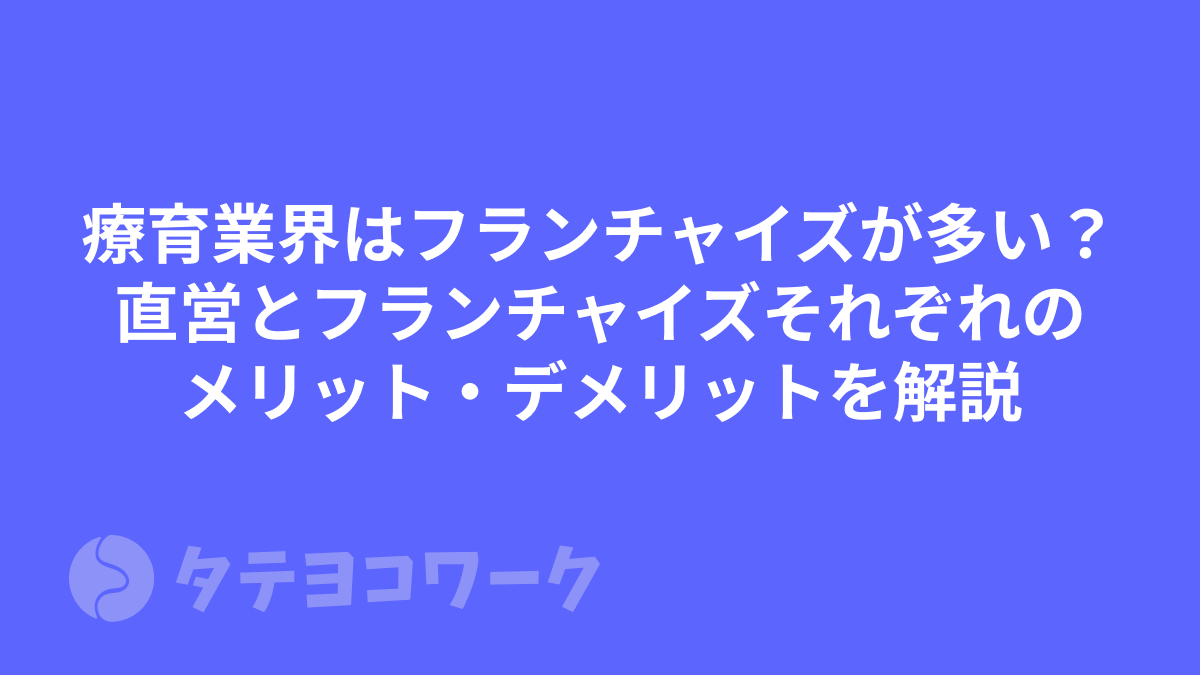タグで絞り込む
キーワードから探す
学童指導員も知っておきたい「アンガーマネジメント」とは?

学童
ノウハウ
心理学
公立学童
専門性
民間学童
学童保育所の現場では、日々たくさんのこどもたちが一緒に生活をしています。そうなれば、こども同士での喧嘩やトラブル、なかなかこどもたちに指導員側の声が届かないもどかしさ、保護者とのすれ違い、同僚との連携の難しさ──それらの問題は必ず起きるといって良いでしょう。学童保育所で働く指導員にとって、避けて通ることができない課題ともいえます。
そうした課題にぶつかったとき、特に扱いが難しく悩みの原因となるのが「怒り」の感情ではないでしょうか?
「どうしてこんなにイライラしちゃうんだろう?」
「あんなに声を荒げて怒りたかったわけじゃないのに…」
このような自己嫌悪に陥る方も多いはず。
怒りを感じてしまうこと自体は、決して悪いことではありません。むしろ、それはごく自然な人間の感情の一つです。この怒りの感情とどう付き合っていくか、つまり「アンガーマネジメント」のスキルが、こどもたちと関わる大人として非常に大切です。
本コラムでは、学童指導員として知っておきたいアンガーマネジメントの基本的な考え方と、実践的なスキルをご紹介します。怒りのメカニズムを理解し、こどもたちにも自分にも丁寧に向き合える方法を一緒に考えていきましょう!
学童保育所における怒りの場面
学童保育所の現場では、日常生活のなかに怒りの種がたくさん転がっています。特に、忙しい時間帯や、予期せぬトラブルが続いたときなどは、感情のコントロールが難しくなる場面が増えていきます。
近年、学童保育所を利用する家庭が増加していることで、狭い施設内に大人数のこどもたちが過ごしている場合もあり、より心身ともに余裕のない環境が生まれているという意見もあります。
例えば学童保育所ではこんなときに、怒りを感じるのではないでしょうか──
・何度注意してもこどもたちが同じ問題行動や危険な行動を繰り返す。
・こどもたちが遊びからの切り替えがうまくできず、集団行動やスケジュールが乱れる。
・忙しい時に何度も「先生!あのね!聞いて!」と声をかけられ続けて仕事が進まない。
・保護者から一方的なクレーム(苦情)を受けたり、「先生はうちの子をちゃんと見てくれていない」と責められたりする。
・他スタッフとの連携がうまくいかず、業務負担に不公平さを感じる。
このような怒りを抱く出来事の積み重ねによって、いつの間にか相手へ強い負の感情を抱くようになったり、自分のことを嫌いになってしまう自責の感情が生まれてしまったり、突然怒りが爆発する引き金になってしまったりします。
冒頭にも述べたとおり、怒りの感情を抱くこと自体は全く悪いことではないのですが、学童保育所の指導員というこどもたちに関わる立場上、怒鳴りつけたり、特定の子に強く当たってしまったり、故意もしくは無意識のうちに不機嫌な態度をとってしまったりすることの教育的悪影響は非常に大きいです。
怒りの感情は自然に湧き上がってくるものですが、しっかりとトレーニングをすることでコントロールできるようになります。そのためにはまず、怒りについて理解をしていくことが重要です。
怒りってそもそも何?
怒りは、人間にとって必要な感情のひとつです。誰かに無視をされたとき、不当な扱いを受けたとき、努力が報われなかったとき──そんなときに、私たちは怒りを感じます。それは「自分の大切なものが傷つけられるかもしれない」と感じたときに起こる自己防衛反応の一種で、誰もが抱く可能性がある自然な感情です。
しかし、怒りは非常にパワーが強く攻撃力が高い感情でもあるので、感情に任せてそのまま怒りを相手にぶつけてしまうと、自分も相手も傷ついてしまう場合が多いです。
実は、怒りの感情の奥には、さまざまな「本音」が隠れています。心理学では、怒りは「2番目の感情=二次感情」とも呼ばれ、その前に「本当の感情=一次感情」があるとされています。
例えばこどもに何度注意してもふざけてばかりいるときに、「もう、いい加減にして!」と怒ってしまうことがあるかもしれません。怒りの感情がわかりやすく表面に出てきますが、その裏には、
・先生としてちゃんと関われていないのかな?という「不安」
・うまく声かけできない自分への「情けなさ」
・危険なことをして怪我をすることへの「心配」
などの感情が隠れている場合があります。
このように怒りの裏には、多くの場合「不安」「悲しみ」「孤独」「焦り」「無力感」「悔しさ」などの感情があります。「私はなんで今怒りを感じたのかな?」と一歩立ち止まり、自分の心の声に耳を傾け、本当の気持ち(一次感情)は何だったのかを考えること。それが怒りと上手に付き合う第一歩なのです。
アンガーマネジメントの基本技術
アンガーマネジメントとは、「怒りの感情に振り回されず、適切に対処するための心理トレーニング」です。もともとはビジネスや家庭、学校現場などさまざまな領域で活用されてきましたが、こどもたちと日々向き合う学童保育の現場においても、非常に有効な技術として注目されています。
「アンガーマネジメントを勉強したけどイライラする!」や「6秒数えたって全然怒りの感情消えない!」といった声を耳にすることがありますが、アンガーマネジメントは、「怒らないように我慢する技術」ではありません。「怒りの仕組みを理解し、適切に伝えたり受け流したりするための考え方と行動の技術」です。今回は3つの柱を中心に、アンガーマネジメントの基本的な考え方をご紹介します。
1. 自分ルールを理解しよう
怒りの裏には、「〜であるべき」という価値観が隠されていることが多いです。これを「べき思考」といいます。学童保育所の指導員あるあるな「べき思考」としては、
・こどもは大人の言うことをきくべき
・友達同士や指導員同士は常に協力すべき
・保護者は指導員に感謝をするべき
などが挙げられます。
上記のような「べき」が裏切られたとき、私たちは「どうしてこんなこともやってくれないの?!」と怒りを感じますが、これらは実は自身の「べき思考」から作られた独自の「自分ルール」であり、全人類共通のルールではありません。
もちろん、社会で共に生きている者同士、ある程度のルールを共有したり他者に期待したりすることも必要です。しかし、あまりにも自分の「べき思考」や「自分ルール」が強くなりすぎると、現実とのギャップに苦しむことになります。自分の価値観やこだわりを無理に変える必要はありませんが、自身を苦しめてしまうような厳し過ぎる「自分ルール」は少し緩めることも大切です。
まずはイラっとした瞬間に「今、私の”べき思考”や”自分ルール”が反応しているのかもしれない」と気づくこと。そこから、少しだけ期待のハードルを下げたり、相手の立場を考えてみたりすることで、怒りの感情が緩和されることがあります。
2. 怒りのコントロール
怒りのピークはおよそ6秒間といわれています。この最初の6秒をどう乗り切るかが、怒りによる衝動的な言動を防ぐ大きなポイントです。怒りのピークの6秒間を乗り切る方法は、以下のようなものが挙げられます。
・心の中でゆっくり6秒数える。
・深呼吸をする。
・今の怒りレベルを10点満点で自己採点してみる(例:「今のイライラは6点くらいかな」など)。
・好きな人やモノのことを思い浮かべる。
最初はうまくできなくても、習慣にすることで徐々に効果を感じられるようになります。それでも怒りが収まらない場合は、「その場から物理的に離れる」という選択も検討してみましょう。
もちろん、保育現場では簡単にその場を離れることはできませんよね。特に怒りの対象が子どもの場合、子どもを残して離れることにためらいを感じることもあるでしょう。しかし、怒りの感情に任せて暴力的な言葉や態度をとってしまうくらいなら、短時間でも距離をとることは悪い選択ではありません。
たとえば「先生も少し冷静になりたいから、5分だけ離れるね」とこどもに伝えてから、同僚に声をかけて見守りを交代してもらうとよいでしょう。
このとき大切なのは、必ず冷静になったあとに子どもと向き合って話すことです。怒りの感情から逃げたままだと表面上は落ち着いたように見えても、心にモヤモヤが残ったり、こどもが「先生に見放された」と感じてしまったりすることがあるからです。
なお、ここでいう6秒とは、怒りの生理的反応のピーク時間を指しています。つまり、心拍数や血圧の上昇、筋肉の緊張といった身体の反応が最も高まるのがこの6秒間ということです。この間は冷静な判断が難しく、暴言や暴力といった衝動的な行動が出やすいため、まずこの時間をやり過ごす工夫(アンガーマネジメント)が重要とされているのです。
ただし、6秒を乗り越えたからといって、怒りの感情そのものがすぐに消えるわけではありません。身体の興奮はおさまっても、心の中にはモヤモヤや不満が残っていることもあります。
そこで次に必要なのが、「怒りを適切に伝える」ことです。では、どうすれば相手を傷つけずに、自分の怒りを伝えることができるのでしょうか。次に、その具体的な方法をご紹介します。
3. 伝え方の工夫
怒りの感情に無理やり蓋をしたり、そのまま放置しおいたりすると、あるとき一気に爆発してしまいます。怒りを適切に処理するためには相手への「伝え方」が非常に重要です。
その際に有効な方法の一つが、「YOU(ユー)メッセージからI(アイ)メッセージに変えること」です。「YOU=あなた」を主語にした言い方から、「I=私」を主語にした言い方に変えることで、柔らかく相手へ気持ちを伝えられるようになるのです。
例)
・YOUメッセージ →「あなたはなんで静かにできないの?」
・Iメッセージ →「私は、静かにしてくれたら嬉しいな」
「あなたが悪い」というようなYOUメッセージだと「自分が責められている」と感じて反発されやすくなりますが、「私はこう思っている」というIメッセージで伝えることで冷静に受け止めてもらいやすくなります。
またIメッセージで伝えるときは「二次感情の怒り」ではなく「一次感情の本音」を言うことを意識することをオススメします。「私は今イライラしてるんだよね!」というよりも「私は⚪︎⚪︎と言われたのが悲しくて嫌だったんだ」と伝えた方が分かりやすいですよね。自分の本音を考える練習にもなりますので、是非実践してみてください。
こどもの怒りに寄り添うには
大人が怒りのコントロールに悩むように、こどもたちもまた、自分の感情をうまく言葉にできずに怒りを爆発させてしまうことがあります。突然大きな声で泣き叫んだり、物を投げたり暴力をふるったり、暴言を吐いたりするこどもの姿に、どう対応すべきか迷うことはありませんか?
しかし、そうした行動の多くは「助けて」のサインです。
しばしば、こどもたちは怒りという形でしか気持ちを表現できないことがあります。私たちができるのは、その奥にある「本当の気持ち」に耳を傾けることです。よく観察をして前後の状況も把握した上で、
具体的な関わり方の案としては、
・「嫌だったんだね」「悔しかったんだね」と共感したり代弁したりする。
・気持ちを視覚化するツール(気持ちカード、怒りの温度計)を使う。
・怒りたくなったらどうしたらよいか、行動を一緒に考える(ぬいぐるみをぎゅっと抱きしめる、6秒数えるなど、反射的な動きを決めておくと良いです)。
・絵本や物語を使って「感情を言葉にする力」を育てる。
といったことが考えられます。
また、こどもたちは大人の姿を見て感情の扱い方を学びますので、指導員自身が怒りに振り回されず、丁寧に向き合う姿を見せることこそが、最良の教育といえるかもしれません。
おわりに
学童保育の現場は、予測不可能な動きをするこどもたちが集まり、言葉と感情のやりとりが絶えない場所。だからこそ、私たち指導員が感情と上手に向き合う力を身につけることは、こどもたちにとっても自分自身にとっても非常に大きな意味を持ちます。
こどもたちの成長を考えたり忙しさに追われたりする中で、つい自分の気持ちを後回しにしていることもあると思いますが、自分の心が疲れていることに気づかないまま頑張り続けると心に余裕がなくなり怒りのコントロールは難しくなります。自分自身を労ったり大切にしたりすることも忘れずに、こどもたちと日々向き合っていっていけると良いでしょう。
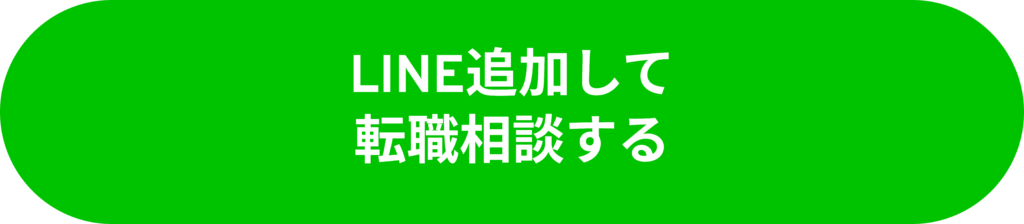
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。