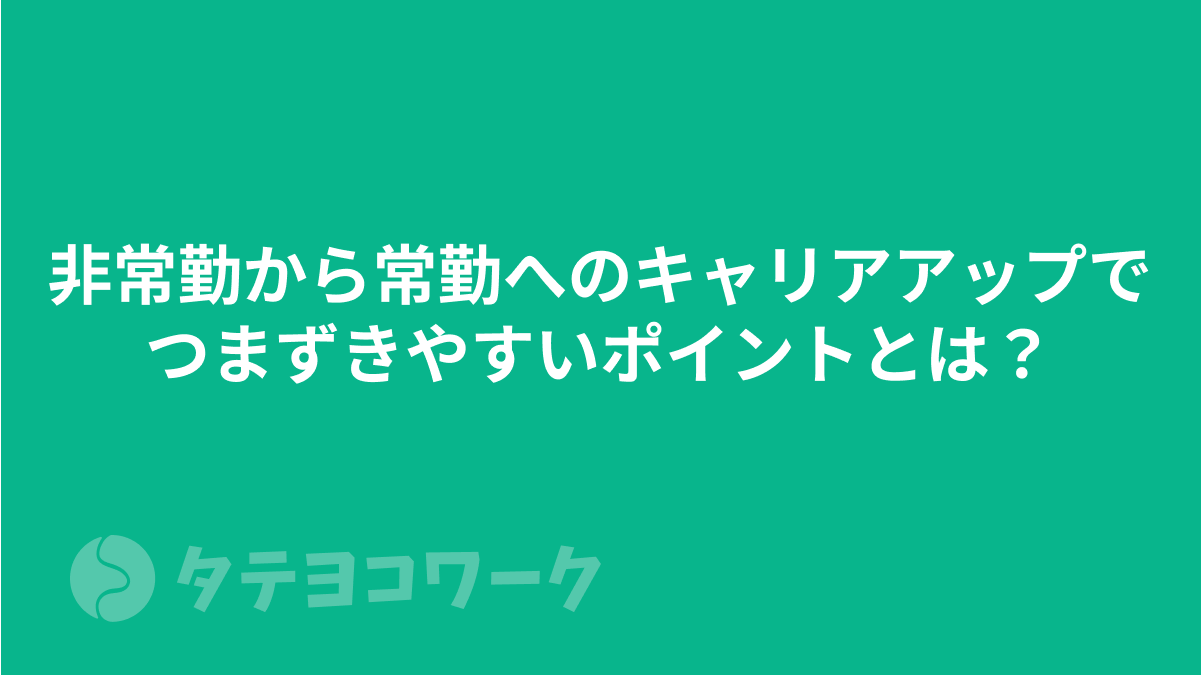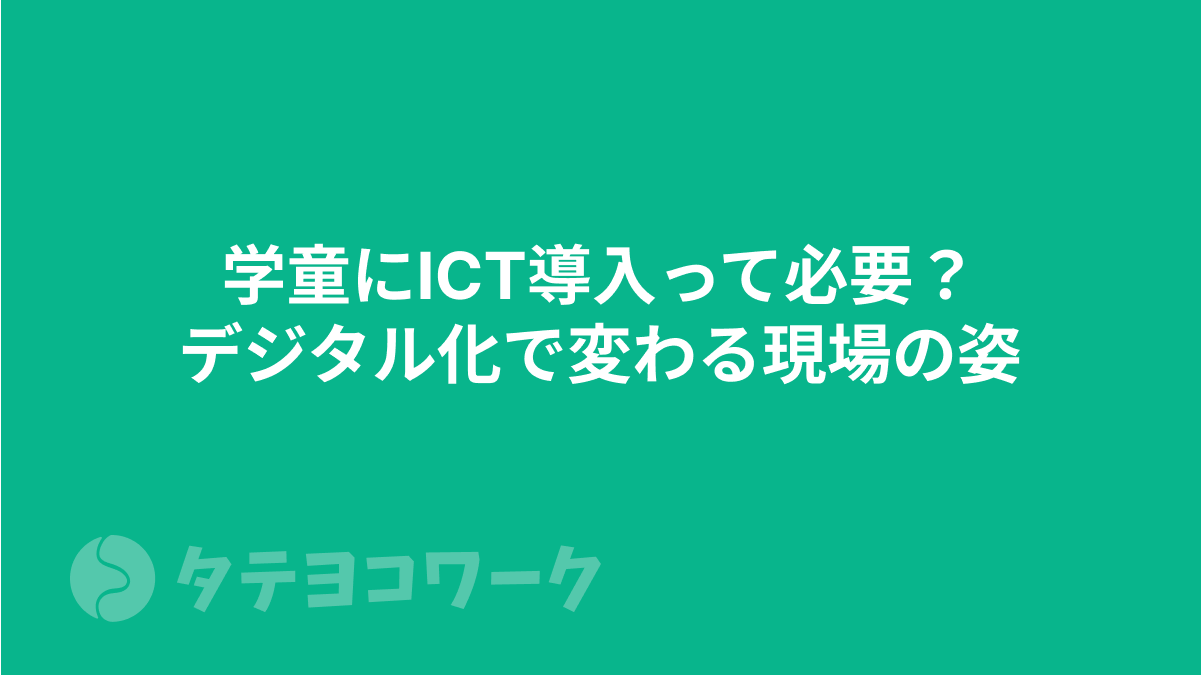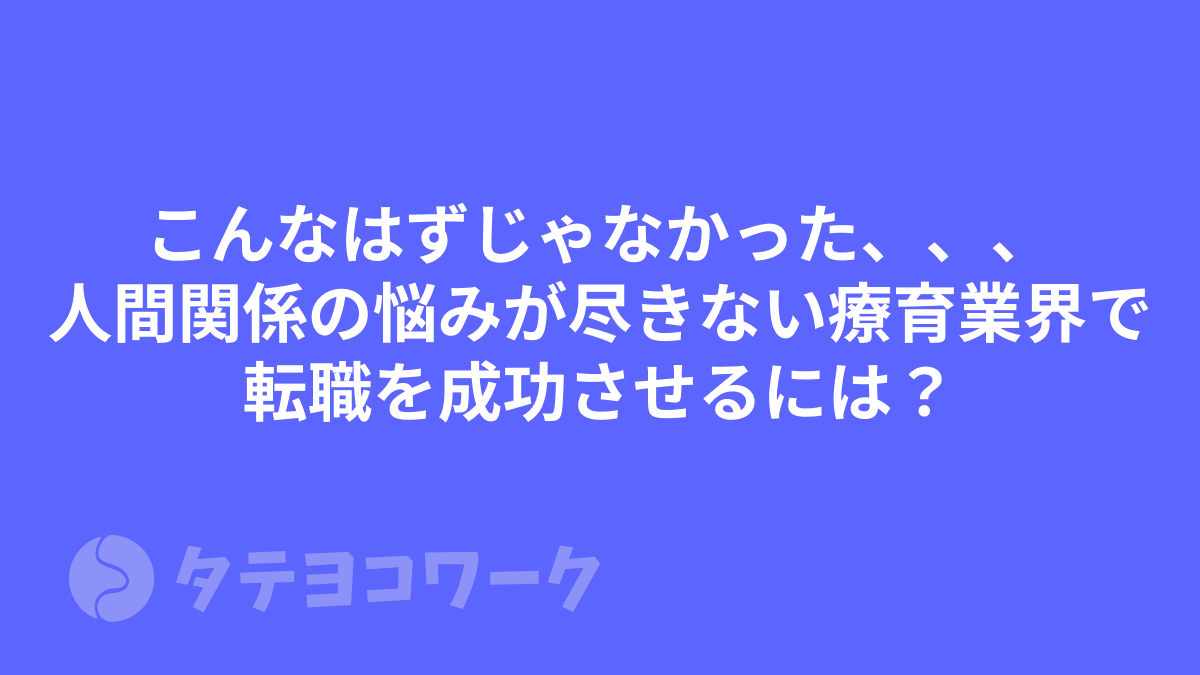タグで絞り込む
キーワードから探す
療育現場でよく聞く「加算」ってなに?目的や要件を解説
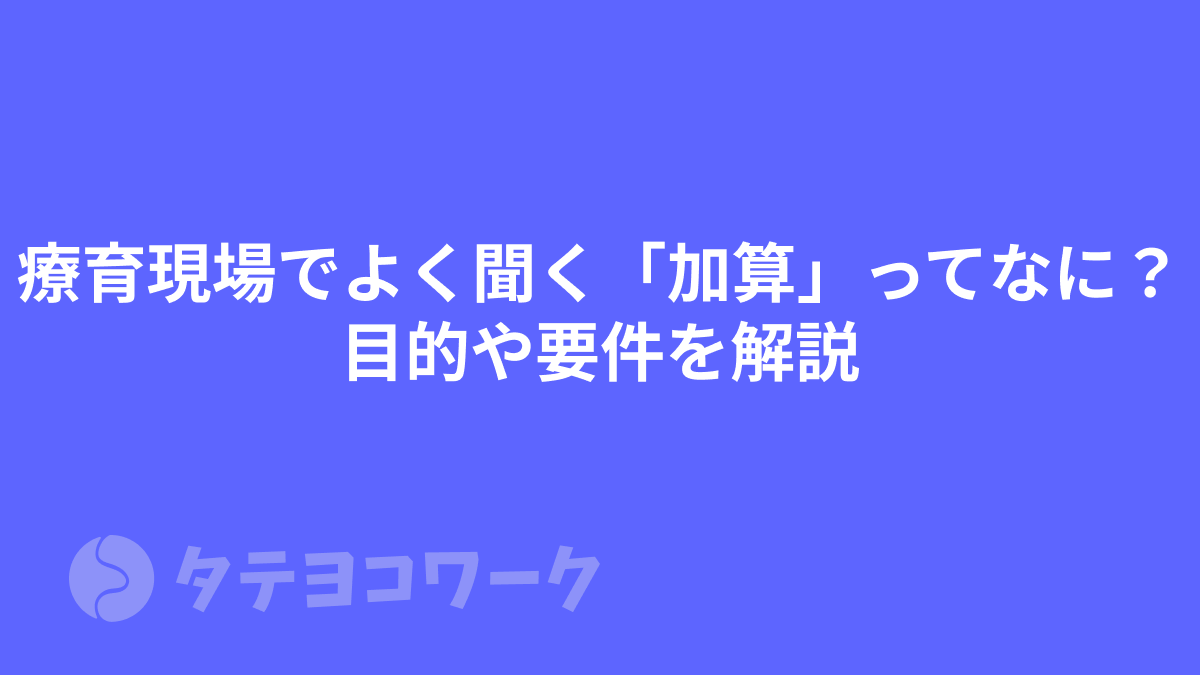
療育
児発
放デイ
療育の現場でよく耳にする「加算」という言葉。なんとなく聞いたことはあっても、詳しい意味がわからず戸惑った経験はありませんか?加算とは、一定の条件を満たすことで基本報酬に上乗せされる制度で、支援の質を高めるために設けられています。
現場で働く人にとっては運営や評価に直結する重要な要素であり、療育を受ける子どもやその家族にとっても、手厚い支援を受ける指標の一つになります。本記事では、わかりにくく複雑で要件の細かい加算の代表的な種類、算定要件、現場への影響までをわかりやすく解説します。

1. 療育現場での主な加算とは?
療育現場では、より質の高い支援を提供するためにさまざまな「加算」が設けられています。たとえば【児童指導員等加配加算】は、基準より多くの職員を配置することで、手厚い支援体制を整えている施設に適用されます。また【専門的支援体制加算】は、言語聴覚士や作業療法士などの専門職が在籍し、継続的な支援体制が整っていることが条件です。【専門的支援実施加算】は、実際にその専門職が個別に支援を行った場合に加算されます。これらはすべて、支援の質を高めることを目的とした重要な仕組みです。
今回はこの3つの加算【児童指導員等加配加算】【専門的支援体制加算】【専門的支援実施加算】について掘り下げて解説していきます。
2. 児童指導員等加配加算とは?
児童指導員等加配加算とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの療育施設において、基準以上の職員を配置した場合に算定できる加算です。人員体制が手厚くなることで、子ども一人ひとりに対して丁寧な対応ができることから、質の高い療育を提供するための重要な仕組みとされています。療育現場で働くスタッフの役割や資格とも深く関わるため、就職や転職を考える上でもぜひ理解しておきたい加算です。
2-1. 児童指導員等加配加算の対象資格
「児童指導員等」とは、下記の職種を指します。
児童指導員
保育士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
手話通訳士
手話通訳者
特別支援学校免許取得者
心理担当職員(心理学修了等)
視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
2-2. 児童指導員等加配加算の算定要件
加算を算定するには、基準を超える人数の児童指導員等を配置していることが前提です。たとえば通常の配置基準よりも1人以上多く、かつ常勤換算での勤務時間が要件を満たしている必要があります。また、加配職員が直接支援に関わることが条件であり、記録や個別支援計画への反映も求められる場合があります。算定の適正化が厳しくなっているため、施設側もきちんとした体制整備と運用が必要です。
令和6年度の報酬改定で大きく変更されたことは、報酬改定前までは専門職による支援も評価されていましたが、専門職の評価は専門的支援加算により行うものとされ除外されました。
2-3. 児童指導員等加配加算の単位数
児童指導員等の配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数により単位数が変わります。
単位数が加算されることで事業所の収益にも影響があり、安定した経営とスタッフ確保につながる重要な要素となっています。最新の単位数は報酬改定を確認しましょう。
参考:こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧」 令和6年6月10日https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/db1c84db/20240611_policies_shougaijishien_shisaku_05.pdf

3. 新設された専門的支援体制加算とは?
2024年度障害福祉サービス等報酬改定において、特別支援加算と専門的支援加算は統合され、新たに専門的支援体制加算と専門的支援実施加算という加算が創設されました。
主な変更点は、
・「体制加算」と「実施加算」の2段階で評価
・実施加算は回数の上限が設定される(2回~6回)
といった部分になります。
療育施設の基準人員に加え、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など専門職を常勤換算1.0以上配置し、かつ都道府県へ届出を行うことで算定可能となります。専門職の在籍によって体制そのものを評価し、児童やその家族に必要な専門支援を提供できる施設として認められる仕組みです。
3-1. 専門的支援体制加算の対象資格
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)
児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)
心理担当職員
視覚障害児支援担当職員
3-2. 専門的支援体制加算の算定要件
加算の算定には、対象となる専門職を常勤換算で1.0以上配置し、都道府県へ届出を行う必要があります。
専門的支援体制加算の目的は、理学療法士等による支援が必要な障害児などへの専門的な支援の強化を図るためです。
3-3. 専門的支援体制加算の単位数
児童発達支援センターや児童発達支援事業所(障害児)において算定できる単位数は、それぞれの区分に応じて異なるため注意が必要です。
4. 新設された専門的支援実施加算とは?
4-1. 専門的支援実施加算の対象資格
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
保育士(※)
児童指導員(※)
心理担当職員(心理学修了等)
視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
※保育士や児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事
4-2. 専門的支援実施加算の算定要件
加算の算定には、対象となる専門職を常勤換算で1.0以上配置し、都道府県へ届出を行う必要があります。また、当該職員は児童や家族の支援に継続的に関与し、チーム支援体制の一員として機能していることが求められます。配置しているだけでなく、実際の支援体制として機能していることが重要です。
4-3. 専門的支援実施加算の単位数
児童発達支援と放課後等デイサービスの単位数は同じですが、対象児の月利用日数に応じた限度回数が異なります。
5. その他の加算
放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧
子育てサポート加算
家族支援加算
個別サポート加算
送迎加算
専門的支援体制・実施加算
関係機関連携加算
医療連携体制加算
保育・教育等移行支援加算
欠席時対応加算
延長支援加算
集中的支援加算
利用者負担上限管理加算
児童指導員等加配加算
看護職員加配加算
福祉専門職員配置等加算
強度行動障害児支援加算
福祉・介護職員処遇改善加算
6. 加算が現場や家庭にもたらすメリット
療育現場における加算制度は、単に報酬を増やすための仕組みではありません。職員の配置や専門職の関与を評価することで、現場全体の支援体制を底上げし、子どもたちやそのご家族がより安心して支援を受けられる環境を整える役割を担っています。ここでは、加算がもたらす具体的なメリットについて、「支援の質」「職員の働きがい」「利用者の安心感」という3つの視点から解説します。
6-1. 支援の質の向上と丁寧なケアの実現
加算制度により、職員数の増員や専門職の配置が可能になり、1人ひとりに対してより丁寧で個別性の高い支援が行えるようになります。特に、専門的支援体制加算では、理学療法士や言語聴覚士などが在籍することで、専門的な視点からのアセスメントや支援が可能です。こうした体制が整うことで、子どもの成長や課題に対してきめ細やかに対応でき、支援の質が格段に向上します。
6-2. 職員の働きがいと専門性の評価につながる
加算が算定される事業所では、職員の配置や役割が明確化されており、専門職がその力を発揮しやすい環境が整っています。これは、職員のモチベーション向上や専門性の発揮にもつながり、キャリア形成にも良い影響を与えます。また、支援内容が記録や計画に反映されることから、目に見える形で評価されやすく、やりがいを実感できる環境になります。結果として離職率の低下にも貢献します。
6-3. 利用者・家族にとっての安心感と支援の充実
加算により支援体制が整備されることで、利用者やその家族は「しっかり見てもらえている」という安心感を得ることができます。専門職の関与や職員の手厚いサポートが受けられることで、家庭だけでは難しい課題にも対応可能となり、保護者の心理的負担も軽減されます。また、計画的・継続的な支援が提供されることで、子どもの成長を着実にサポートできる環境が整うのも大きな魅力です。
7.まとめ
療育現場でよく聞く「加算」は、支援の質を高めるために設けられた報酬制度です。2024年度の報酬改定では、「専門的支援体制加算」「専門的支援実施加算」が新設され、より実効性のある支援が評価される仕組みになりました。加算は事業所にとって収益面の安定だけでなく、職員の働きがいや専門性の向上、そして利用者や家族にとっての安心感にもつながります。求人を探す際には、加算の有無や体制をチェックすることが、安心して働ける環境を見つけるポイントとなります。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。