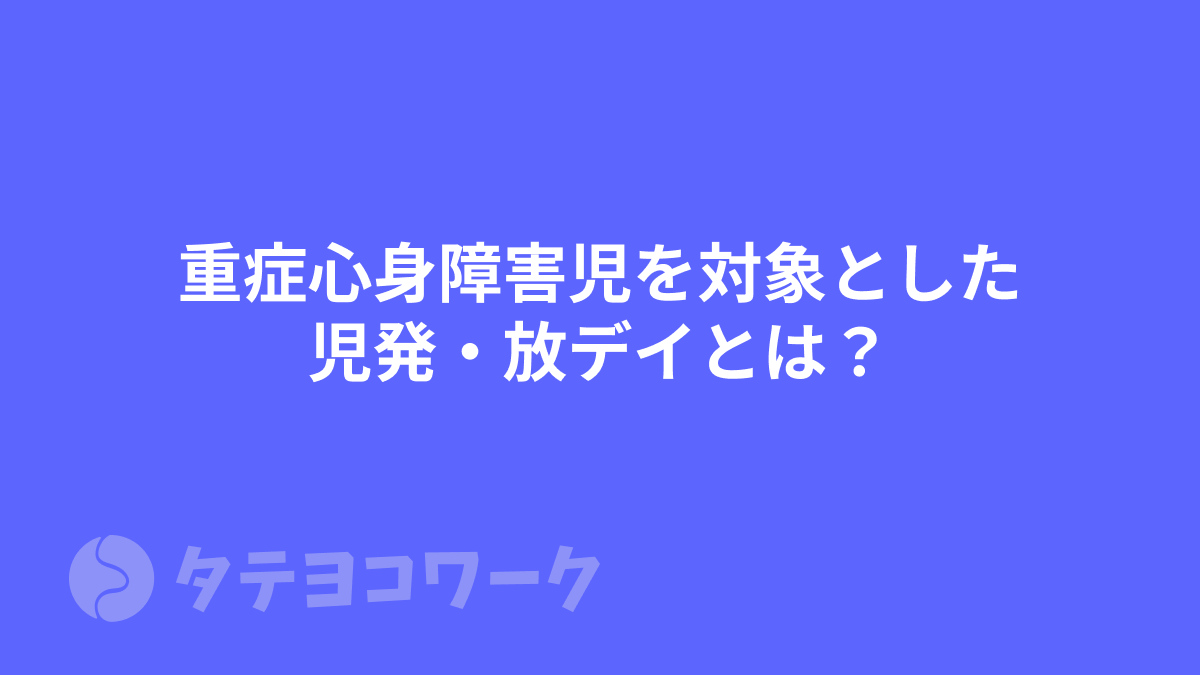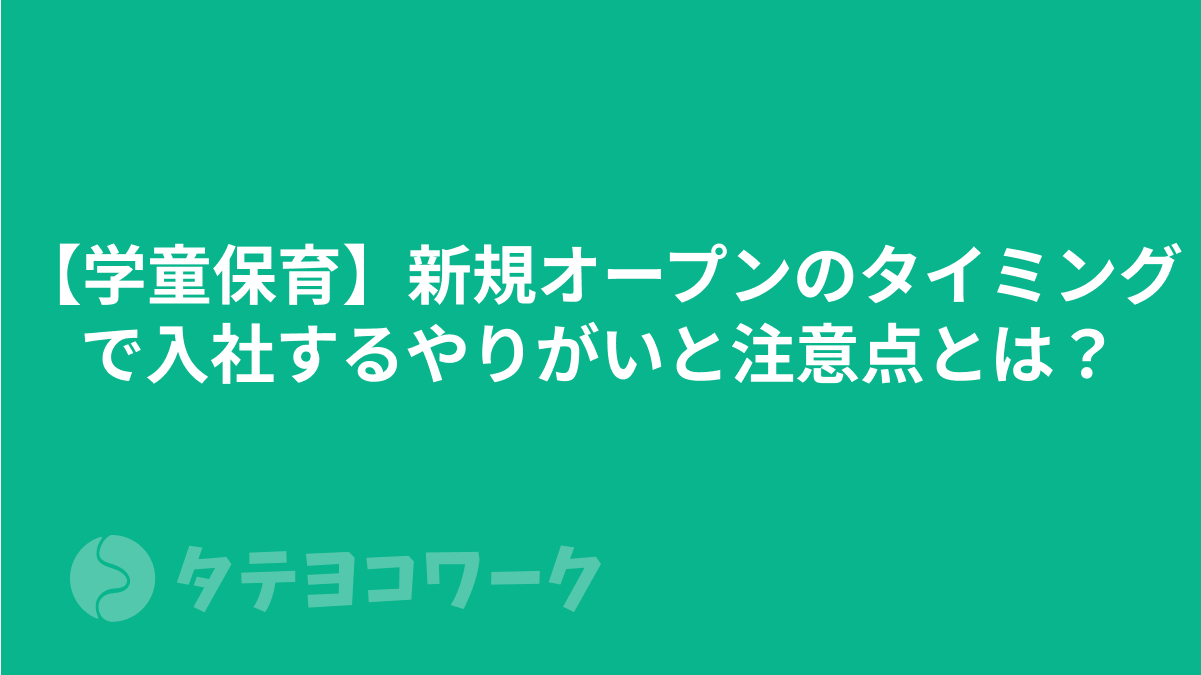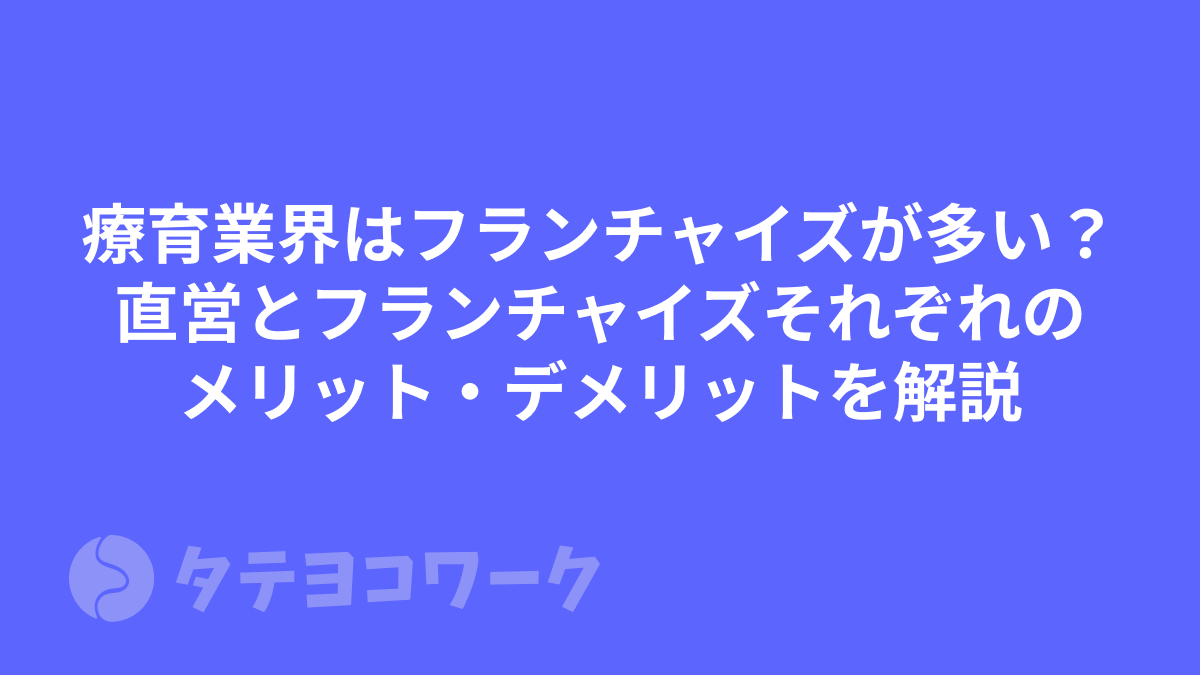タグで絞り込む
キーワードから探す
学童はどれくらい足りていない?こどもの居場所がもっと必要な理由について
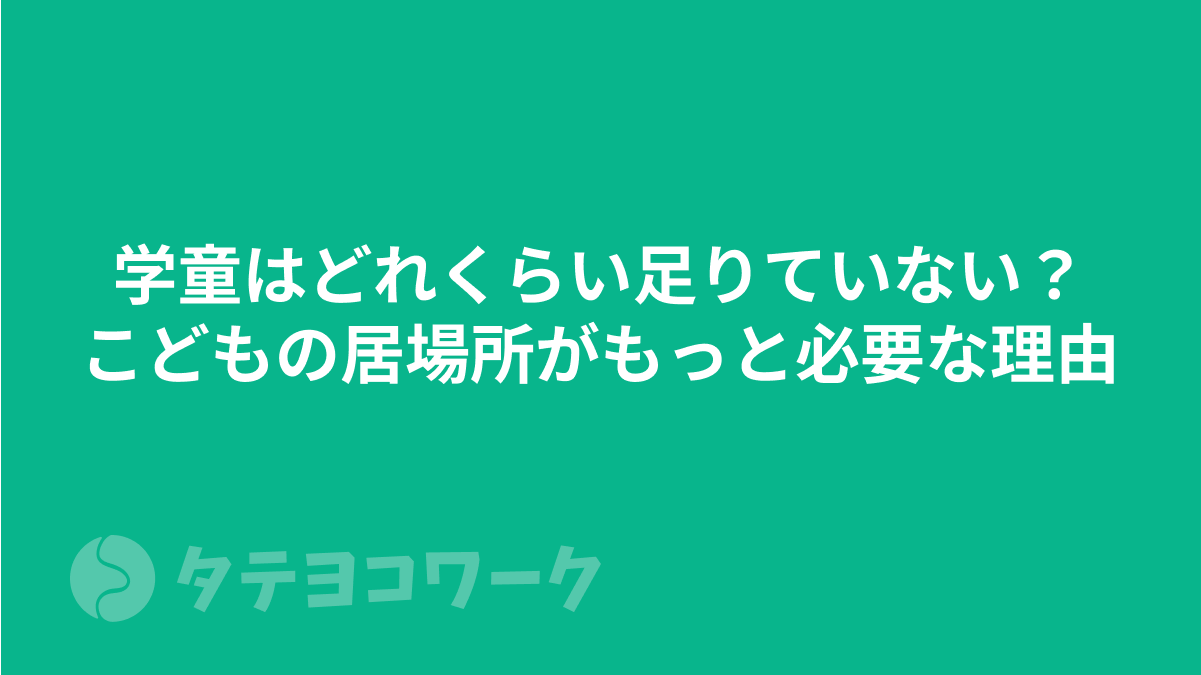
学童
公立学童
民間学童
放課後児童支援員
働き方の多様化や、家族のライフスタイルの変化にともなって、こどもたちの居場所のあり方も大きく変わりつつあります。その中でも特に注目され、需要が高まっているこどもたちの居場所の一つが学童保育所(放課後児童クラブ)です。
学校が終わった後や長期休暇中のこどもたちの居場所である学童保育所は、単なる託児施設としてだけではなく、安全・安心に遊びや学び、交流を促進する施設として重要な社会的役割を果たしています。
しかしながら学童保育所の需要が非常に高まり、注目度や期待が高まる一方で、学童保育所の施設数が不足していたり環境が十分に整っていなかったりといった課題が多くの地域で浮かび上がっています。
本コラムでは学童保育所の不足状況についてまとめながら、こどもたちの居場所が必要な理由を深掘りしていきます。

◎ 学童保育所の待機児童問題について
学童保育所は現在、待機児童問題という大きな課題に直面しています。待機児童問題とは、学童保育所を利用したくても、施設に定員以上の申し込みがあるために入りたくても入れない児童がいるという状況のことをいいます。学童保育所需要の増加に対し、学童保育所の施設数や指導員の数が追いついていないために、待機児童問題は発生しています。
こども家庭庁の統計(2024年5月1日時点)によると、全国の放課後児童クラブにおける待機児童数は1万7686人。前年よりも1410人増加しており、状況は悪化の一途をたどっています。さらに、登録児童数は151万9952人と過去最多となっています。
本来、学童保育所はこどもを安心して預けられる環境を整備するための制度ですが、施設数の不足や人材確保の難しさから、希望しても利用することができないケースが多発しているのが現状なのです。
◎待機児童問題の背景
このような待機児童問題が起きている要因としては、主に以下の点が挙げられます。
①共働き世帯の増加
現代社会では、共働き家庭の増加が顕著です。女性の社会進出や経済的な理由、キャリアの継続などを背景に、夫婦が共に働く家庭が一般的になりつつあります。これに伴い、放課後に子どもを安心して預けられる「学童保育所」への需要が年々高まっているのです。
②核家族化の進行
核家族化の進行も大きな要因と言われています。かつては祖父母や親戚と協力して子育てをする家庭も多くありましたが、現在では親とこどものみで生活する家庭が主流となりました。この変化により、育児を支える「地域の手」が不足し、親の負担は増しています。とくに共働き世帯にとっては、放課後のこどもの居場所が確保できなければ安心して働くことができないため、必然的に学童保育所の利用を希望することになるのです。
③政策の遅れと自治体間の格差
学童保育所の整備は政府にとっても重要な少子化対策の一環とされていますが、政策の実行には多くの課題が残されています。特に、予算の配分や制度設計においては地域差が大きく、自治体ごとの財政状況や行政の対応力によって、サービスの質や利用条件に大きな差が生じています。結果として、「住む場所によって受けられる支援が変わる」という不公平が生まれ、子育て世代の生活に直接的な影響を及ぼしています。
④都市部と地方における構造的課題
地域ごとの人口動態もまた、学童保育所不足の一因となっています。たとえば都市部では人口が集中する一方で、土地が限られており新たな施設を建設することが困難です。土地取得にかかるコストや建設までの期間が長期化し、急増する需要に対応しきれていないのが現状です。一方、地方では人口減少により施設の維持そのものが難しく、運営資金や人材確保といった課題が顕在化しているのです。
◎待機児童問題による影響とは?
学童保育所の待機児童問題によって、こどもたちと保護者には以下のような影響があると考えられます。
①こどもたちの安全が確保できない
第一に、放課後に保護者の適切な保護を受けられないこどもたちが、安全な場所で過ごせない可能性があります。こどもたちが安心して遊び、学び、多くの経験を積むためには、安全な居場所が絶対的に必要です。幼いこどもたちが一人きりで過ごすには多くの危険性・リスクが潜んでいることから、適切な見守り体制が整っている学童保育所は、こどもたちの安全保障の要といえるでしょう。留守番ができる年齢・発達度に達している場合はまだしも、多くの低学年のこどもたちとその保護者にとっては、学童保育所が利用できないということに大きな不安が残るのです。
②仕事と育児の両立が困難になる
次に、学童保育所が利用できないことにより、保護者が仕事と育児の両立に苦労し、キャリア形成や家庭の経済状況に影響が出る可能性があります。定時退勤や時短シフト、早上がりなどの時間調整や育休の延長など、様々な工夫をしながら勤務を続ける保護者もいますが、止むを得ず休職や退職の選択肢を迫られる家庭もあり、女性を中心にキャリアの中断・断絶が起こっています。

◎待機児童ゼロ!? 「全入制度」の落とし穴とは…
「うちの自治体は待機児童ゼロです」と言われて、安心する保護者も多いでしょう。しかし、それは「希望者全員を受け入れる=全入制度」を採用しているだけかもしれません…。
実際には、定員を超えた過剰な受け入れが行われており「部屋が狭くて過ごしづらい」や「人数が多すぎて危ない」という深刻な状況に陥っているケースが多く見られます。机と椅子が足りないため床に座って宿題や遊びをしなければならなかったり、お互いの話が聞き取れないほど騒がしかったり、スタッフ一人で20人以上のこどもを見守らなければならなかったりと、事故やトラブルが起きないのが奇跡といえるような状態の学童保育所がたくさんあるのです。
このような狭隘(きょうあい)環境は、特にHSCといわれる刺激に敏感な子や、ADHDやASdといった発達特性のある子にとっては非常にストレスフルです。「安心して過ごせる場」が、逆に「疲れる場」や「我慢する場」になってしまっては本末転倒ですよね。
また、学童保育所で働くスタッフの負担も大きくなり、子どもへの関わりが一人ひとりに届かなくなるという、質の低下も避けられません。
◎学童保育の拡充に向けた具体的な取り組みと課題
学童保育所は待機児童の数字だけでなく、「定員オーバーでぎゅうぎゅう詰めであること」や「こどもも大人も疲弊している」といった質的な問題にも目を向ける必要があり、今後の子育て支援政策の大きな柱となることは間違いありません。現在実施されている拡充に向けた取り組みとその課題について、具体的にまとめていきます。
①学童で働くスタッフの確保と育成
学童保育の質を左右する大きな要素の一つが、現場で子どもたちを支える「放課後児童支援員」というスタッフの存在です。しかし、現在は人材の確保が難しく、慢性的な人手不足に陥っている施設も少なくありません。
その背景には、スタッフの待遇の低さや不安定な雇用形態、十分な研修の機会が整っていないことなどが挙げられます。今後はスタッフの待遇改善とあわせて、専門性を高めるための研修制度の充実が不可欠といわれており、こどもたちの安全と成長を支えるプロフェッショナルとしての地位向上とキャリアパスの明確化が求められています。
②政府と自治体による取り組み
政府や地方自治体も、学童保育の整備と質の向上に向けて複数の施策を打ち出しています。たとえば「待機児童解消加速化プラン」や「放課後児童クラブ整備推進計画」などは、施設数の拡充と人的体制の強化を図るものです。一部の自治体では、学校敷地内や地域施設を活用した学童保育の設置、運営費への補助拡大など、地域の実情に応じた柔軟な支援策も進められています。ただし、政策の効果には地域差があり、実施体制のばらつきが課題として残っています。
③民間企業やNPOとの連携
公設の学童保育所だけでは追いつかなくなってきた近年、民間企業やNPOが学童保育事業に参入し、特色あるサービスを展開するケースも増えています。たとえば、放課後の時間を活用した学習支援、英語・プログラミング教室、芸術・スポーツなど、従来の保育機能に加えた付加価値のあるプログラムが注目を集めています。一方で、こうした民間サービスには収益性の課題や人材確保の難しさ、長期的な運営の持続可能性といったハードルも存在します。公共性の高い子育て支援分野において、民間と行政の役割分担をどのように調和させていくかが、今後の重要な論点となりそうです。
④地域コミュニティと保護者の協力
学童保育所の充実には、地域住民や保護者の積極的な協力も欠かせません。近隣の高齢者や地域団体による見守り活動、保護者が主体となる運営支援やボランティア活動など、地域ぐるみでこどもの育ちを支える体制づくりが各地で模索されています。また、地域に根ざした取り組みによって、こどもたちが多世代と関わる機会が生まれ、社会性や思いやりを育む教育的な効果も期待されています。行政・民間・地域が一体となり、「こどもを地域全体で育てる」意識の醸成が今、求められているのです。
おわりに
学童保育所は単なる託児施設ではなく、こどもたちが放課後を安心して過ごし、人とのつながりの中で成長していくための大切な「生活の場」あり「こどもの居場所」です。
少子化が進む今だからこそ、一人ひとりの子どもにとっての「豊かな放課後」を実現するために、私たち大人ができることはたくさんあります。行政の支援・取り組みだけでなく、地域、保護者、企業、そして社会全体でこどもの育ちを支えるインフラとしての学童保育の充実を本気で考える時が来ています。
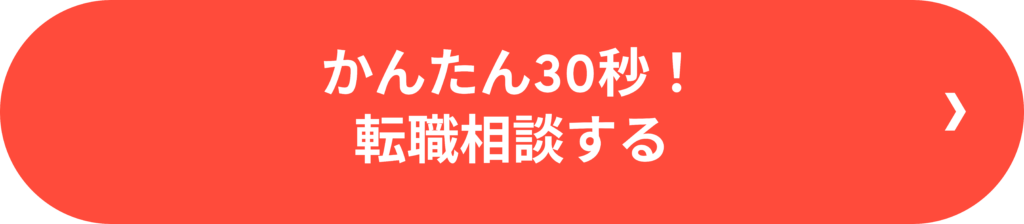
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。