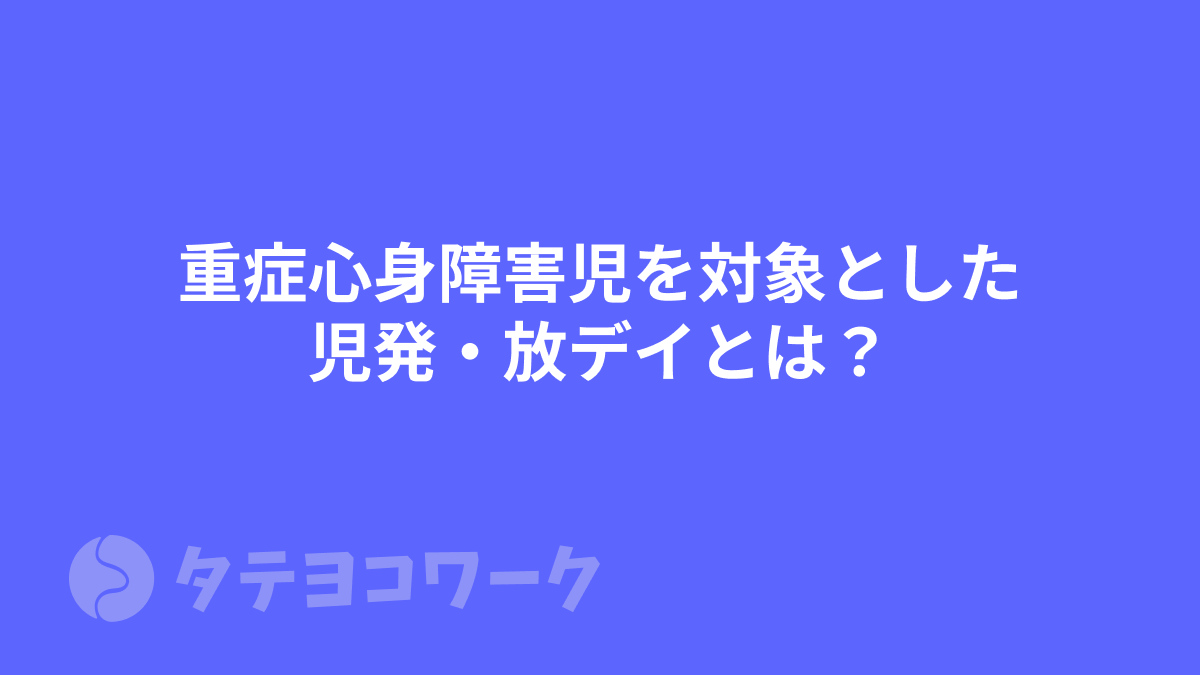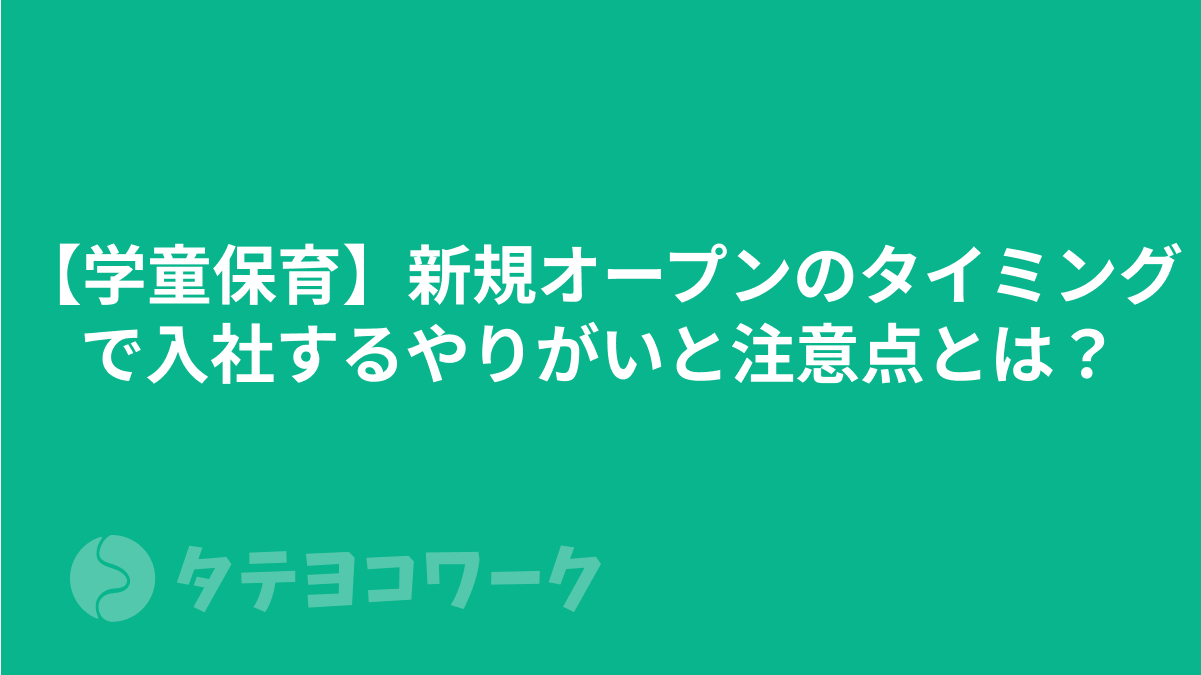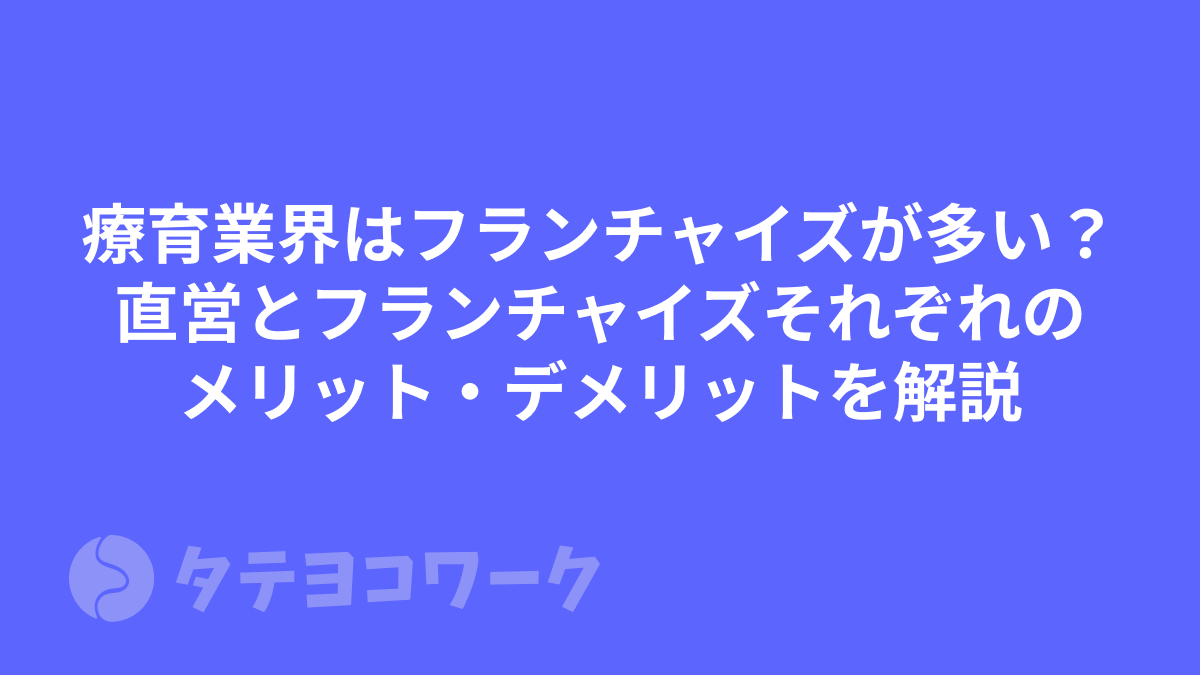タグで絞り込む
キーワードから探す
療育でよく使われるSST(ソーシャルスキルトレーニング)とは?
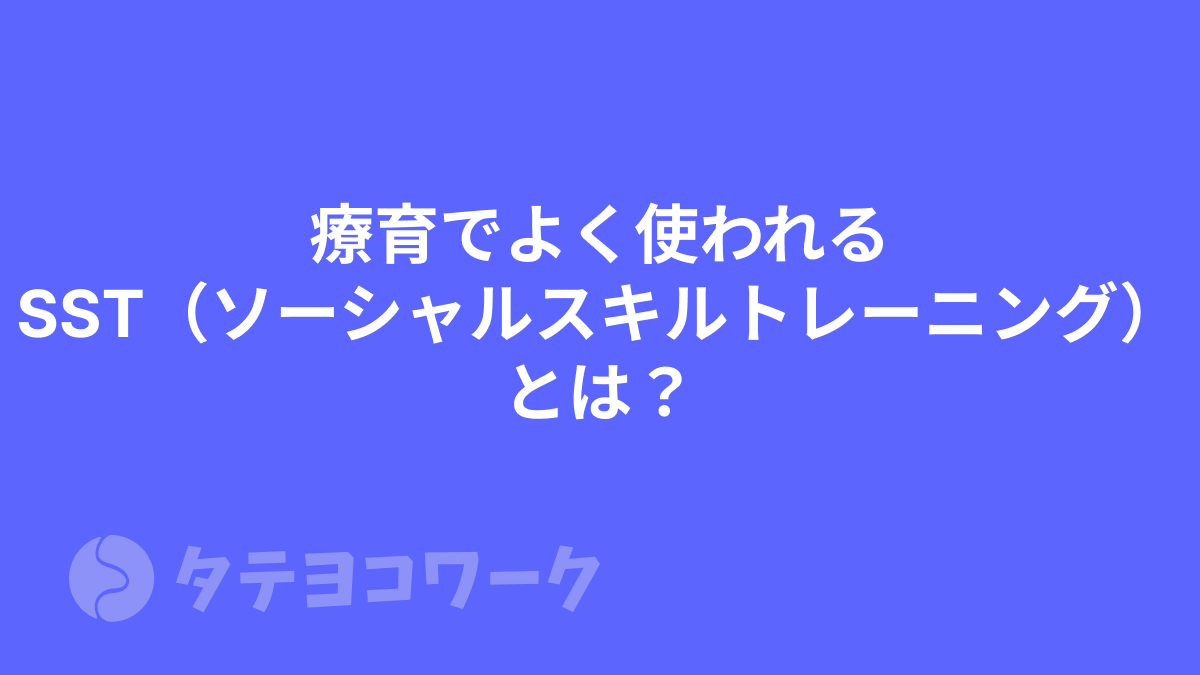
療育
ノウハウ
専門性
発達支援
児発
放デイ
はじめに:SSTとは?なぜ今注目されているのか
現代の療育現場で欠かせない支援の一つが「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」です。これは、子どもたちが集団生活や社会で円滑に過ごすために必要な「対人スキル」を学ぶためのプログラムです。
特に発達障害のある子どもたちにとっては、自己表現や他者との関わり方を身につける貴重な機会になります。学校や福祉施設でも積極的に取り入れられており、実生活に活かせる力を育てる支援法として注目されています。

SSTの目的と期待される効果
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、単に人と話す力を育てるだけでなく、子どもが社会で自立して生活していくための基礎力を養うことが目的です。自分の気持ちを伝える力や他人との適切な距離感を学ぶことで、トラブルの予防や人間関係の改善にもつながります。こうしたスキルは将来的に進学や就労を見据えた際にも重要であり、療育現場でSSTが重視される大きな理由となっています。
コミュニケーション力や対人関係のスキル向上
SSTでは、基本的なあいさつや会話のキャッチボールなど、実生活で必要なコミュニケーションスキルを身につけます。相手の気持ちを想像したり、自分の気持ちを適切に表現する練習を通じて、対人関係に自信が持てるようになります。
問題行動の予防・改善につながる
相手との関わり方がうまくいかないことが原因で起こる問題行動は、SSTで適切な対応を学ぶことで予防・改善が可能です。怒りのコントロールや断り方、順番を守るなどのルールを身につけることで、トラブルを減らし、周囲との関係もスムーズになります。
将来の自立や就労支援にもつながる重要な基礎
SSTで育てる社会的スキルは、将来の自立や職場での円滑な人間関係づくりにも役立ちます。報告・連絡・相談といったビジネススキルの基礎も含まれており、日常生活だけでなく就労支援の場でも有効に機能します。
SSTの進め方とステップ
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、ただ活動を繰り返すだけでは効果が出にくく、段階的な進め方がとても重要です。最初に子どもの特性や課題を把握するためのアセスメントを行い、適切な目標を設定します。次に、ロールプレイや教材を使った練習でスキルの習得を目指します。そして最後に、家庭や学校との連携を通じて定着を図ります。このように、評価・指導・振り返りを一貫して行うことが、SSTの成果につながります。
アセスメント(事前評価)と目標設定
SSTの第一歩は、子ども一人ひとりの発達段階や課題を把握するアセスメントです。観察や面談を通して、現時点でのコミュニケーション力や行動の傾向を明らかにします。その結果をもとに、無理なく達成できる具体的な目標を設定し、支援の方向性を定めます。
ロールプレイ・絵カード・ワークシートなどを使った練習
実際の支援では、子どもが状況をイメージしやすいよう、ロールプレイや視覚教材を用いて繰り返し練習します。絵カードやワークシートでの確認も効果的です。実際の困りごとを想定した場面で練習することで、子ども自身が「できた」という成功体験を積み重ねていけます。
振り返りと家庭・学校との連携による定着
SSTの学びを日常生活で活かすには、支援後の振り返りと継続的なフォローが欠かせません。子どもの変化を記録・共有し、家庭や学校と連携して取り組みを広げます。環境が一致することで、学んだスキルが日常の中に定着しやすくなります。
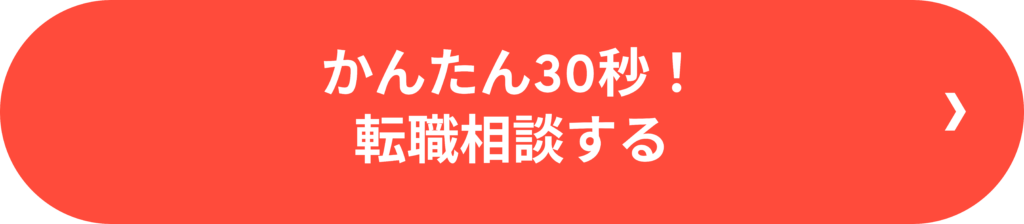
SSTに使える教材・ツール
SST(ソーシャルスキルトレーニング)を効果的に行うには、子どもが視覚的に理解しやすく、興味を持ちやすい教材やツールの活用が欠かせません。市販されている絵カードや絵本、無料で使える公的機関の資料、さらにはICT機器を活用したアプリや動画など、多彩な選択肢があります。それぞれの子どもの発達段階や支援目標に合わせて、最適な教材を選ぶことで、学びの効果を高め、楽しみながらスキルを身につけることができます。
人気の市販教材・絵カード・絵本など
SSTに役立つ市販教材には、場面ごとのやりとりを描いた絵カードや、感情や行動をテーマにした絵本などがあります。子どもが直感的に理解しやすく、繰り返し使える点が魅力です。特に「こんなときどうする?」といった選択形式の教材は、考える力も養えます。
無料で使える公的機関の資料やワークシート
厚生労働省や教育委員会、発達障害者支援センターなどが提供する資料やワークシートは、無料で活用できる優れた教材です。基本的なルールや感情理解を促す内容が多く、支援現場でもよく使われています。信頼性が高く、家庭との共有もしやすいのが特徴です。
ICT・タブレットを活用した最新教材も紹介
近年では、タブレットやスマートフォンで使えるアプリや動画教材も充実しています。視覚的に動きがあるコンテンツは、注意が散りやすい子どもにも効果的。自分のペースで学べるうえ、記録機能やゲーム感覚の練習で楽しく継続できるのもメリットです。
SSTと発達障害の関係
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、発達障害のある子どもたちにとって、社会の中でより良く生きていくための大切なサポート手段です。特にASD(自閉スペクトラム症)やADHD、知的障害などを持つ子どもたちは、対人関係や感情のコントロールに困難を抱えやすく、SSTが有効に機能するケースが多く見られます。それぞれの特性に応じた支援を行うことで、自信を育み、安心して人とかかわる力を養うことが可能です。
SSTを実施する主な場所
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、家庭や学校、福祉施設など、子どもが日常的に過ごすさまざまな場所で実施されています。それぞれの場面での役割や目的に応じて、支援の方法も異なります。また、支援に携わるスタッフの専門性や関わり方によって、SSTの効果は大きく変わります。ここでは、主な実施場所と、支援者に求められるスキルや役割について詳しく見ていきましょう。
放課後等デイサービス・児童発達支援施設
家庭では保護者が日常の中でSST的な声かけを行い、学校では特別支援学級や通級指導教室などで指導が行われます。放課後等デイサービスなどの療育施設では、個別・集団のプログラムが組まれ、専門職による支援が提供されます。環境ごとに目的や支援方法が異なるのが特徴です。
学校(特別支援学級・通常学級内の支援)
SSTを支える支援者には、子どもの発達段階や特性を理解し、適切な言葉や方法で伝えるスキルが求められます。また、子どもが安心して取り組めるよう、肯定的な関わりや共感力も重要です。無理のない進め方で、成功体験を積み重ねるサポートができることが理想です。
医療機関・カウンセリングルーム
SSTは一人の支援者だけでなく、教師・保育士・心理士・保護者など多職種が連携して進めることで効果が高まります。支援の方針や子どもの様子を共有し、一貫した関わりを持つことが大切です。家庭と連携を図ることで、子どもにとって自然で実践的な学びが広がります。
家庭でも取り入れられる簡単なSST
家庭では、挨拶やお願いの仕方、順番を待つ練習など、日常の中でSSTを自然に取り入れることが可能です。例えば、絵カードやごっこ遊びを活用したり、「今の伝え方はどうだった?」と振り返るだけでも十分な学びになります。親子の対話を通じて、社会性を育むことができます。
SSTの実施に必要な資格や職種
SST(ソーシャルスキルトレーニング)を実施するために法律で定められた必須資格はありませんので、先述のように家庭などで親が実施することも可能です。
ただ子どもたちの社会的なスキルを育むための重要な支援なので、多くの実施施設では専門性の高い職種が関わります。例えば、児童指導員や保育士、言語聴覚士など、発達支援に関する知識と経験を持つ専門職が中心となります。さらに、支援計画を統括する児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者などの役割も重要です。こうした職種について理解し、求人を探す際の参考にしましょう。
資格を活かせる現場と求人の探し方
SSTに関わる職種の求人は、放課後等デイサービスや児童発達支援施設などで多く見られます。求人情報サイトや自治体の福祉求人ページ、専門人材紹介サービスの活用が有効です。「SST」「療育」「発達支援」などのキーワードで検索すると効率的です。
まとめ:SSTを通じて子どもの未来と支援者のキャリアをつなぐ
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、子どもたちの社会性を育むだけでなく、支援者自身のキャリアにも深く関わる重要な取り組みです。子どもの成長を間近で見守りながら、その変化に寄り添える仕事には大きなやりがいがあります。また、SSTを実践できる現場は多様で、福祉職としてスキルアップや専門性を高めていくことも可能です。子どもの未来を支えながら、自身の成長も実感できる職場で新たな一歩を踏み出しませんか。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。