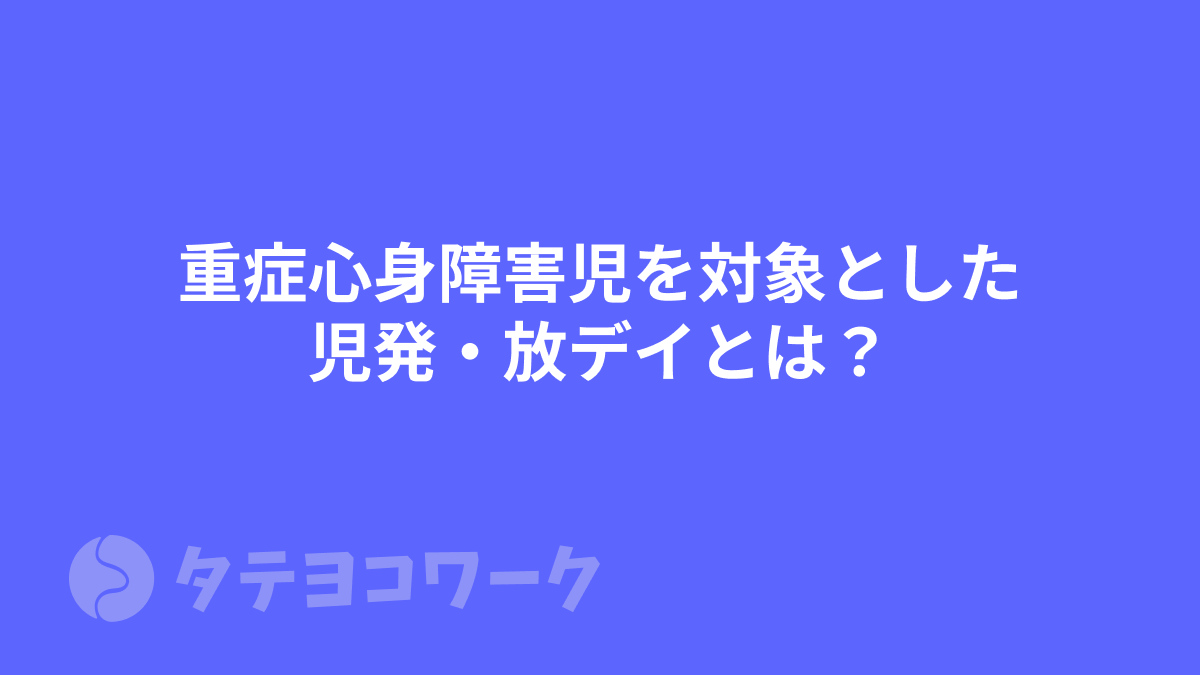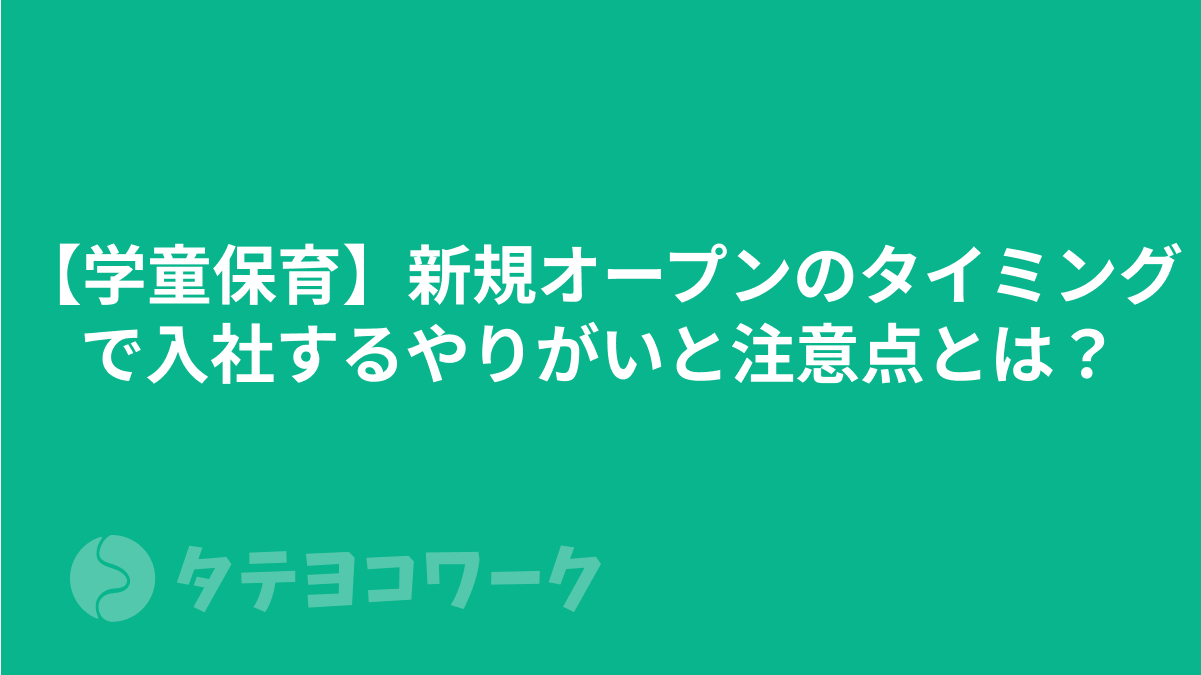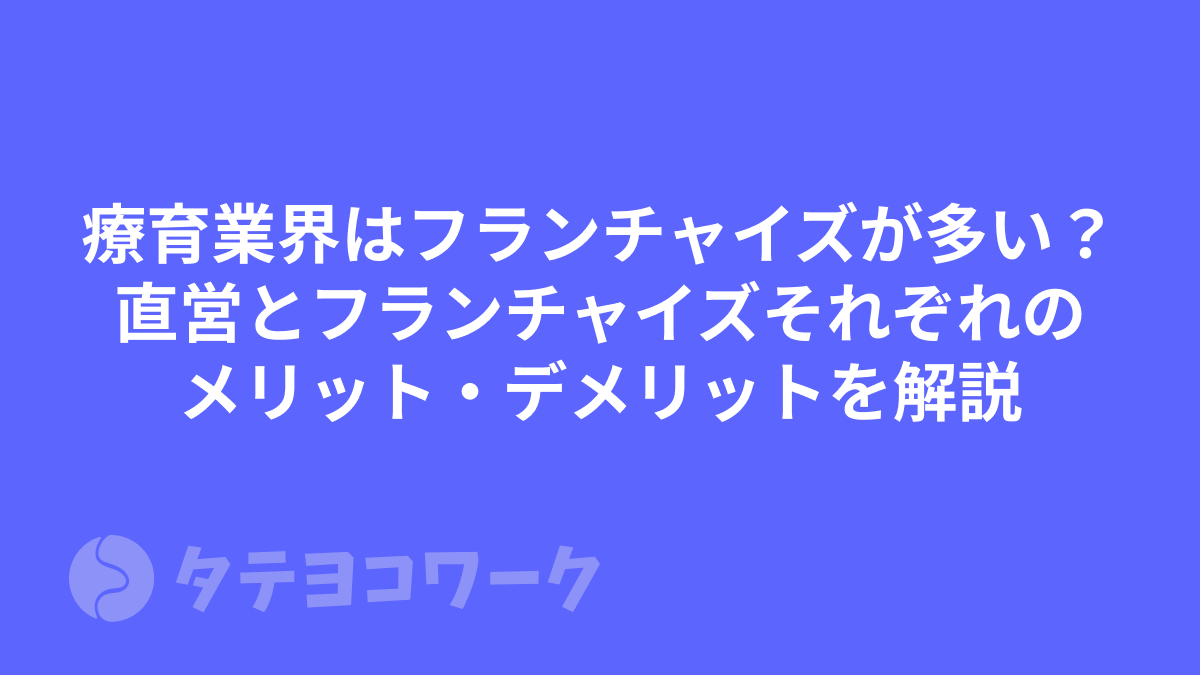タグで絞り込む
キーワードから探す
学童でキャリアアップするには?施設長やエリアマネージャーへの道
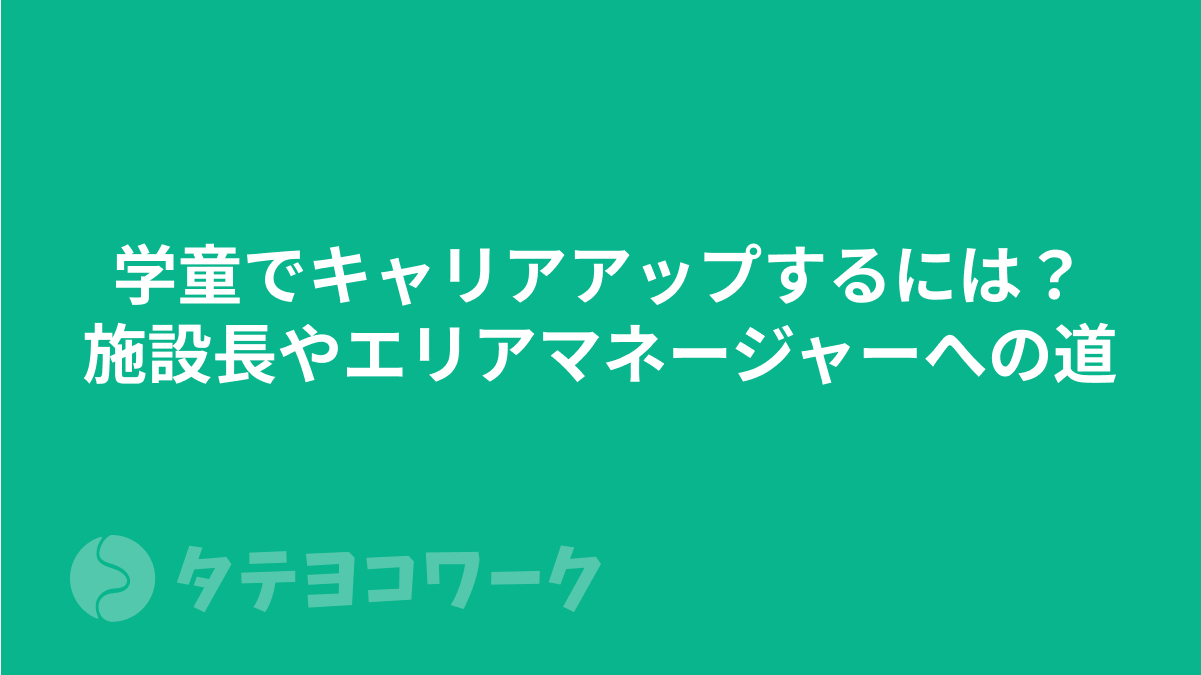
学童
キャリア
保育士
公立学童
社会福祉士
民間学童
教員免許
放課後児童支援員
未経験
転職
学童保育所で働く指導員の仕事は、こどもたちの成長を身近で見守るやりがいの大きい素晴らしい仕事です。しかし、忙しなく日々の業務に追われる中で、「この先どうやってキャリアアップしていけばいいんだろう?」と考えたり「お給料は上がるのだろうか…」と頭を悩ませたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本コラムでは、学童保育所の現場で働く皆さんが、施設長やエリアマネージャーといったキャリアアップを実現するための具体的なステップと成功の秘訣を交えながら解説していきます!
1. 学童保育のキャリアパスって?
学童保育の現場では一体どのようなキャリアパスが考えられるのか、まずは全体像を把握しておきましょう。なお、各施設・各運営事業者によって詳細は異なりますのでご注意ください。
①学童指導員(無資格者)
学童保育の現場でこどもたちの支援を行う基本的な役割です。遊びや学習のサポート、安全管理、保護者との連携など、幅広い業務を担当します。無資格であっても勤務することは可能で、基本的に学童保育のキャリアはここからスタートとなります。
②放課後児童支援員(有資格者)
学童指導員と業務内容はほとんど同じですが、放課後児童支援員という資格を保有することが次のステップです。子どもたちの育成支援を行う専門職として必要な資格で、各自治体が実施する放課後児童支援員認定資格研修を修了することで資格を得ることができます。
③リーダー(主任)
現場の指導員をまとめ、チームを率いる役割です。年齢が若くても抜擢されることの多い、比較的目指しやすい役職といえるでしょう。シフト管理や研修計画の作成、スタッフのマインドケアやイベントの企画・運営など、現場を円滑に運営するためのリーダーシップなどが広く求められます。
④施設長
学童保育施設全体の責任者です。施設の運営、スタッフの管理、予算管理、保護者との関係構築など、高いマネジメント能力が重要になります。保護者や本部スタッフ、役所とのコミュニケーション機会もグッと増えるため、経験豊富な職員が抜擢されることが多いポジションです。
⑤エリアマネージャー(※)
複数の学童保育施設を統括する役割です。各施設の運営状況の把握、施設長への指導・サポート、地域との連携など、より広範な視野と戦略的な思考が求められるようになります。
(※)エリアマネージャーは複数の学童事業を運営する大規模な会社で勤務をする場合に考えうるキャリアパスであり、小規模な学童の場合は施設長までのポジションしか用意されていない場合もあります。

また、近年では以下のようなキャリアアップの道も注目されています。
• 学童を運営する本部(本社)に異動する。
• 独立して民間学童を立ち上げる。
• NPO法人や子育て支援団体に転職する。
• 子育て支援・教育関係のコンサルタントとなる。
• 保育士・教員免許を取得して転職・兼業する
…など。
学童指導員のキャリアアップには、多様な選択肢があることがわかりますね。
2. キャリアアップに必要なこととは?
施設長やエリアマネージャーなど、学童でのキャリアアップを目指すためには、日々の業務を確実にこなし、自身のスキルを上げながら周囲からの信頼を得ることが非常に重要です。以下に具体的なポイントを紹介していきますのでぜひ参考にしてください。
( 1 ) 目の前の仕事に真摯に取り組むこと!
キャリアアップの第一歩は、目の前のこどもたちや保護者との関係づくりに丁寧に向き合うことです。指導員としての基本業務をしっかりこなすことが、信頼や評価につながります。
具体的には、以下のような姿勢が求められるでしょう。
• こどもの権利を尊重しながら支援する姿勢。
• 安全管理を徹底する責任感。
• チーム内での報連相(報告・連絡・相談)の徹底。
• 時間管理能力と優先順位のつけ方。
• 保護者への丁寧な対応。
上記のような行動を日々地道に積み重ねていくことによって、周囲から「信頼される存在」として扱われるようになり、職場における役割の拡大やポジションアップにつながっていくと考えられます。
( 2 ) 主体性と改善意識を常に持つこと!
「言われたことをやる」だけでは、上のポジションに推薦されることは難しいかもしれません。自分から様々な意見を提案する姿勢や、業務の中で気づいた課題に対して解決策を考える習慣が、リーダー候補としての評価に直結します。「本当に今のやり方で良いのか?」や「自分の行動や仕事の環境に改善できるところはないのか?」といった、クリティカルシンキング (批判的思考) ができるようになると良いでしょう。
例えば、
• 行事運営の際に、スケジュールの流れを工夫してこどもが飽きない構成を提案してみる。
• スタッフの間でうまく共有されていない情報を、掲示物やLINEグループで整理・可視化する。
• 事故やヒヤリハットが起きたとき、再発防止のルールづくりを自ら考案してみる。
こうした「小さな改善提案」や「行動の工夫」がこどもたちや職場全体を助けることになり、上司や同僚からの高い評価に繋がります。
( 3 ) スキルアップを目指して学び続ける姿勢でいること!
キャリアアップの要素として、資格取得や研修受講によるスキルの向上も欠かせません。現場での経験だけでなく、体系的な専門知識を持っていることで、自信を持って業務に臨むことができます。キャリアアップに活かせる資格や研修には、以下のようなものがあります。
★《必須》放課後児童支援員認定資格
都道府県や政令市が実施している公式研修で、これを修了することで「放課後児童支援員」の資格が与えられます。近年はこの資格を持っていないと常勤で働くことができない地域も増えているため、キャリアアップには必須となる資格といえるでしょう。
⭐︎保育士・教員免許・社会福祉士など
民間事業者では、これらの資格を保有している人を優遇するケースも多く、昇給や施設長への登用条件になっている場合もあります。転職市場でも有利になります。ちなみに上記の放課後児童支援員資格を取得する際にも、これらの資格保有者は受講を免除される項目があります。
⭐︎支援者向け実践研修・セミナー
資格取得を目指すだけではなく、知識や学びを得るための研修も積極的に受講していきましょう。最近では、「こども理解」や「発達障害支援」、「不適切保育を防ぐアンガーマネジメント」や「保護者対応」など、支援員向けの実践的なセミナーもどんどん増えています。費用は自己負担の場合もありますが、現場ですぐに活かせる内容を学んでいくことでキャリアアップにつながる可能性があります。
3. 具体的なキャリアアップの道筋
それでは、実際にどのようなステップでキャリアアップを実現していけるのか、具体的な道筋を紹介していきます。
【STEP①】学童指導員(未経験・無資格)
学童保育でのスタート地点は、無資格・未経験でのパートやアルバイト勤務や、新卒で採用されて勤務を始める場合が多いでしょう。このポジションでは、主にこどもたちの遊びや生活支援、日々の安全管理を担当することになります。
◎ ここで身につけるべきこと
• 基本的な支援スキル(見守り、声かけ、支援)
• チームワークとコミュニケーション
• こどもとの信頼関係構築
• 指導計画や行事の企画報告書などの書き方
▶︎ 次のステップへのポイント
• 放課後児童支援員資格の取得
• 遅刻・欠勤をしない安定勤務
• 行事やイベントのリーダー経験
• お便りや月報など基本的事務作業の習得
【STEP②】放課後児童支援員(常勤職員)
有資格者としての採用で、常勤職員や正社員として働くことができるようになると、シフトリーダー的な役割や、後輩・アルバイトスタッフの育成にも携わる機会が出てきます。
◎ ここで身につけるべきこと
• 現場やチームの全体把握
• こども対応+保護者対応
• 外部機関(学校・地域・役所)との連携対応
▶︎ 次のステップへのポイント
• 運営や業務にあたっての主体性
• トラブル時の対応力(クレーム対応含む)
• 一通りの事務作業習得
• 担当施設内での信頼獲得と存在感
【STEP③】主任・リーダー
施設長の補佐役として、現場スタッフの育成や日々の業務運営に責任を持つポジションです。施設の「現場力」を支える中核となる重要な役割です。
◎ ここで身につけるべきこと
• 他スタッフのメンタルケアや勤務状況把握
• シフト表の作成や年間運営計画の立案
• 施設長との連携強化
▶︎ 次のステップへのポイント
• 問題提起と解決策を提案できる力
• 本部や行政への計画書・報告書作成経験
• 指導計画・行事案の全体設計
• 内部研修の実施経験
• チームビルディングの成功経験
【STEP④】施設長
いよいよ学童施設の責任者。マネジメント、保護者対応、行政対応など、すべての力が求められる重要なポジションです。
◎ ここで身につけるべきこと
• スタッフの採用・評価・育成
• 保護者との信頼関係づくり
• 施設の運営・経営的視点(収支、安全管理など)
▶︎ 更なるステップへのポイント
• 本部や他施設との連携強化
• 地域や行政との会議での発言力
• 他施設の見学・交流など、視野の拡大
• 多拠点管理への意識向上・実践
【STEP⑤】エリアマネージャー
複数施設を統括し、運営支援や職員育成、行政との連携を担う役割です。こどもと関わる場面がグッと減り、大人とのやりとりが増えるポジションのため、経営視点・マネジメント力・調整力の総合力が問われます。
★ 活躍の場
• 施設長同士のネットワークづくり
• 管轄エリア内の課題抽出と改善提案
• トラブル対応とスタッフのサポート
• 現場と本部をつなぐ存在としての調整役
4. キャリアアップを支える「3つの習慣」とは?
最後に、上記のようなキャリアアップを目指すならば知っておきたい「3つの習慣」をご紹介します!今日からできることばかりなので、ぜひ実践してみてくださいね。
① 日常的に業務の振り返りをする!
毎日の業務の中で「今日のよかったこと・反省点・次に活かしたいこと」を簡単で良いのでメモに残しましょう。この習慣が、必ず自己成長の基盤になります。自分の行動を客観視し、改善のサイクルをつくっていくことが大切です。
② 他施設の事例に触れてみる!
学童保育は施設によって運営方針や雰囲気、働き方がまったく異なります。他施設の見学や、自治体主催の研修、業界イベントなどに参加して、実際に現場を見てみたりそこで働く人の話を聞いたりすることで、自身のキャリアアップに活きるような新たな視点を得ることができるはずです。
③ 情報発信をしてみる!
少しハードルが高いと感じる方もいるかもしれませんが、SNSやブログ、施設内のお便りなどでこどもたちの活動や自分の気づきを発信してみるのもオススメです。自身の思考が整理されるだけでなく、保護者や地域、他スタッフとの信頼関係構築や自己PRにもつながりますよ。ただし、個人情報の取り扱いには十分ご注意を!
おわりに
キャリアアップとは単なる昇進ではなく、「自分自身の成長の軌跡」であり「自分はこどもたちに対して、どのように関わることができるのか」を問い続ける道のりです。慢性的に学童業界は人手不足のため、実はキャリアアップのハードルはそこまで高くありません。自分はどのポジションで、どのくらいの給与水準で、どのような働き方をしたいのかをしっかりと見極めて、日々行動していくことが大切です。
このコラムをきっかけに、今の働き方を見直し、自分らしいキャリアビジョンを描く一歩を踏み出していただけたら嬉しいです。周りと比べることなく、一歩ずつ、自分のペースで。こどもたちとともに、自身の未来も育んでいってください。
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。