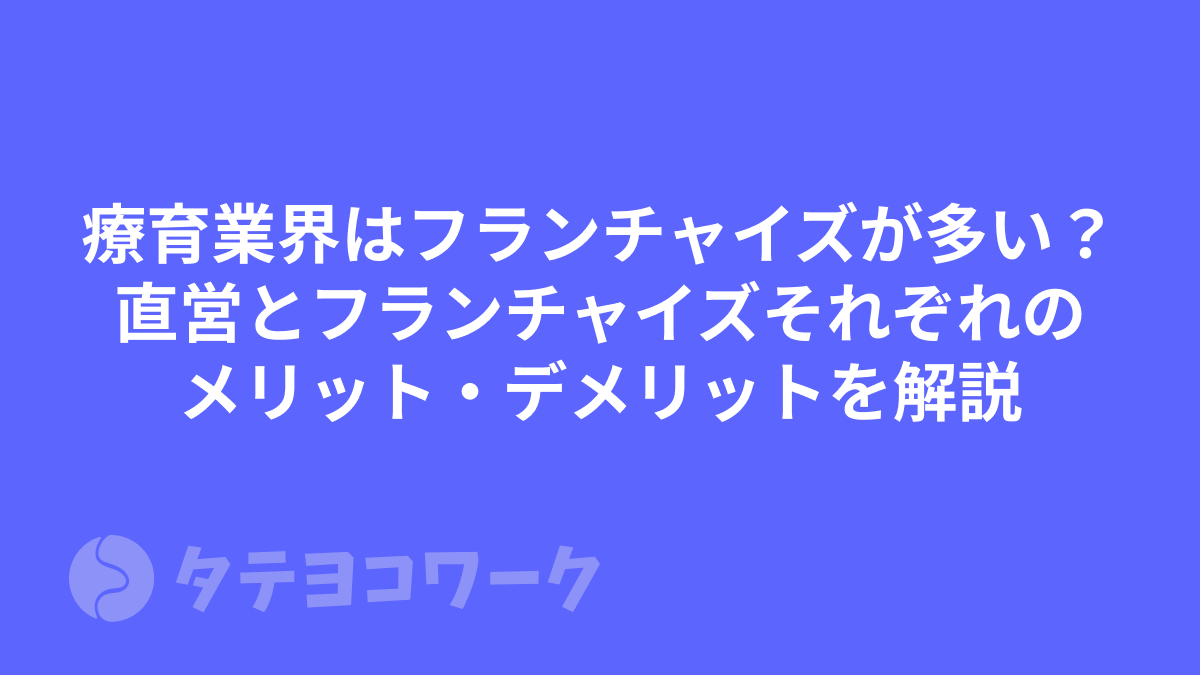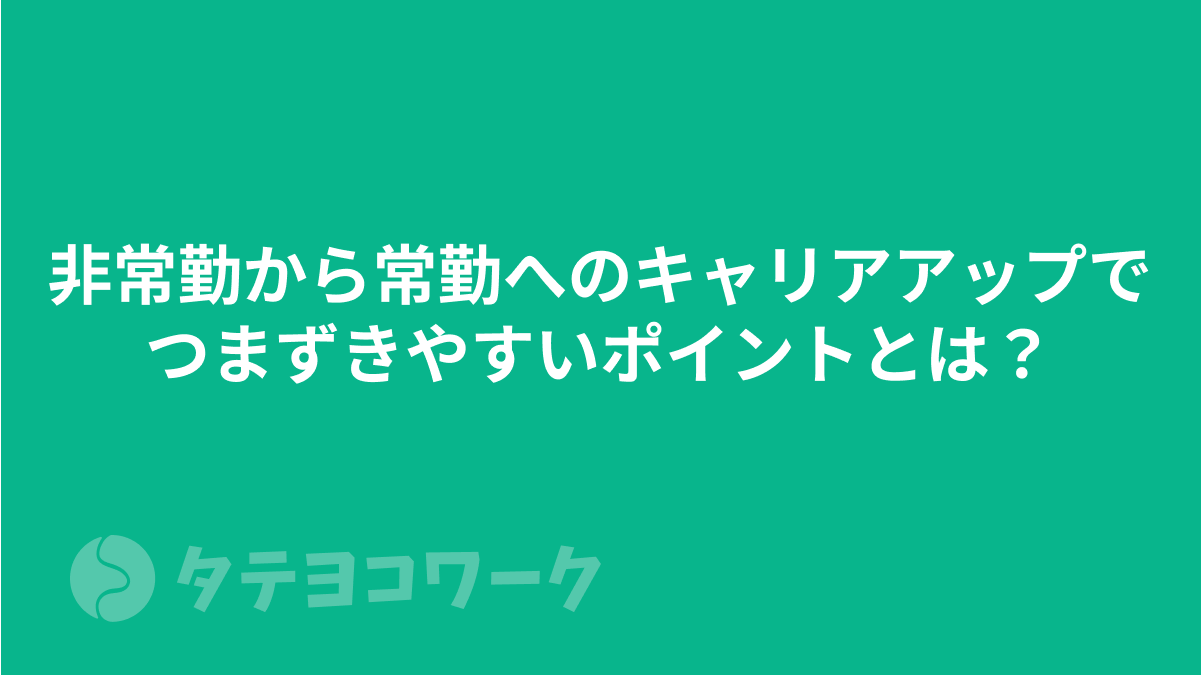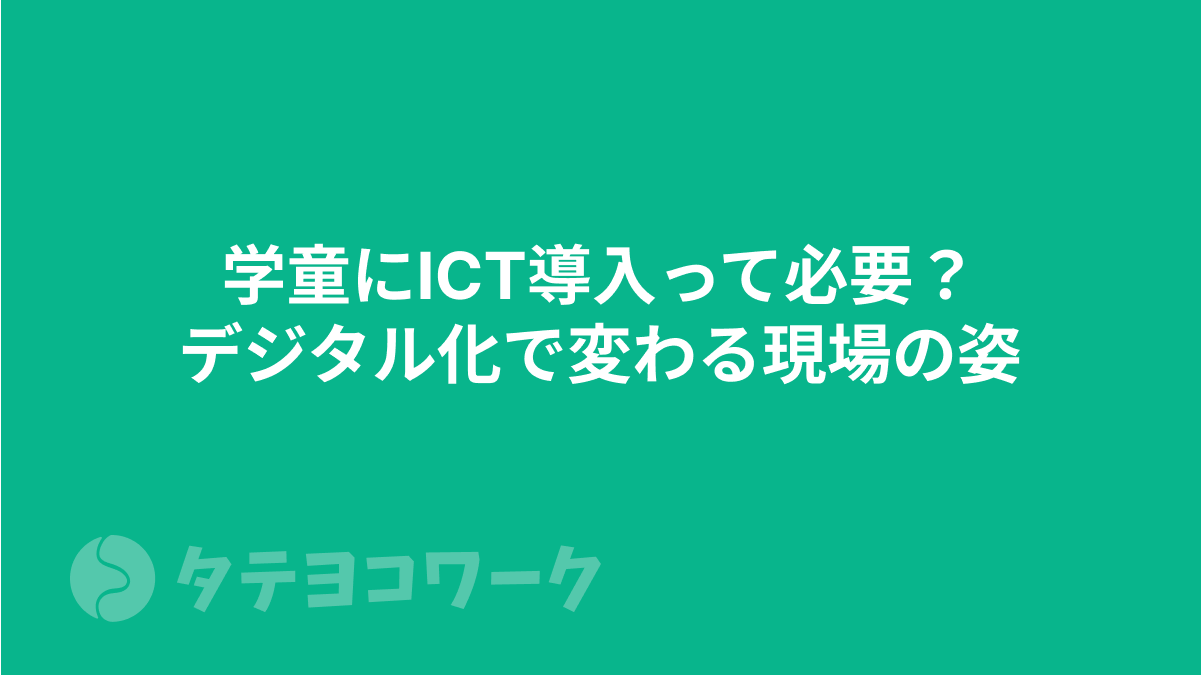タグで絞り込む
キーワードから探す
夏の学童保育で注意すべき点とは?安全と楽しさの両立のためのノウハウ
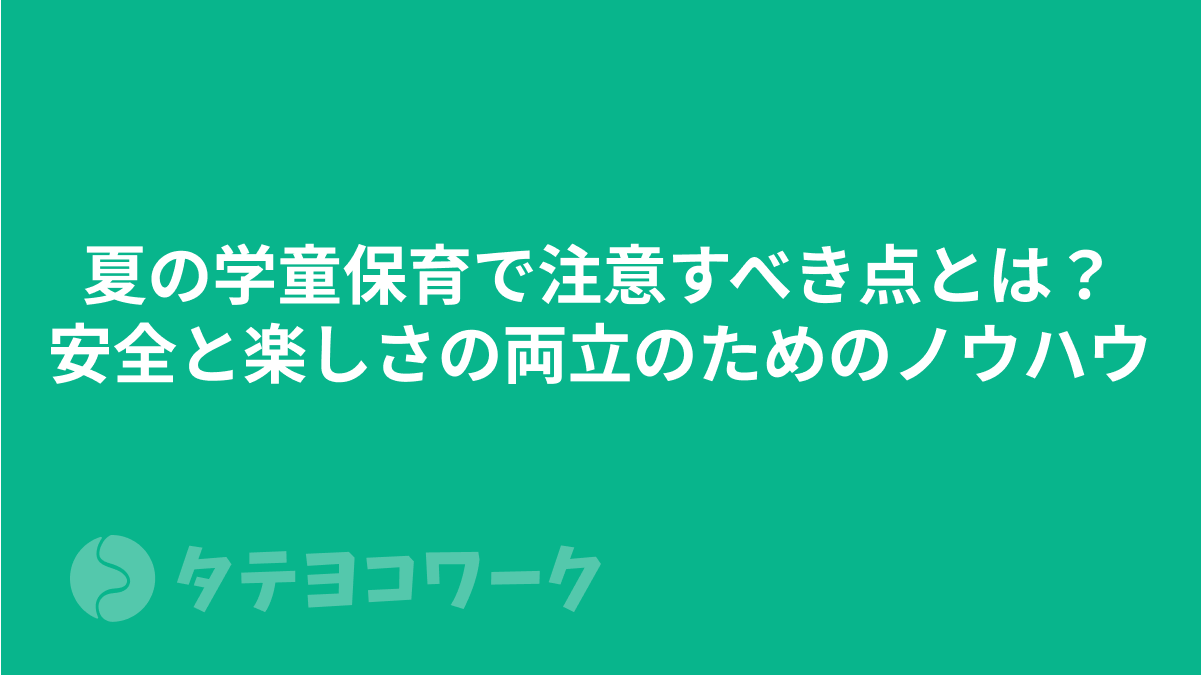
学童
ノウハウ
公立学童
民間学童
放課後児童支援員
あそび
夏休みの学童保育は、こどもたちの「やりたい!」があふれる特別な時間。友達と全力で遊び、挑戦し、思い出をつくることができる最高の季節である一方で、真夏ならではのリスクも少なくありません。学童支援員はこどもたちの熱中症や事故の防止などに努める必要があり、安全への配慮をより一層欠かせなくなる緊張感のある時期ともいえるのです。
さらに、これまでは「暑さのピークと1日保育が続く、夏休み期間さえ乗り越えることができれば…」と多くの現場スタッフは考えていたことでしょう。しかし近年は9月以降も残暑が厳しく、夏休みを終えてもなかなか安心できない状況が続いています。むしろ、夏休み後の疲れが出る時期に異常気象といえるような酷暑が重なることで、こどもも支援員も体調を崩しやすくなっているのが現実です。
そこで本コラムでは、暑さが厳しい夏の時期に学童保育で注意すべき点や、安全と楽しさを両立するための工夫を紹介します。
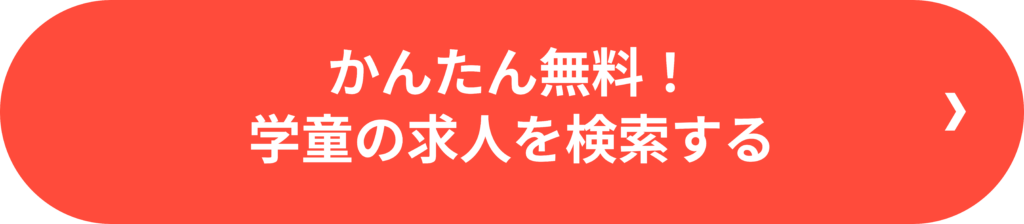
1. こどもの「やりたい!」を尊重しながら安全を守ろう!
学童に通うこどもたちは、毎日様々な遊びたいことや挑戦したいことで頭がいっぱいです。鬼ごっこや虫捕り、工作に読書など、やりたいこと・興味の対象は多岐にわたります。その溢れ出る好奇心こそが成長の糧となり、学童保育所の活気を生み、こどもたちの主体性を育てる土壌となります。
とはいえ、こどもたちの「やりたい!」は危険を孕んでいることもしばしば。特に暑い夏にもかかわらず「外で思いっきり体を動かして遊びたい」というこどもたちの想いには、熱中症のリスクが高いがゆえに、なかなか応えることが難しいですよね…。
常日頃このような場面での対応には頭を悩ませていることと思いますが、現場の学童支援員に求められるのは、単に禁止するのではなく「どうすれば安全に叶えられるか」を考えることです。
例えば、「鬼ごっこをしたい」とこどもが希望した場合には、涼しい時間帯を見計って外遊びに出かけ、日陰の多い場所で短時間だけ活動することで、熱中症のリスクを最大限に抑えつつこどもの希望を叶えられます。
なお、外に出られるかどうか判断する際は、スタッフの体感という漠然とした曖昧な基準に頼らずに、暑さ指数 (WBGT) ※を参考にしてくださいね。
※暑さ指数 (WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)とは?
人間の熱バランスに影響を与える以下の3つの要素を取り入れた指標で、熱中症予防の目安として用いられています。
・気温:空気の温度
・湿度:空気中の水蒸気量
・輻射熱:太陽光や地面、建物などからの熱
気温だけでなく、湿度や輻射熱も考慮することで、人が実際に感じる暑さに近い値を知ることができます。これにより、熱中症のリスクをより正確に判断し、適切な予防策を講じることが可能になります。
暑さ指数は、以下の5つの段階で熱中症の危険度を示します。
・21未満:注意(積極的に水分を補給しましょう)
・21~25:警戒(激しい運動や作業は避けましょう)
・25~28:厳重警戒(外出はできるだけ控えましょう)
・28~31:危険(高齢者や乳幼児は特に注意が必要です)
・31以上:極めて危険(運動は原則中止しましょう)
暑さ指数は、環境省熱中症予防情報サイトや気象庁の天気予報、各ニュースアプリや天気予報アプリ、自治体のウェブサイトや防災無線などで知ることができます。ぜひこまめにチェックをしてみてください。
暑さ指数をもとにした結果、どうしても外に出ることが難しいと判断した日には、「鬼ごっこをしたいということは、友達と走り回りたいということ?」などとより詳細なこどものニーズを聞き取り、その気持ちに応えられるような室内遊びを提案できると良いでしょう。
風船バレーやフルーツバスケットなど、室内でも安全に考慮しながら体を動かし、満足感を得られる方法をこどもたちと一緒に考えて実践することはできます。また、近隣に小学校の体育館や市民体育館などの室内で走り回れる場所があれば、そういった施設を借りることも検討しても良いかもしれません。
闇雲に全てを規制するわけでもなく、こどもの希望を全て応えて無茶をするわけでもない。そんな、こどもたちの「やりたい」を尊重しながら安全を守ろうとする姿勢こそ、学童保育における支援員の基本といえるでしょう。
2. 真夏の定番 「水遊び」の魅力とリスクについて
暑い夏の学童に欠かせない活動の一つが水遊びです。水遊びは体を冷やし、気分をリフレッシュできますし、短時間でも充実感を味わえる面白い遊びであるため、こどもたちに大人気です。プールや川での遊泳だけでなく、公園・校庭での水鉄砲合戦や水風船づくり、ミストシャワーなど、バリエーションも豊富です。夏場に外で遊ぶなら、水の使用は必須と言っても良いかもしれません。
しかし、水遊びは楽しいだけでは済まされない危険も伴います。実際に、2025年7月には東京都小金井市にて学童保育中にプール遊びをしていた小学1年生の児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しています。
水遊び中にこどもたちの安全を守るためには、参加人数を制限し支援員の目が届く範囲で遊んでもらうことや、熱中症や疲労による事故を防ぐために活動時間を10〜15分程度の短時間に区切って遊ぶこと、水深は膝下までに制限することなどの工夫が必要です。そして、充分な人数の学童支援員を配置して見守りの目を少しでも増やしましょう。
また、遊ぶ前後にはこどもたちの体調や体温を確認し、体調が少しでも悪い場合は無理に参加させないことも重要です。活動後には必ず着替えや休憩を促して健康状態を整える配慮も欠かせませんし、いざという時のために心肺蘇生法を学んでおくことも水遊びの安全管理においては大切な準備です。
こうして注意事項を列挙してみると、水遊びの時間は支援員にとっては非常に緊張感のあるものであるとわかりますね。
熱い夏に外遊びをするため、そしてこどもたちの強い要望に応えるために、積極的に取り入れられがちな水遊びですが、魅力とリスクの双方を理解しておくことが非常に重要です。
3. 夏だからこそできる学童の工夫
水遊び以外にも、工夫次第でこどもたちに楽しさと学びを提供できる夏ならではの活動はたくさんあります。
たとえば、冷たい食べ物を作ったり食べたりするクッキング活動は、暑い夏だからこそ楽しめる安全な活動です。冷やし中華作りやフルーツポンチ作り、アイスバー作りなどがおすすめです。少し実施難易度は上がりますが、流しそうめんのイベントなども実施できると非常に盛り上がるでしょう。
なお人数が多い施設の場合は、全員が調理に参加するとなると時間がかかりすぎてしまいますし、目が行き届かなくなる危険性もあるため、状況に応じて「切る作業は学童支援員が担当し、盛り付けはこどもが行う」などと役割を分けることで安全を確保しましょう。また、アレルギー対応や食中毒発生防止などにも充分注意してください。
また、夏祭りごっこも人気の活動です。射的や輪投げ、ヨーヨー釣りを工作から作り、準備段階からこどもたちが参加することで、当日だけでなく準備の過程も楽しめます。
科学遊びも夏にぴったりな面白い活動です。氷を使った実験や水を使ったロケット、太陽光を利用した影遊びなど、夏らしく身近な素材を活用して工夫すれことで、学びと遊びを両立させることができます。
このような活動を計画するときは、学童支援員がすべて準備して与えるのではなく、こどもたち自身が主体的に参加できる設計にすることがポイントです。こうした工夫により、こどもは遊びの中で達成感や学びを得ると同時に、仲間と協力する楽しさも体験できます。夏で外に出られない不満を吹き飛ばすような面白い活動を、こどもたちと一緒に生み出していきたいですね。
4. 夏を乗り切るための学童支援員の心構え
こどもの「やりたい!」を安全に叶えるためには、学童支援員自身の意識や行動が非常に重要です。
こどもたちが安心して挑戦できる環境を作るためには、まずは学童支援員自身が安全管理の基本を理解し、体調管理や活動の準備に努める必要があります。
水分補給や休憩をこどもたちと一緒にとることで、自身の健康を守ると同時に、休むことの大切さをこどもに伝えることもできます。
また、いつも以上に職場全体のチームワークも必要となってきます。活動前には役割分担を明確にし、誰が監視を行い、誰が準備や片付けを担当するのかを決めておくことが大切です。特に水遊びには多くの人員を割く必要があることから、全体の様子を見ながら配置を考えなければいけません。
夏休み中は忙しくゆっくりと全体MTGをすることが難しいと思いますが、ぜひ夏休みが終わった後のタイミングで振り返りの時間を設け、暑い時期の関わりに関する改善点や気づきを共有し、9月以降の活動に活かしていきましょう。「こどもたちの希望」と「安全」を天秤にかけるのではなく、「安全の枠の中でどうすれば希望を叶えられるかを常に考えること」が支援員ひいては施設全体に求められます。
日頃からこどもたちとの信頼関係を築くことも重要です。
こどもたちに「先生はやっちゃダメ、としか言わない」と思わせてしまうのではなく、「自分たちのことを考えて、いつも一緒に悩んでくれる」と思ってもらえるような環境を整えていくことが必要です。
学童支援員が安全管理に懸命に取り組む姿勢が、こどもたちの不満につながってしまっては勿体ないですよね。信頼や安心感につなげられるような声かけ・関わりを実践していきましょう。
まとめ
夏の学童保育は、危険と隣り合わせでありながらも、こどもたちにとってかけがえのない思い出をつくる場です。
こどもたちの「やりたい!」を尊重しながらも、安全管理を徹底し、夏ならではの活動を工夫して提供すること。そして、支援員自身が安全と楽しさの両立を常に意識すること。これらのポイントを大切にしていけば、暑い時期であったとしても学童保育所はこどもたちにとって最高の居場所になっていくはずです。
近年は、暑さが9月以降まで長引くのが当たり前になってきており、夏休みさえ終われば一息つける…という時代ではなくなっています。だからこそ、このコラムで紹介した工夫や安全対策は、これからの残暑期にも活かせる実践的な視点となるはずです。長い夏をこどもと支援員のどちらも無理なく乗り越え、楽しんでいきましょう!

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。