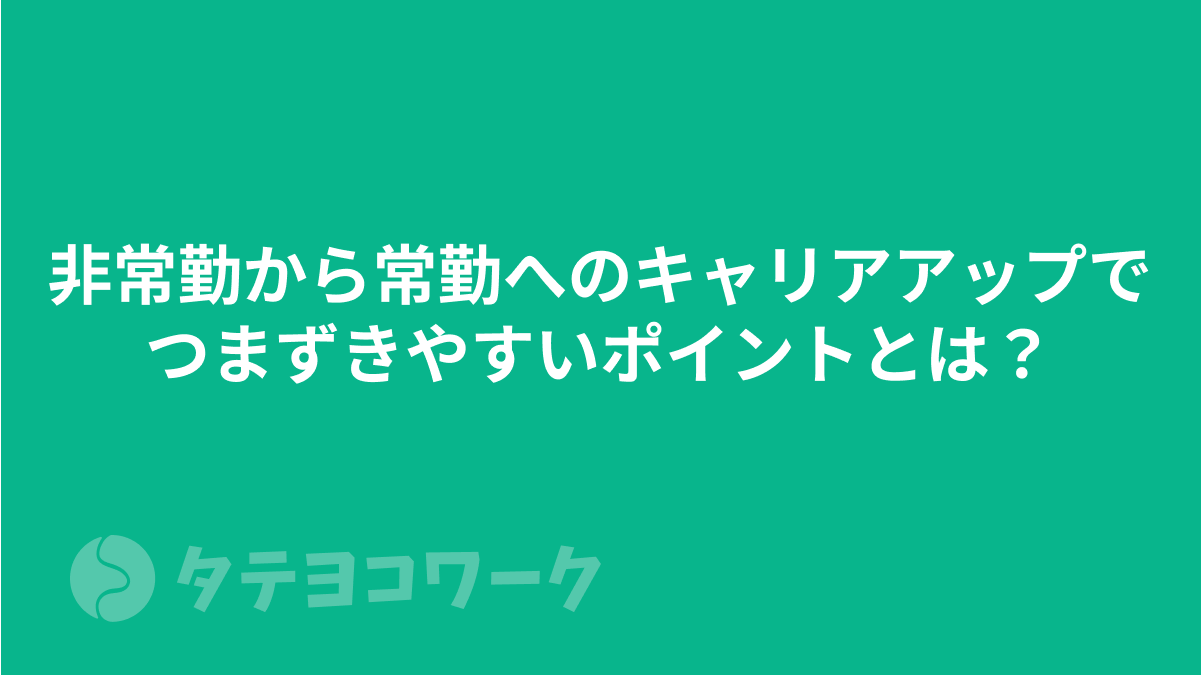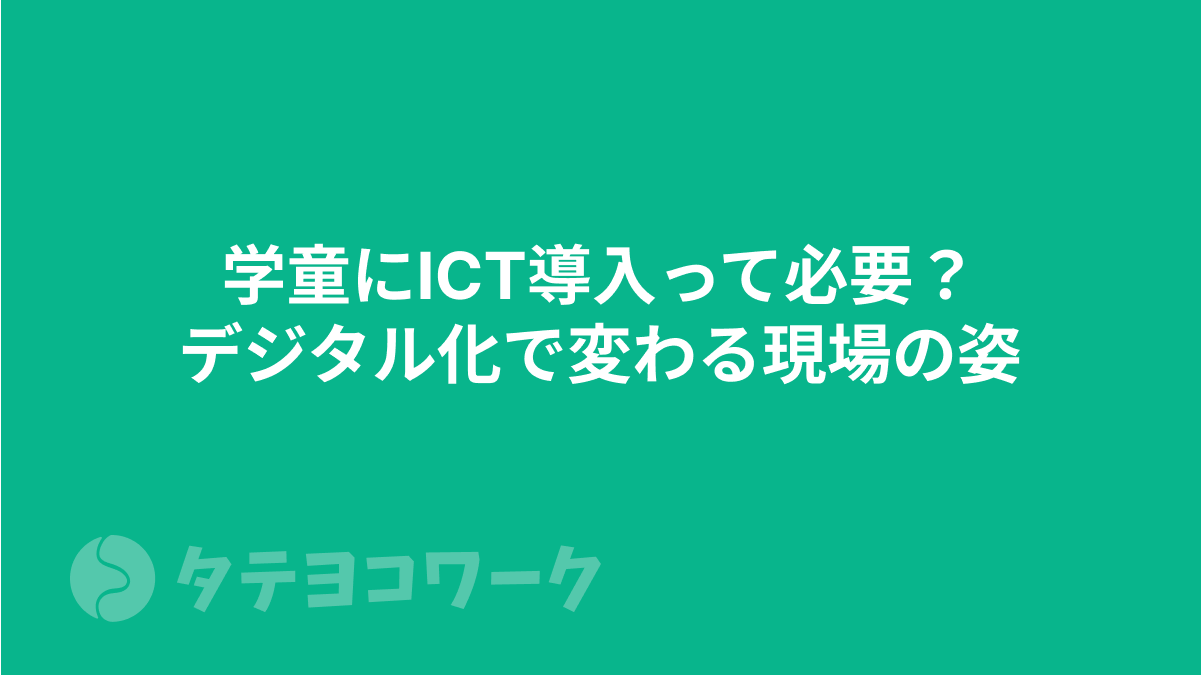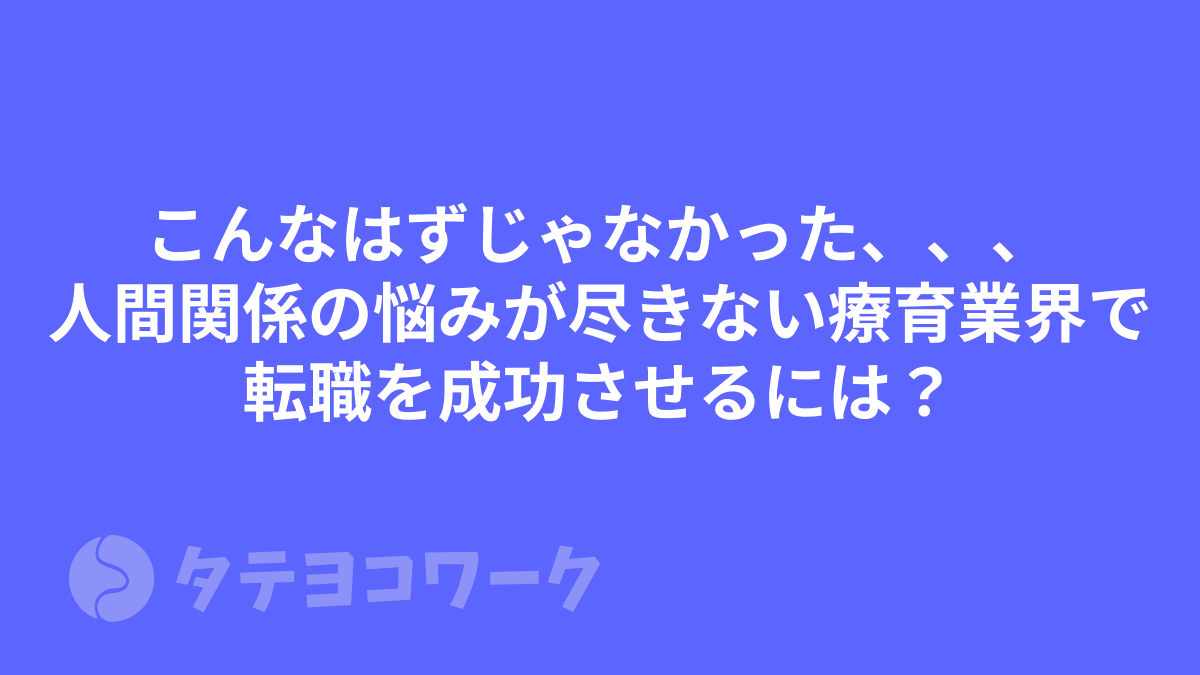タグで絞り込む
キーワードから探す
不登校のこどもたちのために、学童保育所ができることとは?
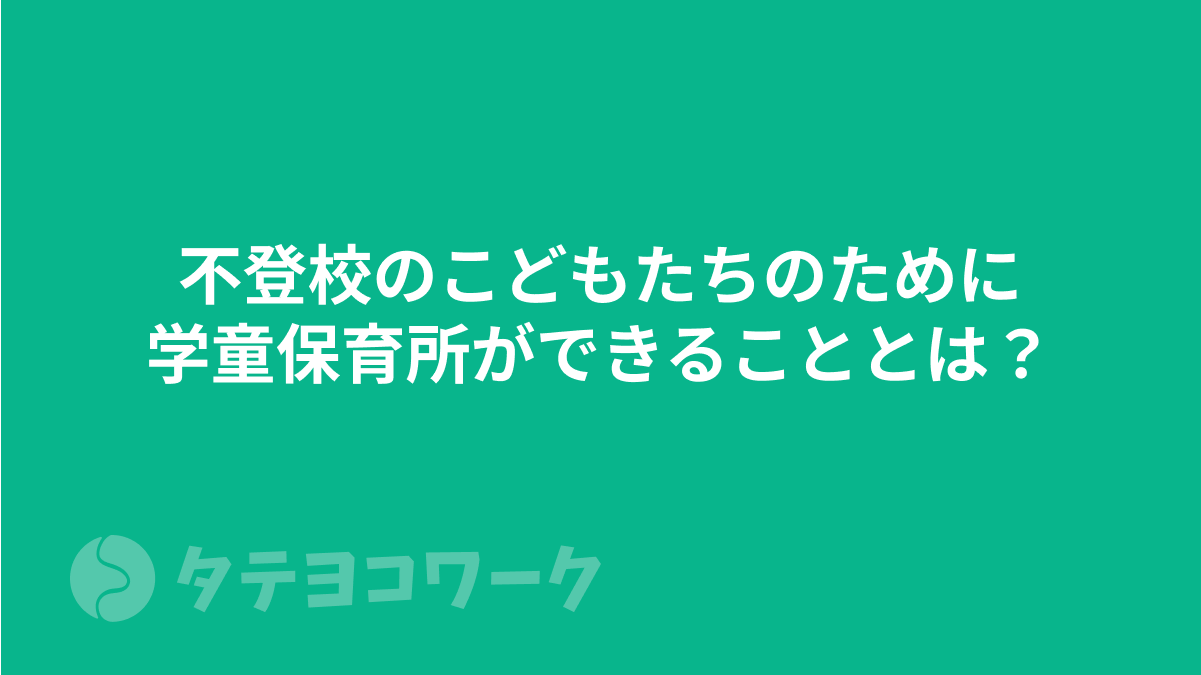
学童
公立学童
発達支援
民間学童
近年、学校に通うことができないこどもや、学校に通わない選択をするこどもたちが増加しています。文部科学省の統計によると、小中学校に通う子どもの約30万人以上が、年間30日以上休む状態が続いているそうです。小学生だけでも、約10万人以上のこどもたちが学校に登校できていないという現状があります。
学校や家庭だけでは対応しきれない不登校のケースも増えてきている中で、現代の小学生にとって非常に馴染み深い場所である学童保育所は、どのような役割を果たせるのでしょうか?
本コラムでは不登校の要因やサードプレイスの重要性について触れながら、不登校のこどもたちのために学童保育所という場所にできることについてまとめていきたいと思います。
不登校の要因・背景について
不登校のこどもたちが増えている要因や背景については、以下のようなものが考えられます。
①いじめや人間関係トラブルの深刻化
クラスメイトからの無視やからかい、酷いいじめをされることによって学校に行くことを怖れるようになってしまうこどもたちがいます。最近はデジタル機器やSNSの発達により、スマートフォンやゲームを持っていないことで仲間外れにされたり、LINEグループに入れてもらえない・Instagramの親しい友達から外されるなどSNSを使った嫌がらせを受けたり、盗撮や加工画像などの問題が発生したりといった現代ならではの課題もあるといわれています。また、こども同士の関わりだけでなく、学校の先生との関わりの中でトラブルが起きる可能性もあります。
②こどもたちの発達や個性に対する理解不足
発達障がいや強い感受性を持つこどもたちは、学校の環境に馴染めず、息のしづらさを感じやすいといわれています。ADHDやASDだけでなく、LD(学習障がい)やHSP(刺激に敏感な特性)、ギフテッドなどこどもたちには様々な個性がありますが、一人ひとりに最適な環境を整っているとはいえない現状です。
③コロナ禍による影響
新型コロナウイルスの蔓延により、外出や集団活動の制限、リモート学習が導入されたことで、こどもたちの日常や生活のリズムは大きく乱され、社会的孤立感が深まったといわれています。マスクを外した顔を見せることが怖い、対面して会話をすることが苦手、というこどもたちも一定数存在します。新型コロナウイルスの蔓延が落ち着いてきた昨今でも、その影響は強く尾を引いているのです。
④家庭環境の問題
両親が離婚をした、引越しをした、経済的に余裕がない、両親が多忙でなかなか家族の時間が取れない、両親から学業や人間関係・遊び方などについて過度なプレッシャーをかけられる、身内に不幸があったなど、様々な家庭環境の問題から心身のバランスを崩し、不登校になるこどももいます。不登校は学校の問題と考えられがちですが、家庭環境に起因している場合もあるのです。
このように、多くのこどもたちが多種多様な理由で学校に行けなくなる状態に追い込まれています。何か特定の理由によって不登校になるというわけでなく、複合的に絡み合った要因がある場合もあります。また「理由は分からないけどなんとなく行きたくない…」というように、漠然とした不安を感じている子も。
どのような背景があれど、重要なのは「こどもたちは何の理由もなく学校へ行くことを拒絶しているわけではない」ということです。こどもたちには、それぞれの事情や要因があり、その背景には深い心理的な痛みや不安、葛藤があります。
そして、こどもにとって学校へ行かないことは、単なる甘えやわがままではありません。自分を守るために発動させる自己防衛の一つの形だと理解する必要があります。つまり、不登校はこどもたちが大人社会のルールや環境に対して抵抗し、自己肯定感や安心感を保つために使った精一杯の手段ともいえるのです。
サードプレイスの重要性について
不登校であるこどもたちの多くは、日中の時間を家の中で過ごしています(保健室や自治体が定めた通級教室、民間のフリースクールなどに通えている子もいます)。日中の時間帯に誰かと顔を合わせるのが怖い、学校に行っていないの?と言われたり思われたりしたくない、外部との関わりを避けたいと感じている子が多いためです。
しかし、家庭内にこもる時間が増えるほど、子どもたちは社会とのつながりが失われることになり、ますます孤立する危険性が高まります。
このような状況において、近年「第三の居場所」といわれる子どもたちが学校や家庭以外に、安心して過ごせる場所が注目されるようになってきました。
・学校には行きたくないけれど、誰かと一緒に遊びたい。
・学校に行きなさい、勉強をしなさい、ゲームはやめなさいと親に言われるのがつらく、学校にも家にも居場所がないと感じる。
・学校に無理に行かせたくはないけれど、家にずっといるのは心配。
そんなこどもたちと保護者にとって、大きな支えとなるのがサードプレイスです。プレーパークや児童館、公民館や図書館、民間のフリースクールなどが有名ですが、実は学童保育所(放課後児童クラブ)もサードプレイスの一つです。
学童は不登校のこどもたちの居場所になる?
学童保育所は、親が働いている間のこどもたちを預かる「安全な託児施設」として長年機能してきましたが、最近は「こどもたちの心身の成長を支える場」や「コミュニケーションや社会性を育む場」、そして「地域におけるサードプレイス」としての役割が注目されはじめています。そして、学校に行っていない不登校のこどもたちにとっても重要な居場所になる可能性があるといわれています。その理由をいくつか挙げてみましょう。
①学習をする場・評価をされる場ではないから。
学童保育所では宿題・学習のサポートを行う場合もありますが、それはあくまでも付加的な要素にすぎず、最も大切なのは、「遊び・体験・交流」の時間とされています。こどもたちは好きな遊びに熱中する中で、自然と「ルールを守る」「協力する」「創造性を発揮する」「達成感を味わう」などの生きる力を身につけていきます。
このような活動において、点数をつけられたり評価をされたりすることはなく、不用意に自己肯定感を削られるような仕組みが学童保育所にはありません。そのため心理的安全性が高く、不登校で学校には行っていない(行きたくない)けれど、学童には行きたいと思える子も多くいるのです。
②学童のスタッフは勉強を教える先生ではないから。
学童保育所という環境では、大人とこどもたちは対等な関係を築き、温かく受け入れ合う空間が広がっている場合が多いです。学童スタッフは学習指導をする先生ではないため、上述のとおりこどもたちのことを点数や成績で比較をしたり評価をしたりすることもありません。そのため、こどもが「ありのままでいられる」という安心感を抱きやすく、自尊心や自己効力感を高められる可能性があるのです。
学校の先生でもなく親でもない、第3の大人がいることは不登校の子にとっても大きな心の拠り所になります。
③異年齢交流が活発な場所だから。
学童では、異なる年齢や性格の子どもたちが関わり合いながら、遊びを通して自然に信頼関係を築くことができます。「この場所(この仲間)なら、自分は受け入れてもらえる」と感じられれば、自分の居場所を見つける助けとなります。
たとえ学校のクラスにうまく馴染めず、同級生と仲良くできなかったとしても、学童保育所で他のクラスや学年、他の学校のこどもたちと遊ぶことができるならば、心の安定と自信につながるのです。
不登校のこどもたちに対して、学童ができること
それでは、具体的に学童保育所は不登校の子どもたちに対してどのような支援ができるのでしょうか。今回は大きく分けて3つの支援内容を挙げてみます。
①安心できる「もうひとつの居場所」を提供すること。
決められた目標や時間割が無い学童保育所では、「今日は何もしたくない」「静かに過ごしたい」といったこどもの気持ちを尊重し、その気持ちに寄り添うことができます。
このような空間は不登校のこどもたちの「逃げ場」や「避難所」としての機能に加え、「リハビリの場」としても効果を発揮すると考えられます。家族以外の人との関わりを通して、こどもたちは少しずつ安心して笑顔を取り戻し、自信をつけることができるのです。
②人間関係の構築をサポートすること。
学童は、学校よりも小さな集団規模かつ異年齢保育であることが多いため、こども同士が気軽に学校とは違う人間関係を築きやすい環境といえます。様々な人と関わる中で、役割や責任を持つ経験を積み、コミュニケーション能力や自己肯定感を育むきっかけを提供できる可能性があります。
また学童保育所のスタッフは、学校現場よりもゆっくりじっくりこどもたちと個別で関わることができるため、他者との関わりに不安や苦手意識を感じている不登校のこどもたちに対して、適切な支援をすることも期待できます。
③遊びの中で学ぶ機会を提供すること。
こどもたちは学童保育所で自分の好きな遊びにとことん向き合うことで、多くのことを覚え、学んでいきます。ボードゲームやカードゲームでルールを理解したり、工作や活動を通じて創造力を養ったり、集団活動やイベントで達成感や自信を得たり…これらは「学力の向上」とは別軸の、社会性や自己肯定感といった「生きる力」を育むための重要な学びです。
遊び道具や一緒に遊ぶ仲間が揃っている学童保育所の環境は、「生きる力」を学ぶ場として最適であるといえます。
④不登校児の保護者サポートができる。
学童保育所は不登校のこどもたちだけでなく、不登校児童の保護者が抱える孤独感や不安・負担を和らげる役割も果たせる可能性があります。スタッフと保護者が連携して、子育ての悩みや支援の必要性について話し合い、必要に応じて地域の福祉や支援団体とつながることも可能です。こうした連携は、家庭や地域社会を巻き込みながら、こどもたちの多様なニーズに対応した包括的な支援体制を作る基盤となります。
まとめ
学童保育所は、こどもたちが自由に遊び、自分らしさを育む大切なサードプレイスです。自己肯定感を取り戻し、人とつながる力をゆっくりと育みながら、自分のペースで前に進める学童保育所は、学校や家庭だけでは解決しきれない子どもたちの居場所として大きな役割を果たしているといえます。
しかしながら、学童保育所は本来放課後の時間にこどもたちを預かるという特性上、「午前中から預かってくれる環境があるか」や「学校に行っていなくても学童だけ利用することができるか」などの判断は施設によって異なるのが現状。こどもが不登校になったことで思うように働けず、学童の利用条件を満たすことができないといい家庭もあるそうです。
不登校の家庭にとっても学童保育所で働くスタッフにとっても負担の少ない、より良い仕組みづくりについて、社会全体で考えながら構築していく必要があるでしょう。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。