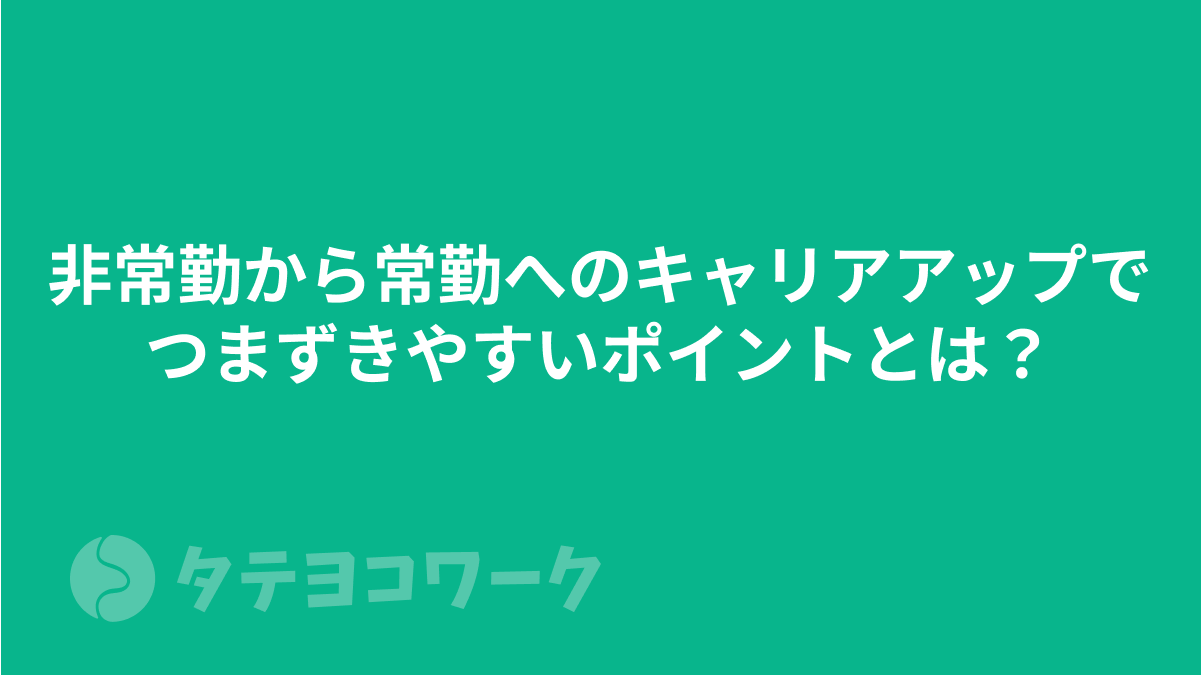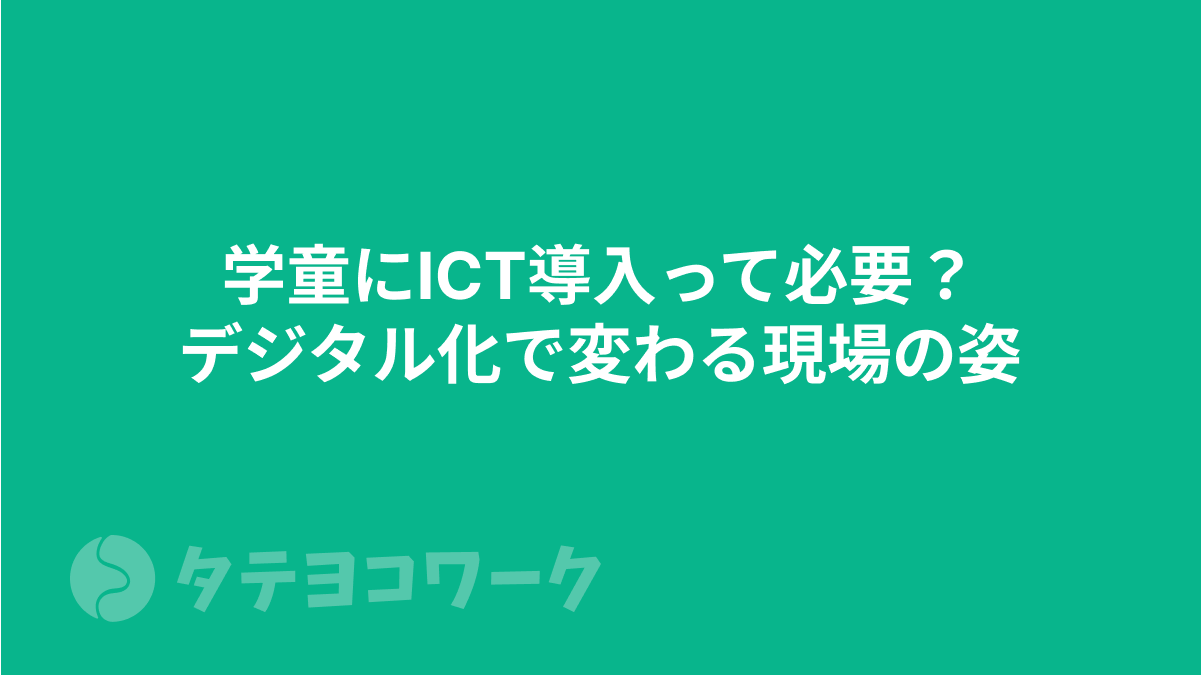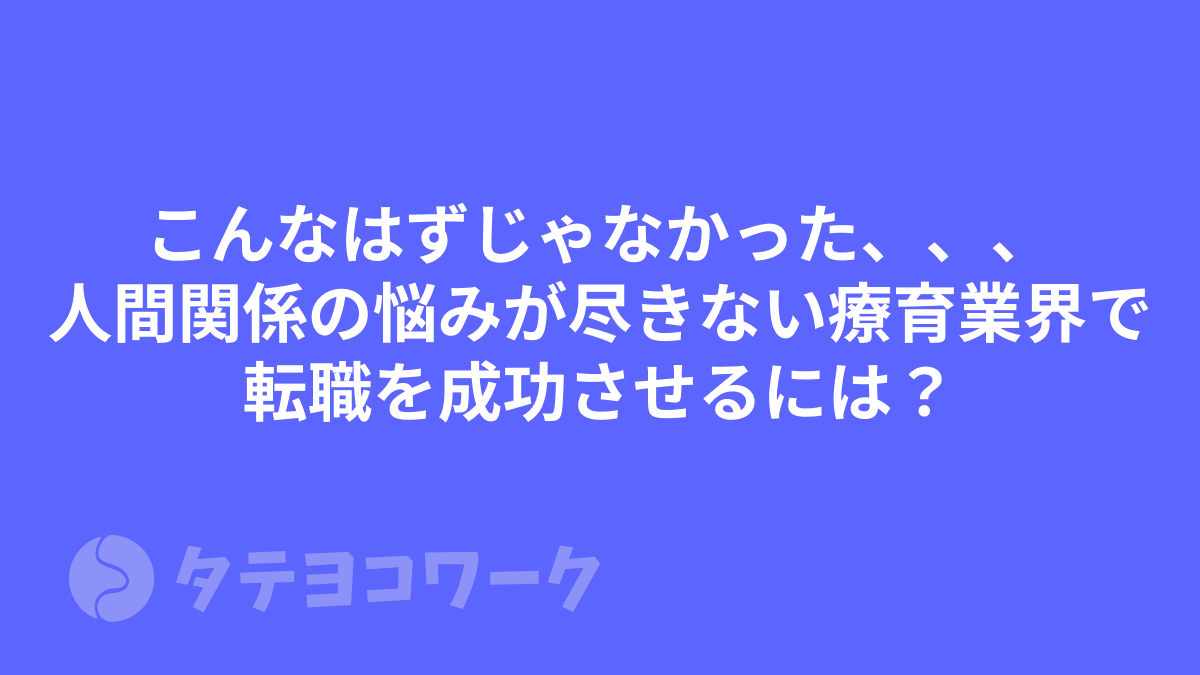タグで絞り込む
キーワードから探す
塾講師の経験は療育でも活かせる?
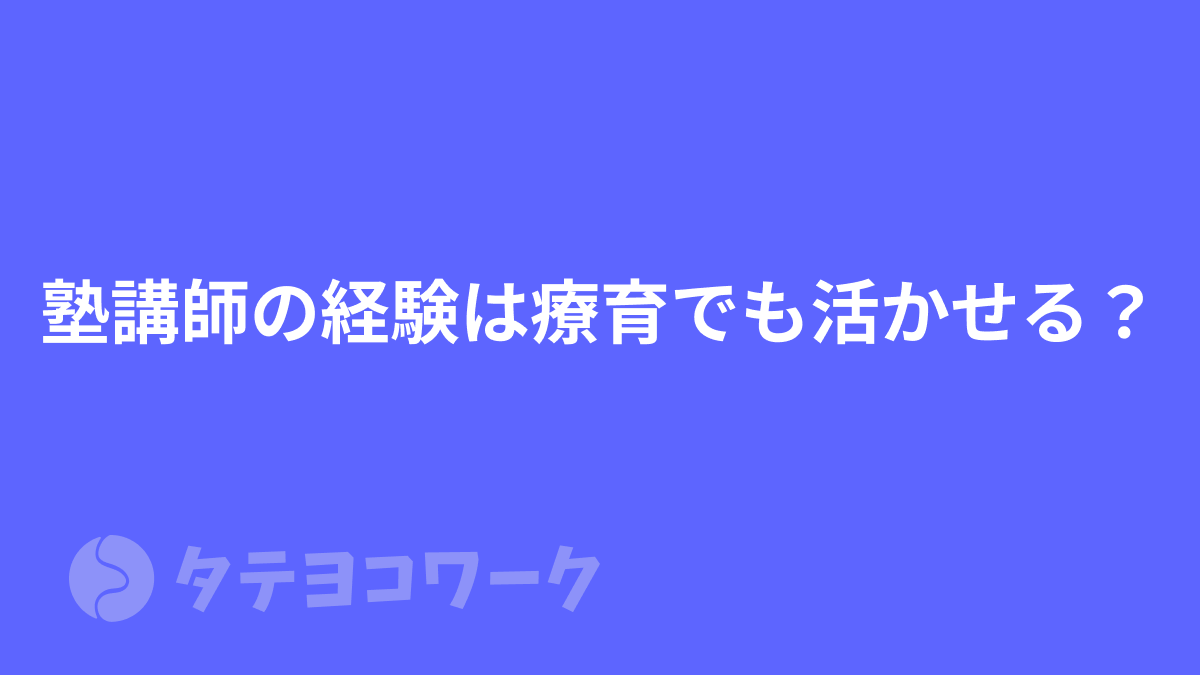
療育
キャリア
キャリアチェンジ
児童指導員任用資格
児発
放デイ
転職
はじめに:教育と療育の接点とは
近年、発達障害やグレーゾーンの子どもたちへの支援に関心が高まる中で、「療育」のニーズが拡大しています。そしてそれと同時に、塾講師や家庭教師として教育現場に関わっていた人材が、療育の分野に転身する例も増えてきました。
塾と療育、一見すると目的や手法が異なるようにも思えますが、実は多くの共通点があります。特に「一人ひとりに応じた支援」「保護者との信頼関係」「柔軟な指導力」など、塾講師時代に培ったスキルは、療育の現場で非常に役立つことがあります。
本コラムでは、塾講師の経験が療育にどう活かせるのか、どのようなスキルが評価されるのか、実際の場面ではどんな違いがあるのかについて、具体例を交えながら深掘りしていきます。

「学びを支える」立場としての共通点
個別最適化された支援への理解
塾の現場では、生徒一人ひとりの学力や性格、目標に応じて教え方を変えることが求められます。特に個別指導塾では、「同じ教科書を使っていても指導内容が異なる」という状況が日常です。
これは、療育で求められる「個別支援計画」に非常に近い発想です。発達に特性のある子どもたちは、視覚・聴覚・感覚の優位性や、注意・集中の持続時間、得意・不得意の傾向が大きく異なります。そのため療育の現場でも、同じプログラムを全員に一律で提供することは難しく、「その子に合ったやり方」を見つけていく必要があります。
このような「一人ひとりに合わせて調整する」という姿勢やスキルは、塾講師の経験から得られる極めて重要な資質です。
学習支援=療育の一部
療育というと「生活習慣」「コミュニケーション」「感覚統合」などが主なイメージとして挙げられますが、学習支援もその一部です。特に放課後等デイサービス(通称:放デイ)では、宿題や予習復習のサポート、学校の授業内容の理解補助など、学習的な支援が必要とされる場面が少なくありません。
ここで塾講師の経験が直接活きてきます。教科の知識だけでなく、「どこでつまずいているかを見抜く力」や「理解できるようにかみ砕いて説明する力」は、子どもたちの自信や成功体験に直結します。
保護者対応のスキルも武器になる
塾講師としての保護者対応の経験
多くの塾では、定期的に保護者面談や電話でのフィードバックが行われます。ここで大切なのは、「子どもの状況をわかりやすく説明する力」と「保護者の不安に共感し、信頼を築く姿勢」です。
このスキルは、療育の現場でも必須となります。なぜなら、療育は「子どもと保護者を一体として支援する」ものだからです。保護者の協力なしに、安定した支援は成り立ちません。
また、療育を受けているお子さんの保護者は、学校生活や将来への不安を多く抱えていることが少なくありません。そうした保護者の気持ちに寄り添い、前向きな関係を築ける塾講師の資質は、療育現場でも非常に重宝されます。
子どもの変化を言語化できる力
保護者対応の中で、最も難しいのが「子どもの変化を具体的に説明すること」です。学習においても、療育においても、子どもは日々少しずつ成長していますが、その変化は見えにくいものです。
塾講師として「前回より計算のミスが減った」「文章題の読み取りが速くなった」など、小さな変化をとらえて言語化する力を養ってきた人は、療育でも「前より落ち着いて椅子に座れるようになった」「順番を待てるようになった」といった行動の変化を捉えるのが得意です。
このような観察力・記録力・報告力は、療育での保護者連携の要になります。

療育の現場ならではの特性とは?
塾講師の経験が療育に活かせることは確かですが、当然ながら「療育ならではの特性」も存在します。特に療育では、学力向上だけでなく、「生活スキル」「社会性」「情緒の安定」「自己肯定感」など、多面的な発達を支援することが目的となります。
塾講師が関わる際に注意したいのは、「点数が上がれば良い」という視点を少し横に置くことです。たとえば、椅子に10分間座って話を聞けるようになった、お友だちとトラブルなく遊べた、といった行動の変化こそが、療育における大きな成果と見なされます。
これは言い換えれば、子ども一人ひとりの「小さな成功」に目を向け、そこを評価し、支えていく姿勢が必要であるということです。塾講師として「達成主義」に慣れてきた人にとっては、新たな視点が求められる場面でもあります。
「支援的視点」と「指導的視点」の違い
ここで重要なのが、「支援」と「指導」という言葉の違いです。塾講師の多くは「指導者」として、ある程度の“ゴール”を設定し、その達成を促します。これに対して、療育では「支援者」として、子どものペースや特性に寄り添いながら、「どのように取り組めば安心して参加できるか」「どうすれば成功体験を積めるか」といった“環境づくり”が中心になります。
この違いを理解せずに、塾講師の経験だけでそのまま療育に飛び込むと、「思ったようにいかない」「子どもに拒否されてしまった」といった壁にぶつかることがあります。しかし、これは失敗ではありません。むしろ、そのような違いを乗り越えて「支援的視点」を身につけたとき、塾講師経験者は非常に頼もしい支援者に変わります。
発達障害の特性理解は必須
療育では、ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などの特性に対する基本的な理解が求められます。たとえば、ASD傾向のある子どもは「曖昧な指示が理解できない」「感覚の過敏がある」「視線が合わない」などの特性を持つ場合があります。これらを理解せずに「ちゃんと聞いていない」「指示通りに動かない」と判断してしまうと、子どもとの関係性は築けません。
逆に、塾講師として「なぜこの子は集中できないのか?」と探究する姿勢を持ち続けた人は、療育でも強いです。発達障害は「本人の努力不足」ではなく「脳の特性」によるものと理解したうえで、「環境の調整」や「関わり方の工夫」を行う姿勢が、支援には不可欠です。
実際に活かされたスキル事例
ここでは、塾講師出身者が療育現場で発揮した実際のスキル事例をご紹介します。
①声かけの技術
塾講師は「やる気を引き出す言葉がけ」に慣れています。「できるじゃん!」「昨日より速くできたね」など、具体的な成果に焦点を当てたポジティブな声かけは、療育でも子どもの自己肯定感を育てます。
たとえば、発達に特性のある子は「失敗体験」が積み重なりやすいため、「できたこと」に着目した声かけが心の支えになります。
②教材アレンジ力
塾では、教科書に沿って進めながらも、生徒の理解度に応じてプリントや問題を作り替えることがよくあります。療育でも、「ひらがな表を色分けする」「図形をパズル化する」「計算をゲームにする」など、子どもが楽しく取り組めるような教材の工夫が求められます。
この「教える内容をその子のレベルに合わせて再構築する力」は、塾講師ならではの強みです。

チーム支援への適応――療育の現場で求められる協働性
塾講師は、基本的に「個人プレー」が中心になりやすい職種です。授業の準備から指導、評価まで、自分ひとりで完結する場面が多く、ある種の「個人技」によって成果を出していく側面があります。
一方、療育の現場では、「チームで子どもを支える」ことが大前提となっています。特に、放課後等デイサービスや児童発達支援といった施設では、児童指導員、保育士、作業療法士、公認心理師など、様々な専門職が連携して一人の子どもをサポートします。
このような環境においては、「自分のやり方」だけで押し通すことはできません。周囲と情報を共有し、方針をすり合わせ、役割を調整しながら関わる「柔軟性」と「協調性」が強く求められます。
特に、子どもに何か変化があった場合、それをすぐにチーム内で共有できる「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」の習慣は極めて重要です。塾での経験が長い人ほど、このチーム支援の文化に最初は戸惑うことがありますが、ここをクリアできれば一気に療育現場での活躍の幅が広がります。
塾講師から療育職へ――実際の転職・副業事情
近年、放課後等デイサービスなどの療育施設では、塾講師や家庭教師経験者の採用が進んでいます。これは、学習支援ニーズが高まっている背景と、即戦力としてのスキルを持っていることが評価されているためです。
副業からスタートするケースも多い
最近では、平日の昼間に療育の仕事、夕方以降や週末に塾講師を継続するという「兼業型」も増えています。こうした働き方は、フリーランス講師や非常勤講師にとって相性が良く、双方のスキルを相互に活かしながらキャリアの幅を広げられる方法の一つです。
また、塾ではなかなか得られなかった「子どもの感情面の変化」や「発達そのものへの理解」を学べるため、自身の教育スキルをより深める貴重な機会にもなります。
転職を目指す際に注意したいポイント
塾講師が療育職へ転職する場合、注意点もいくつかあります。
まず、療育の仕事には「福祉」の要素が強く含まれており、利益や成果主義に偏らない視点が求められます。「売上」「成績向上」といったKPIが明確だった塾とは異なり、「目には見えにくい子どもの成長」や「本人・家庭の安心感」を重視する文化の中で働く必要があります。
また、療育施設によっては「児童指導員任用資格」や「保育士資格」など、一定の資格が必要とされる場合があります。無資格でも働けるケースもありますが、採用の幅を広げるためには、通信制大学や講習会を通じての資格取得も視野に入れておくと良いでしょう。

向いている人・向いていない人とは?
療育に向いている塾講師の特徴
塾講師経験者の中でも、特に以下のような資質を持つ人は療育現場で活躍しやすい傾向があります。
- 子ども一人ひとりの「違い」を肯定的にとらえられる人
- 保護者や他職種との関係づくりを大切にできる人
- 「教える」よりも「支える」という意識を持てる人
- 成果を急がず、小さな成長を喜べる人
- 困っている子どもの行動の背景を考える習慣がある人
こうした資質は、たとえ発達障害や療育についての専門的な知識がなかったとしても、後から十分に学んでいくことができます。
逆に、向いていない可能性がある人
一方で、次のような傾向が強い場合は、最初にギャップを感じやすいかもしれません。
- 成績向上や成果主義へのこだわりが強すぎる
- 「言った通りにやらない子はダメ」という価値観が強い
- 待つことが苦手で、すぐに結果を求めたがる
- 保護者対応に苦手意識がある
- チームでの連携が煩わしいと感じる
もっとも、これらは絶対的なNG要素というより、「どれだけ柔軟に価値観を変えられるか」が鍵になります。療育の仕事は、経験を積む中で少しずつ視点が変わり、やりがいや面白さが深まっていく仕事でもあります。
支援現場で変化する「やりがい」のかたち
塾講師として感じる「やりがい」は、多くの場合、生徒の成績が上がった瞬間や志望校に合格した報告を受けたときに最も大きくなります。一方、療育の現場におけるやりがいは、必ずしも目に見える成果ではなく、もっとささやかで、日常の中の一コマにあります。
たとえば、昨日まで椅子にじっと座れなかった子が、今日は3分間集中してお絵描きに取り組めた。言葉がうまく出なかった子が、「せんせい、これ!」と一言声をかけてくれた。これらは、テストの点数には表れないかもしれませんが、その子の人生にとっては確かな一歩です。
塾講師の中には、「こんな小さなことで?」と最初は違和感を覚える人もいますが、やがてそれがいかに尊い「成長」であるかを実感するようになります。
「成績」よりも「自立」や「生活力」がゴール
療育支援の目標は、学習成果よりも「その子が将来、どのように自分らしく生きていけるか」を重視しています。たとえば、次のようなゴールが想定されます。
- 小学校の教室に安心していられるようになる
- お友だちと適切にやり取りできるようになる
- 朝の支度を自分でできるようになる
- 失敗してもパニックにならず、切り替えられるようになる
つまり、支援の目的は「成績を伸ばす」だけではなく、「社会生活を送るうえで必要な力を身につけること」にあります。学びのゴールが変わることで、支援者としての意識も変わっていくのです。
学習支援における「見立て」の重要性
塾講師は、子どもの「わからない」を解決するプロです。しかし、療育では、その「わからない」の背景に、発達特性や認知スタイルが関係している可能性を見立てる力が求められます。
たとえば、「九九が覚えられない」という子に対し、単なる暗記不足と捉えるのではなく、
- ワーキングメモリの弱さがあるのでは?
- 音で覚えるより、視覚で覚えた方がよいタイプかも?
- 数字や記号への感覚に困難がある?
といった視点からアプローチを変える必要があります。
このように、「見立て=支援の入口」として、子どもの困難の根本を探る力が、療育での学習支援においては不可欠です。
学習支援における「見立て」の重要性
特に重要なのが「視覚優位」「聴覚優位」などの認知スタイルを把握し、それに合わせた支援を行うことです。
視覚優位の子ども
- 話だけでは理解が難しく、図・絵・文字などの視覚情報があると理解しやすい
- 口頭説明よりも、板書や手順書の提示が有効
- ルールや予定は視覚的に「見える化」することで安心できる
聴覚優位の子ども
- 話を聞くだけで内容を把握しやすく、読んだり書いたりするのはやや苦手
- 一斉指示や読み聞かせなど、言語によるインプットが効果的
- 細かい口調の変化にも敏感で、声のトーンが影響することがある
塾講師は、すでに「話して教える」スキルには長けていることが多いですが、療育では「見る・聴く・触る」など、多様なスタイルに対応した教え方が求められます。そのため、絵カード、写真、実物教材、ジェスチャーなどの工夫も含めて、伝え方の幅を広げていく必要があります。
保護者との関係構築スキル
塾講師も保護者対応には関わることがありますが、療育ではより深い関係づくりが求められます。なぜなら、発達障害のある子の子育てには、多くの苦労や不安が伴っており、保護者は「理解者」を強く求めているからです。
保護者との関係で大切なのは、「専門家としてアドバイスする」のではなく、「支援者として伴走する」姿勢です。
たとえば、
- 「お母さん、毎日の関わり、本当に頑張っていらっしゃいますね」
- 「今日は○○ちゃんが、自分からお片付けできましたよ!」
といった共感と報告の積み重ねが、保護者にとって大きな安心材料となります。
塾講師の「コミュニケーション能力」は療育でも強みになりますが、「一方的に話す」のではなく、「気持ちに寄り添う聴き手」になる意識が求められます。

教育と福祉をつなぐ存在として
教育のプロである塾講師が、療育という福祉領域に関わることは、現場にとっても大きな価値があります。学習面の支援ニーズは今後さらに高まり、特に小学生以降の発達障害児の学習困難に対応できる人材が求められています。
塾講師の
- 分かりやすく伝える力
- 子どもへの観察眼
- 成長の喜びを共有する力
は、療育の現場にとって非常に貴重な存在です。
一方で、療育が「子どもの未来を支える」深くて長い支援であることを理解し、教育的視点に福祉的視点を加えることができれば、塾講師は療育現場における最強の支援者になれるのです。
塾講師から療育へ転身する理由とは?
近年、「子どもと深く関わりたい」「点数以外の成長も支えたい」という理由で、塾講師から療育の世界へキャリアチェンジする人が増えています。背景には次のような要因があります。
- テスト至上主義に疑問を感じた
- 成績よりも子どもの本質的な成長を見たい
- 受験指導では届かない子どもたちの支援がしたい
塾講師として「もっと寄り添いたい」という想いを持った人が、療育の現場で新たな可能性を見出しています。
キャリア転向のハードルと、その越え方
療育支援への転向には、「福祉の知識がない」「専門用語に不安がある」といったハードルを感じることもあります。しかし、未経験者でも次のような工夫で乗り越えることができます。
①「学び直し」に挑戦する
- 放課後等デイサービスや児童発達支援の現場では、研修体制が整っている事業所も増えており、知識は入社後に身につけられます。
- 発達障害支援に関する書籍や、eラーニング教材などで「自学」も可能です。
② これまでの経験を「翻訳」する
- 「授業づくり」「子どもとの関係構築」「保護者対応」など、塾講師時代のスキルはすべて療育にも応用可能です。
- 特に「個別対応」「指導の引き出し」「変化に気づく目」などは、即戦力として重宝されます。
③ 仲間とつながる
- SNSや研修会を通じて、他の支援者と交流することで、実践知が増えて不安が軽減されます。
- 先輩スタッフやOT・ST・心理士など専門職との連携を通じて、現場知を吸収していく姿勢も大切です。
実際に働くとどう変わる?塾講師から療育支援員への転身例
ここでは、実際に塾講師から療育支援員へ転職したAさん(30代・女性)のケースをご紹介します。
転職前の悩み:
- 志望校合格を目指して日々全力を尽くしていたが、「点数以外の力も伸ばしてあげたい」と思うようになった
- ADHD傾向のある生徒への指導が難しく、「この子に合った教え方ができていないかも」と感じていた
転職後の実感:
- 「自分のペースで頑張る子どもたちを、長い目で見守れることに喜びを感じている」
- 「毎日の小さな変化に気づき、喜び合える仲間と働ける環境がある」
- 「以前のように指導成績に追われることがなく、自分も穏やかな気持ちで関われている」
Aさんのように、子どもに寄り添う力が強い人ほど、療育現場で新たな「やりがい」を見出せることが多いのです。
塾講師から見た療育の「魅力」
① 子どもの個性をそのまま受け止められる
塾では「集団に合わせる」ことが求められがちですが、療育では「その子に合わせる」ことが大前提です。個性や特性に合わせた支援を考える時間そのものが、深く豊かな教育の実践ともいえます。
② 保護者と「子どもを育てるチーム」になれる
塾では保護者との関わりは部分的ですが、療育では「一緒に育てるパートナー」としての関係が築かれます。時には悩みを共有し、時には成長を喜び合う、その信頼関係が、支援者としての原動力にもなります。
③ 子どもとの関係が長期的に続く
療育では、数ヶ月〜数年という長いスパンで子どもを見守ります。その中で「できなかったことが、できるようになった瞬間」に立ち会える喜びは、他には代えがたい経験です。
塾講師の経験を活かすために、意識しておきたいこと
塾講師としての強みを活かしながら、療育でより良い支援者になるために、次のような意識の変化も必要です。
- 「答えを教える」から「考え方を育てる」へ
- 「短期成果」から「長期成長」へ
- 「一律指導」から「個別支援」へ
- 「教える」より「寄り添う」へ
療育では、教え込むよりも「一緒に悩み、一緒に見つける」姿勢が求められます。その柔軟さと謙虚さが、信頼される支援者への第一歩になります。
まとめ:あなたの「教育力」は、療育の現場でも活かされる
発達障害のある子どもたちは、日々多くの困難と向き合いながらも、自分のペースで確かに成長しています。彼らの歩みに寄り添い、その一歩一歩を支えていく支援者の存在は、今後ますます重要になっていくでしょう。
塾講師として培ってきた
- 子どもを見る目
- 教える工夫
- 成長を喜ぶ姿勢
は、まさに療育の現場で求められている力です。
「今までのキャリアをリセットするのではなく、発展させる場所がここにある」
そう感じたあなたには、療育支援という新たな舞台での活躍が待っているかもしれません。
「教える」から「支える」へ。
その一歩は、あなたと子どもの未来を大きく変える可能性を秘めています。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。