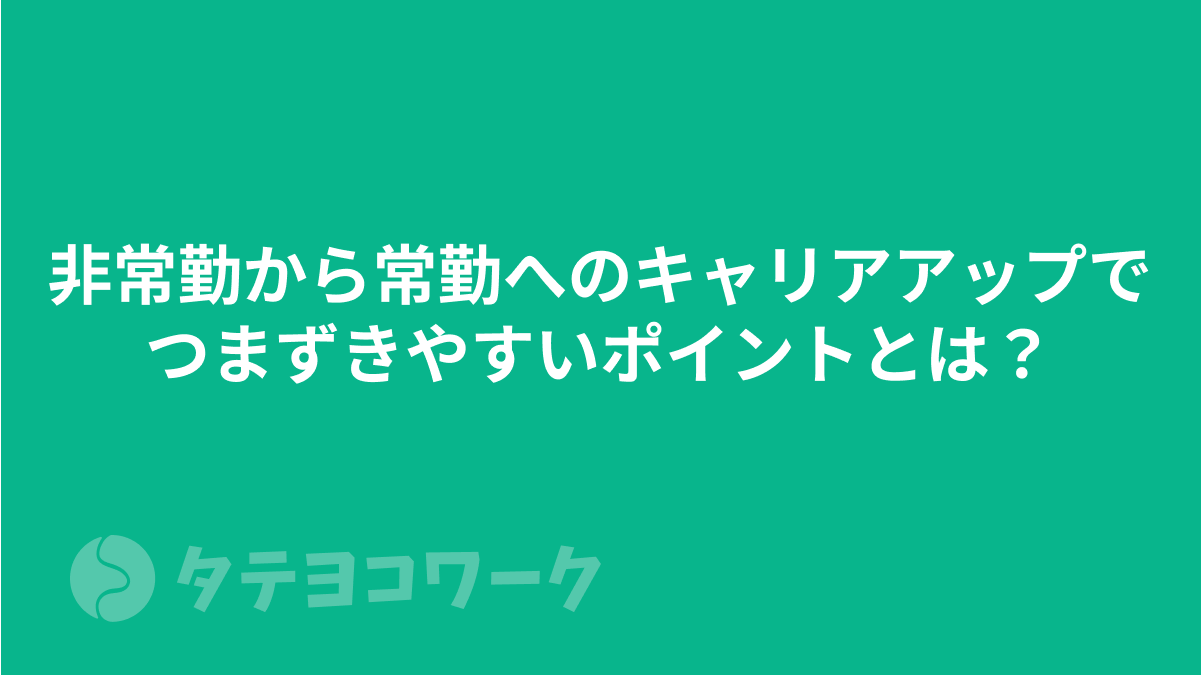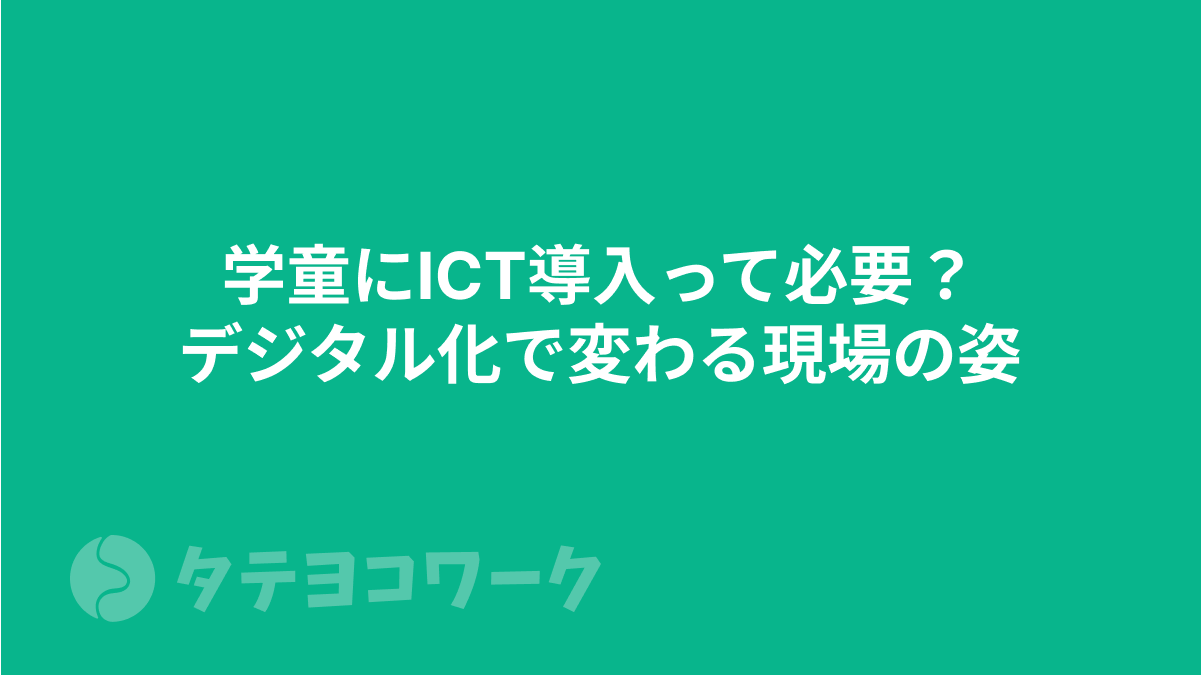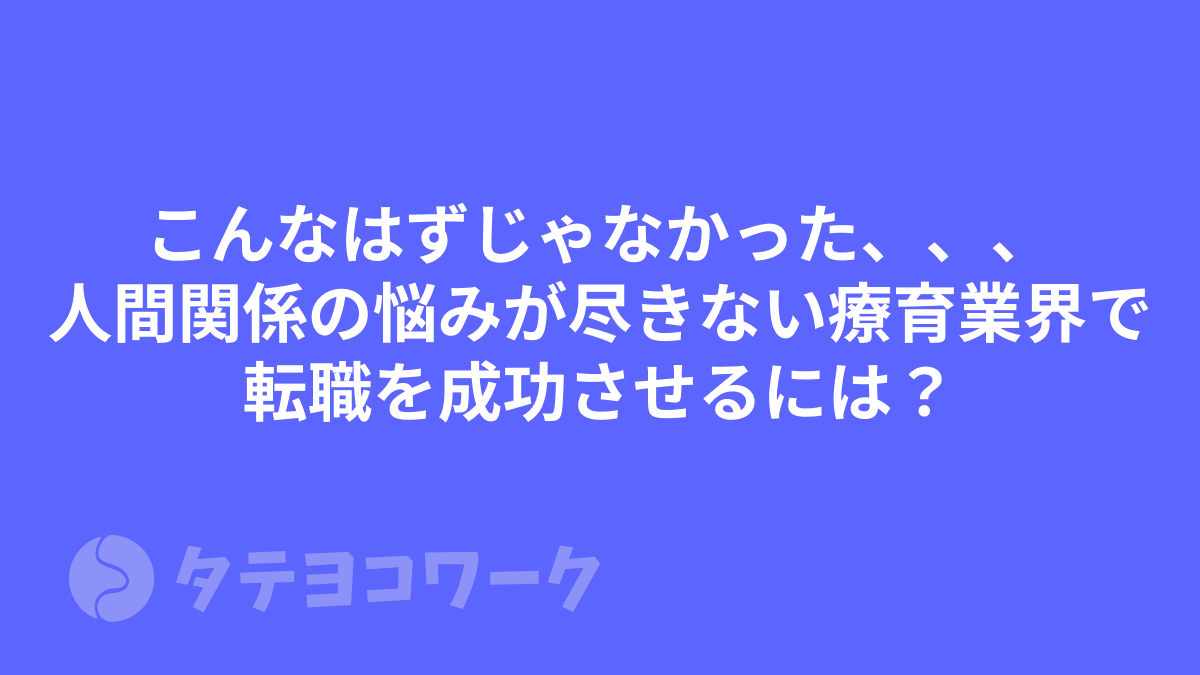タグで絞り込む
キーワードから探す
保育所訪問支援事業とは?サービスの詳細や必要な資格を解説
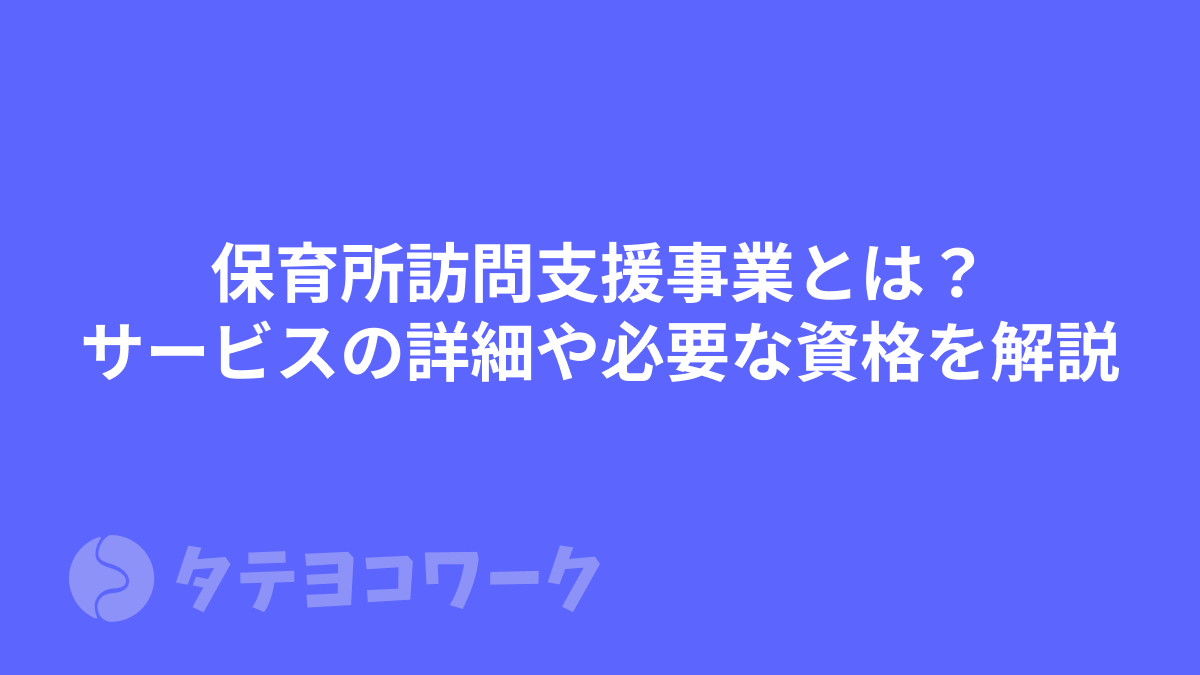
療育
保育士
キャリアチェンジ
児発
放デイ
1.保育所訪問支援事業とは?
保育所訪問支援事業とは、発達に特性のある子どもが地域の保育所や幼稚園、認定こども園などで安心して過ごせるよう、外部の専門職が現場を訪問して支援を行う制度です。子ども自身への働きかけに加え、保育士への助言や保護者への情報提供など、多方面からのサポートが特徴です。
近年、インクルーシブ保育の推進により全国的に導入が進み、子どもの適応支援と保育者の負担軽減の両面で期待されています。福祉や療育の仕事に関心のある方にとっても、専門性を活かせるやりがいあるフィールドです。

2. 保育所訪問支援事業の目的と背景
保育所訪問支援事業は、「すべての子どもが地域で共に育つ」ことを目指したインクルーシブ保育の推進を背景に導入されました。発達に特性のある子どもが集団生活に安心して参加できるよう、専門職が保育現場をサポートすることが目的です。具体的には、子どもの行動や特性に応じた支援方法を保育士へ助言したり、保護者と連携して支援方針を共有したりする役割を担います。
この制度により、子ども・家庭・保育者の三者をつなぎ、成長を支える土台づくりが可能になり、福祉の現場で働く人にとっても、地域支援の最前線に関われる意義深い取り組みです。
3. 対象施設と支援の実施方法
保育所訪問支援は、特定の施設だけでなく、地域にあるさまざまな保育関連施設で実施されています。支援の方法は自治体によって異なる部分もありますが、基本的には定期的に専門職が訪問し、子どもや保育者への支援を行います。どのような施設が対象となり、どのように支援が進められていくのかを知っておくことで、支援に関わる側も安心して現場に臨むことができます。
【対象となる施設】
「保育所等」とされているため保育所や幼稚園などだけをイメージされるかもしれませんが、保育所等訪問支援では次のような「集団生活の場」を訪問することが可能です。
- 保育所、幼稚園、認定こども園
- 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、フリースクール
- 乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ
- 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス
- その他、「児童が集団生活を営む施設」と市区町村が認める施設

4. 具体的な支援内容とは?
保育所訪問支援事業では、専門職が保育現場を訪問し、子どもへの関わりだけでなく、保育士や保護者への支援も行います。対象となる子どもの行動を観察し、発達の状況や困りごとを見極めたうえで、保育士には具体的な対応の方法を助言します。また、家庭との連携を図ることで支援がより効果的に機能し、子どもの安心と成長につながる支援が可能になります。
4-1. アセスメント
訪問支援では、まず実施事業所が子どもの行動や発達状況を多角的に把握する「アセスメント」が行われます。遊びや日常生活での様子を観察し、特性や課題を丁寧に分析します。その結果をもとに、支援の方針や関わり方を検討し、関係者との共有を図ります。根拠に基づいた支援につなげるための土台となります。
4-2. 個別支援計画書作成
訪問支援を行うには、子どもの状況や支援方針を明記した「個別支援計画書」が必要です。アセスメントの結果を反映しながら、支援目標や実施内容を具体的に記載します。計画書は保護者や保育所とも共有され、支援の方向性を一致させる重要な役割を担います。
4-3. 保育所等訪問支援の日程調整
訪問支援は、保育所・保護者・支援者の三者間で調整を行いながら進めます。子どもの在籍施設との日程調整や時間設定は、業務を円滑に進めるための基本です。また、訪問に関する同意取得や必要書類の手続きも丁寧に行うことが求められます。
4-4. 子どもへの直接的な関わりと観察(直接支援)
専門職は保育の場において子どもと実際に関わりながら、その行動や発達の特性を観察します。関わり方は遊びや日常のやりとりを通じて行われ、無理なく自然な支援が可能です。この観察から得られる情報は、支援方法の検討や計画作成に活かされます。
訪問の頻度は月1~2回程度が一般的で、1回あたり1~2時間の支援が多く見られます。
4-5. 保育士や教職員への助言・対応方法の提案(間接支援)
保育士や教職員に対して、子どもとの関わり方や環境の工夫など、具体的な対応策を助言します。現場で抱える悩みに専門的な視点から提案を行うことで、支援力の向上が図られます。保育者自身が安心して子どもに接することができるようになる点も重要です。
4-6. 保護者への情報提供と連携のサポート(報告)
保護者にも子どもの様子や支援の意図を丁寧に伝えることで、家庭との連携が深まります。支援は園だけで完結せず、家庭でも一貫性をもって行われることが理想です。必要に応じて他機関と連携を図ることで、より包括的なサポート体制が築けます。
5. 保育所訪問支援に関わるために必要な資格
保育所訪問支援事業に携わるには、以下のような資格と同時に、障害のある子どもの支援に関する知識や経験があり、集団生活への適応のための専門的な支援の技術を持つこととされています。
保育士や療育現場での勤務経験を活かして訪問支援にチャレンジしたい方にもチャンスがあります。以下に、主な対象資格を紹介します。
・児童指導員
・保育士
・作業療法士
・理学療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員など
6. 保育所等訪問支援を実施する事業所
保育所等訪問支援は、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを運営する事業所が、指定を受けて実施します。児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つとして位置づけられ、事業所は専門職を配置し、保育所や学校などへの訪問支援を行います。支援内容は自治体へ届け出た計画に基づき、定期的に実施されます。訪問支援には、施設での療育経験や保護者対応など、実務に基づく知識が求められるため、経験豊富な職員の配置が望まれます。今後、保育現場との連携を強化する観点から、支援の質を重視する事業所が増加傾向にあります。
7. 保育所等訪問支援の利用対象者
保育所等訪問支援の対象となるのは、障害を持つ児童とされています。保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通いながら、集団生活に困難を感じている子どもが利用できます。支援は障碍者手帳等の有無にかかわらず基本的には利用可能ですが、自治体によっては「医師の意見書」や「療育相談の実施」等が求められる場合もあります。
8. 保育所等訪問支援の利用申請の流れ、費用
施設側からの申請は不可とされており、利用するにはまず保護者が自治体の窓口で通所受給者証の申請をする必要があります。書類等の手続きを進め、自治体から通所受給者証が交付されると支援が開始されます。子どもが安心して過ごせるよう、個別ニーズに応じた訪問支援が行われます。
費用は、基本的に9割が自治体、1割が利用者の負担となります。
9. 保育所等訪問支援業務に向いている人、向いていない人
9-1.保育所等訪問支援業務に向いている人
保育所等訪問支援業務に向いているのは、子ども一人ひとりの発達や特性を丁寧に観察し、柔軟に対応できる人です。保育士や教員、保護者と円滑に連携するコミュニケーション力も求められます。また、施設ごとに異なる環境に対応する適応力や、限られた時間で的確に支援する判断力も重要です。療育や保育に情熱を持ち、現場に寄り添える人に適した仕事です。
9-2.保育所等訪問支援業務に向いていない人
マニュアル通りの対応しかできない人や、状況に応じて柔軟に動けない人は訪問支援に不向きです。また、保育士や保護者と信頼関係を築くコミュニケーション力が乏しい場合も、業務に支障が出やすくなります。多職種と連携しながら子どもを支える姿勢が求められるため、単独で完結したいタイプの人には難しい仕事です。
10. まとめ:保育所訪問支援は“療育×保育”をつなぐ大切な仕事
保育所訪問支援事業は、発達に特性のあるなどの子どもたちが安心して保育施設で過ごせるよう支える、非常に意義のある仕事です。療育の専門性と保育の実践をつなぐ役割を果たすことで、子どもの成長や周囲の理解を深めることにも貢献します。福祉や療育に関心のある方にとって、知識と経験を活かせるフィールドです。
また保育所訪問支援は子ども自身だけでなく、家庭や保育現場にとっても頼れる存在で、専門職による適切なアドバイスや対応が、保育者の負担軽減や保護者の安心感にもつながります。子どもを取り巻く環境全体を支える、縁の下の力持ちともいえる仕事です。
「やってみたい」「関わってみたい」と感じたら、まずは求人情報を確認してみましょう。保育所訪問支援を実施している事業所は増えています。自分の資格や経験を活かせる現場を見つけ、第一歩を踏み出してみましょう。
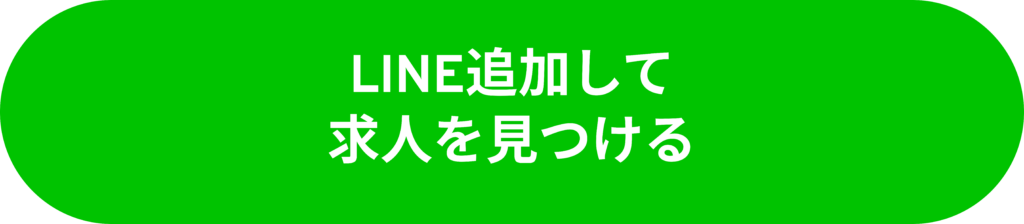
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。