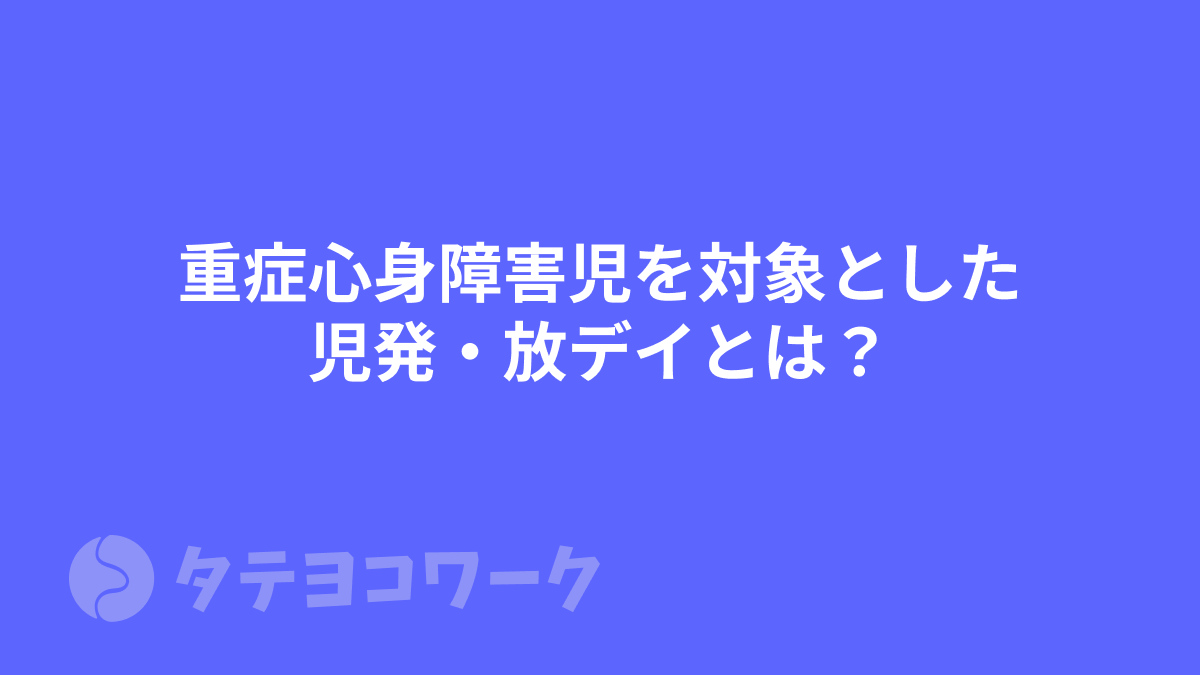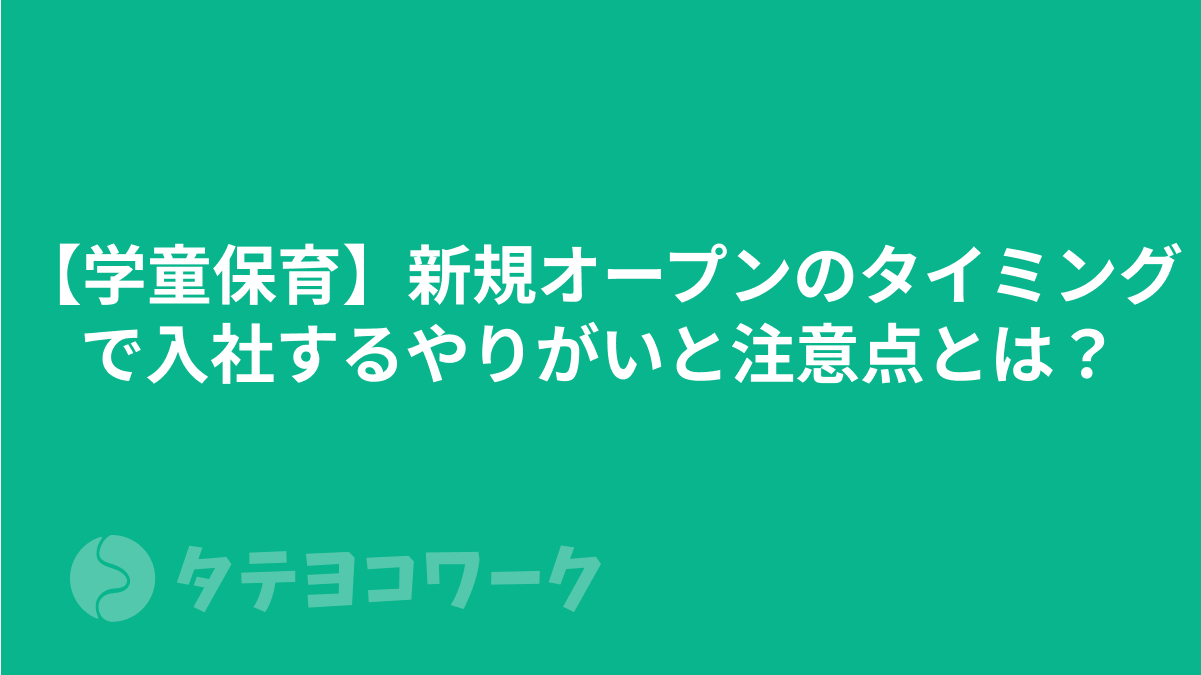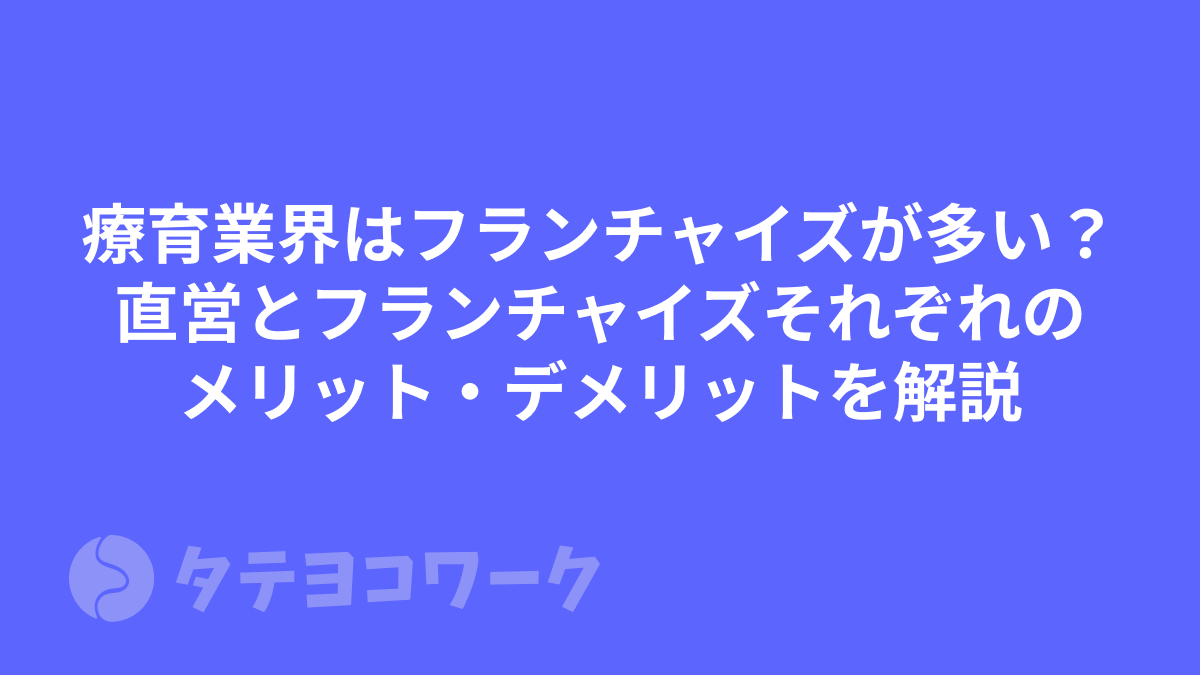タグで絞り込む
キーワードから探す
学童保育における保護者対応のコツ5選
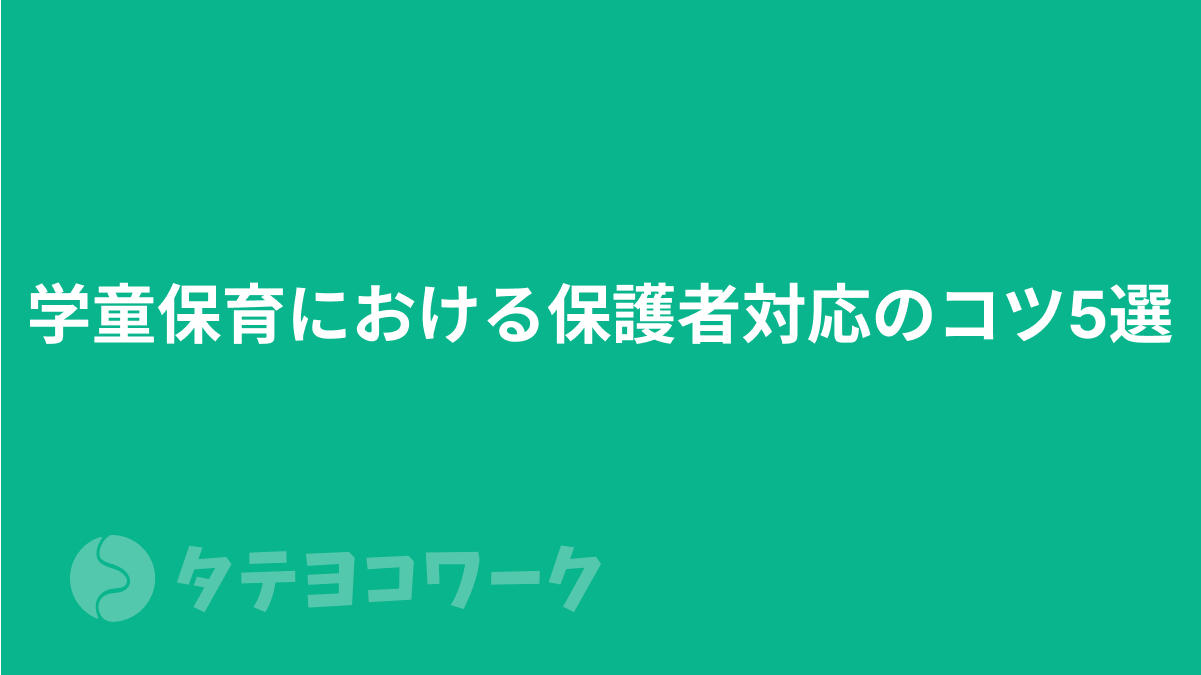
学童
ノウハウ
公立学童
民間学童
学童保育所は、こどもたちにとって「家」と「学校」以外の大切な放課後の居場所であり、働く保護者にとって必要不可欠な子育て支援施設です。そんな学童保育所で、こどもたちがのびのびと健やかに成長するために重要となるのが「スタッフと保護者の信頼関係」。
学童保育所のスタッフと家庭がしっかりと連携し、お互いに信頼しながら、ともに子育てに取り組む “チーム” になれることが理想です。
しかし実際のところ、「保護者と関わる時間が限られている」や「クレームや不満を伝えられることが多く、うまく連携できていない…」など、不安や悩みを抱えているスタッフも少なくありません。
そこで今回は、学童保育所の現場でよくあるシーンを想定しながら、保護者対応をスムーズに進めるための実践的なコツを5つご紹介します!
① 笑顔と明るい挨拶で “安心感” を届けましょう!
小学生が利用する学童保育所は保育園とは異なり、こどもが自分の足で登降所することが多く、保護者が送迎を行わないケースも少なくありません。そのため一人で降所する子の保護者とは、顔を合わせる機会自体が非常に限られています。たとえ日々お迎えに来る家庭であっても、実際に保護者とお話しできる時間は、せいぜい数分程度というのが現実でしょう。
だからこそ、限られた時間とコミュニケーション量のなかで「この学童の先生は信頼できる」や「こどもを安心して任せられる」と思ってもらえるかどうかが、その後の関係性を大きく左右します。
その第一歩としてとても効果的なのが、「笑顔」と「明るい挨拶」です。基本中の基本のように感じられますが、大人数のこどもたちと過ごす忙しい日々の中で常に意識して実践し続けるのは、意外と難しいものです。だからこそ「お迎えに行くといつも笑顔で迎えてくれる」、「顔を合わせると向こうから気持ちの良い挨拶をしてくれる」というだけで、保護者の印象はぐっと良くなります。
さらに、「保護者の名前を覚えて呼びかける」や「目を見て挨拶をする」、「時間に余裕があれば、こどもの様子を一言添えてみる」といった些細な工夫が、信頼関係づくりの土台となります。
② 「こどもの様子」は具体的に伝えましょう!
保護者が学童保育所に期待することのひとつが、「こどもが学童でどのように過ごしているか」の情報です。
「今日は学童で何をして遊んだの?」と聞いても、「忘れた」や「わからない」と、素っ気ない返事が返ってくる…そんな経験がある保護者も多いのではないでしょうか。特に、夜遅くに帰宅する家庭では、こどもとゆっくり話す時間すら取れない日もあるでしょう。
だからこそ、こども自身が話さない・話せないことを、スタッフが代わりに伝えてくれることは、保護者にとって非常にありがたいのです。
・「今日も元気でしたよ〜」
だけではなく、
・「〇〇ちゃん、今日は□□くんと一緒に紙飛行機を作って、何回も飛ばしていましたよ!」
・「いつもよりちょっと元気がないように感じましたが、おやつの時間になると□□くんと一緒に楽しそうに食べていました。笑顔が戻り安心しました」
など、“誰と・何を・どんなふうに” を具体的に伝えるだけで、印象が大きく変わります。
もしお迎え時に伝える場合は、必ずしも自分が対応できるとは限らないため、観察メモを残したり職員間で共有しておいたりすることで、どのスタッフでも報告ができる体制を常日頃から作っておくと安心です。
また、お迎えのない家庭には次のようなタイミングでこどもの様子を伝えることができます。
• 忘れ物の連絡をするとき。
• 行事や持ち物のお知らせ電話のついで。
• 行事や懇談など、地域のイベントで顔を合わせたとき。
忙しい中でも、少しのやりとりで保護者との距離を縮めることができますよ。
③ 情報共有は「早め」&「正確」&「簡潔」に!
保護者との信頼関係を築くうえで、情報の伝え方は非常に重要です。特にトラブルや体調不良など、緊急性の高い事柄については、早め・正確・簡潔な情報共有を心がけましょう。
たとえば、こどもが学童でケガをした場合は、
• いつ・どこで・どのように起きたのか。
• ケガの場所と程度(腫れ、出血、擦り傷など)はどうか。
• 応急処置の内容(冷やした、消毒した、病院受診を検討しているなど)について。
このような情報を落ち着いて丁寧に、事実に即して伝えることが必要です。感情的な表現や曖昧な表現は避け、「〇〇の場面で□□をしていて、△△になりました」と明確に伝えましょう。
対面での報告が難しいときは、連絡帳、メール、保護者連絡アプリなどを活用するのも一案です。あらかじめテンプレートや記録フォーマットを作っておくと、情報の漏れを防ぎやすくなりますよ。
緊急時に限らず日常的な連絡においても、以下のポイントを意識して伝えるようにすると、保護者からの信頼を得やすくなります。
• 要点は最初に伝える(結論から話す)こと。
• 期日・持ち物・手順などは明確に!
• 「お忙しい中恐れ入りますが…」などの配慮を忘れないこと。
忙しい保護者にとって、簡潔で丁寧な情報提供をしてくれるスタッフは「頼れる存在」としてバッチリ記憶されます。
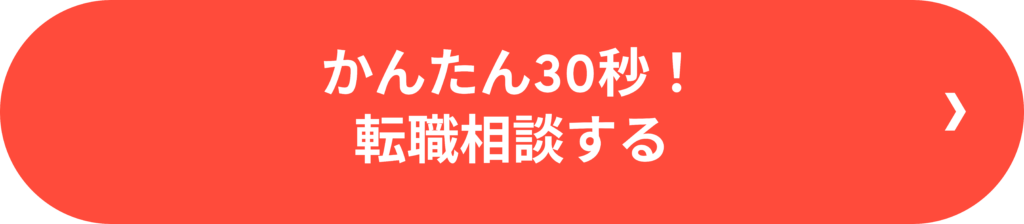
④ クレームや不安の声には「まず受け止める」姿勢を!
どれだけ丁寧にこどもたちと向き合っていても、保護者から不満や不安の声を受けることは避けられません。
思いがけないタイミングで「ちょっと話があるのですが…」と切り出されると、緊張や不安を感じるのも無理はありませんし、自分の行動を否定されたような気分になって傷ついたり怒りの感情が生まれたりすることもあるでしょう。
しかし、そんなときほど大切なのは「まず、しっかりと相手の話を聴くこと」。
反射的に反論したり、焦って謝罪をしたりするのではなく、
• 「この度は、ご心配をおかけしました」
• 「ご意見いただけてありがたいです」
といった言葉を先に伝えることで、相手の気持ちが少しずつ落ち着いていくのを感じられるはずです。
そのうえで、事実確認を丁寧に行い、必要であれば責任者に引き継ぐことも大切です。すぐに解決できない内容については、「確認してからご連絡させていただきます」と誠意をもって対応しましょう。
誠実な対応ができれば、むしろその出来事を通じて信頼が深まることも少なくありません。逆境こそチャンスです!価値観の異なる保護者との対話の時間と考えて、お互いの考えをしっかり話し合ってみましょう。
⑤ チームで情報を共有し、対応を「属人化」させない
保護者対応でありがちな課題のひとつが、“情報の属人化”です。” 情報の属人化” とは具体的に、「特定の職員しか対応内容を把握していない」という状況のことを指します。
例えば、担任の先生や特定のスタッフしかこどもの様子やこどもを取り巻く状況、トラブルの内容について知らない場合、別の職員が対応したときに話が通じず、保護者が不信感を抱いてしまうことがあります。
このようなリスクを避けるためには、チームで情報を共有する仕組みづくりが必要不可欠です。
• 申し送りノートやホワイトボードを活用する。
• 職員間のミーティングを必ず毎日実施する(出来れば朝と昼、昼と夜など2回実施できると良い)。
• グループチャットや共有ファイルなども積極的に導入する。
このように、誰でもすぐにアクセス・把握できる環境を整えて、こどもたちの情報を常に1人のスタッフが抱え込まないようにすることが大切です。
また、「このような場合はこう伝える」といった言い回しの統一や、「対応に困ったときのルール」などをあらかじめ共有しておくことで、チームとしての一貫性が生まれ、安心感を与えることができます。
こどもたちの情報は “生もの” 。さらに膨大な量の情報がありますのでなかなか全てを共有するのは難しい部分もありますが、重要事項の情報漏れが発生しないよう職場全体で協力しながら仕組みづくりを進めていくことが必要です。
まとめ
保護者対応は、決して「完璧にこなさなければならない」ものではありません。むしろ、日々のちょっとした心配りや丁寧に向き合おうとする姿勢こそが、信頼関係の土台を築く大きな力となります。
今回ご紹介した5つのコツは、どれも特別な技術や資格が必要なものではなく、明日からすぐに実践できる小さな工夫ばかりです。こうした取り組みを一つひとつ丁寧に積み重ねていくことで、保護者との関係性は少しずつ、でも確実に良い方向へと変化していくはずです。
こどもたちが安心して過ごせる学童をつくるために、そして現場で働くスタッフ自身が「この仕事が好き」と思える環境を築くためにも、保護者との “よい関係づくり” を大切にしていきましょう。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。